
日本の ジャズの歴史を遡ると芸能界の誕生とのクロスロードに立つことになる。例えば渡辺貞夫である。ナベサダと呼ばれている。ジャズの黎明期、渡辺姓のミュージシャンがたまたま多かったのであるが区別するのに「ナベサダ」「ナベシン」「ナベタツ」と呼ばれていた。「ナベシン」こと渡邊晋が55年に設立した芸能ポロダクションがナベプロである。その片隅を間借りしていたのがジャニーズ事務所と言う事になる。ナベプロ制作の番組「シャボン玉ホリディー」は毎週見ていた。ザ・ピーナッのバックで踊る初代ジャニーズの事を薄っすら覚えている。
ジャニーズ問題が取りざたされている時期you tubeメディアでコメンテーターとして出演している中森明夫の存在を知った。性加害そのものではなくジャニーズにおける父性の欠如という斬新な視点で語っていた。そう言えばメリーの旦那でジュリーの父親が全く出てこなかったことに気づく。父親の名前を聴いた時存在だけは知っていた。藤島泰輔・・・小説家としてである。新聞記者としてキャリアをスタートさせているが人間関係の幅の広さに驚く。先ず上皇のご学友である。若くして亡くなっているがジャニーズ事務所設立の際は後方から支援した。
話は本題に入る。この本はアイドル論である。アイドルと言う言葉を聞いたのは60年代の半ばシルビー・バルタンの「アイドルを探せ」という曲によってである。では日本のアイドルはいつ出現したかと言う事である。僕は麻丘めぐみ位からではなかったかと勝手に思っていた。年頃の男の子に勘違いさせて疑似恋愛体験をさせるという手法である。麻丘めぐみのヒット曲に「私の彼は左利き」というのがある。僕は左利きである。おお・・・やっと自分の時代が来たと思ったのである。矯正されて直した右利きを左利きに戻していた時期がある。だが世の中甘くない。左利きだけではモテないし注目もされない。そうこうしているうちに「左寄り」になりレフト・アローンにのめり込むようになって「左前」になっていった。中森は最初のアイドルは1971年にデビューした南沙織だという。その前にもアイドル的歌手はいた。雪村いずみ、江利チエミ、弘田三枝子などなど・・・だが洋楽の日本版と言う存在であった。南沙織の生みの親CBSソニーのプロデユーサー酒井政利は日本独自の新しいシンガーを世に送り出したい思いでデビューさせた。この時中森11歳・・・論理的に南沙織が日本最初のアイドルと規定できるはずもない。ここに推しという概念が関与する。歌による仮想空間が存在しアイドルとフアンが同一方向に向かっているこれが「推す力」である。そもそもアイドルとは何か。中森は日本憲法を持ち出す。
『天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく』
「アイドルはフアンの象徴でありこの地位は主権の存するフアンの総意に基づく」と読み替えられる。
主権はあくまでフアンに有るとする。ここにはキャンディーズ、ピンクレディー、山口百恵、松田聖子、安室奈美恵など時代を彩ったアイドルの変遷史が分かりやすく綴られている。アイドル界にも批評は必要だという。成熟した芸術、芸能の分野には優れた評論が存在する。評論をただのこき下ろしと勘違いする輩が多い。勿論ジヤズ界も例外ではない。
アイドルは元々未完成のものでフアンとの共同作業で磨き上げられていく。絶対に輝く瞬間が有ると思って支える人が居るから続いている。この見解はジャズに関しても半分だけ当たっている。
「推す力」中森明夫著 集英社新書 1000円
カテゴリー: ブックレビュー
「村に火をつけ白痴になれ 伊藤野枝伝 」栗原康著

伊藤野枝は今から100年ほど前に生きた作家であり編集者であり婦人開放家で無政府主義者であった。女学校時代にのちに作家となる教師、辻順と恋愛関係となり辻は教職を追われることになる。野枝は辻と事実婚状態なるが情熱は収まりきらず大逆事件にも関わったとされる無政府主義者、大杉栄と同棲生活に入る。大杉も自由恋愛思想の持ち主で奥さんと愛人もいたがそこに野枝も入り込んでいった。三角関係ならぬ四角関係である。週刊文春にすっぱ抜かれた元内閣官房副長官、木原誠二を彷彿させる。だがこれが今の話ではない。100年も前の話なのである。栗原が野枝の故郷、福岡の今宿を取材で訪ねた所、お年寄りの口が重たいのである。「あの女の故郷だと知られるのが恥ずかしい」というのである。ある年齢の方の倫理観からすれば想像できない女性だったと推察される。野枝は生まれるのが早すぎた女性である。野枝は平塚らいてうの後を引き継ぎ「青踏」の編集にも携わったが一般女性にも紙面を解放した。野枝はよく言えば共助の精神、悪く言えば使えるものは親でも使えというスチャラカ社員的な何とかなるさと言ういい加減な考えの持ち主でもあった。当然赤貧状態であったがあまり気にしている様子は伺えない。勿論筆の力を緩めることもない。野枝は時代を駆け抜け28歳の若さで大杉ともに特高によって虐殺される。1923年関東大震災の年である。栗原は野枝の情熱が乗り移ったかのようなテンポの良いポップな文体で綴っていく。男性が書いたこの手の評伝に在りがちないやらしさはない。その事がブレディ・みかこのあとがきで明らかになる。栗原は女性になりたかったという。そうか・・・栗原は辻や大杉になって野枝を愛したかったのではなく野枝になって辻や大杉に愛されたかったのだ。女性に読んでもらいたい一冊である。
「村に火をつけ白痴になれ 伊藤野枝伝 」栗原康著 岩波現代文庫¥1120
「女帝 小池百合子」 石井妙子著
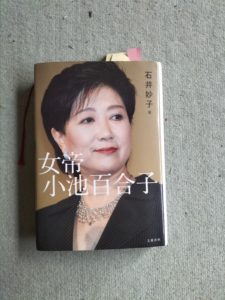
石井妙子のノンフィクション作品はどれも面白い。僕は「原節子の真実」「おそめ 伝説の銀座のマダム」が好きである。これらについてはブログで述べたことがあると思ったがデータが見つからない。ここに至って「女帝 小池百合子」がにわかに話題になっている。これがジャニーズ問題と無関係ではないのである。性加害を受けた人物が実名で告白しその行為が社会を動かしつつあるのだ。「女帝・・」では小池のいくつかの疑惑について述べられている。その一つがカイロ大学主席卒業という勲章である。この本を読んだ人間はそれが経歴詐称であると確信するはずである。だがこの疑惑はマスコミ、ワイドショウでほとんど話題にはならなかった。あまつさえ選挙結果にさえ影響しなかった。この本で重要な発言をしている人物Xサンはカイロ大学在学中のルームメイトである。この本が出版される頃には小池は日本の政界で隠然たる権力を持ちつつあった。実名で出ることに身の危険を感じたという。それで仮名での表記になっている。だがジャニーズの実名での告発に後押しされる形で文庫化されるのをきっかけに実名表記に変更したという。小池百合子の政策は一見まともに見える標語で表現されるがどれもが恣意的な解釈に満ちた自己都合に満ちている。嘘の原点は政界に取り入るために経歴詐称をしなければならなかったこの時期にある。次の選挙で都民が経歴を見逃すはずがない。面白い本である。文庫化で値段もお求め安くなっているはずだ。お薦めである。
パリの空の下ジャズは流れる
だいぶ前の話になるがウディ・アレン監督の「ミッドナイト・イン・パリ」という映画を見た。小説家志望の主人公が婚約者の彼女とパリ旅行に行くのだが12時過ぎると1920年代のパリにタイムスリップするという話である。あるパーティーに行くとそこにはS・Fジエラルドとゼルダがいる。ある時はピカソ、ヘミングウエイと文学や芸術の話をする。ダリ、コール・ポーターもいる。ライブハウスに行くとコクトーや黒人ダンサージョセフィン・ベイカーがいる。百花繚乱のパリ黄金期に取りつかれるストーリーになっている。その辺の文化事情の詳細が分かる本に出合った。それが「パリの空の下ジャズは流れる」である。1920年代から1950年代までの音楽、文学、映画、政治状況が一望できる。ジャズとクラッシックの相関関係、コクトーを通じてジャズとサティ、ドビッシーが影響し合う過程などエピソード満載である。どのページを読んでも小説のように面白い。毎日一話づつ紹介したいくらいだ。ジャンゴがいてルイ・アームストロングがいてエディット・ピアフがいる。スイングジャズの知識がある人には超お薦め本である。2段組み600ページの大作であるので秋の夜長にはもってこいの本である。
「パリの空の下ジャズは流れる」宇田川悟著 晶文社
「戦争は女の顔をしていない」スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチ著
折しもウクライナ戦争が勃発中にこの本と出合った。作者スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチはウクライナ生まれ国立ベラルーシ大学を卒業している。我々がロシア文学について語る時、例えばドストエフスキー、トルストイ、ゴーゴリ、ソルジェニーツィン・・・国籍はと聞かれると口ごもってしまう。正直に言うと何か関係あるの・・と言う事である。因みにゴーゴリはウクライナ生まれである。日本の北海道の住人にとってウクライナとベラルーシの違いは栃木と群馬の違い程度であった。そういう意味でマイノリティーである。第2次世界大戦では両国民ともソビエト軍として戦っている。この本は女性の作者がソ連軍の兵士として従軍した女性のインタビューを元に書かれている。ここでまず驚くのがその軍務が多岐にわたっている事である。衛生兵や兵站の補給係りなら想像に難くないが狙撃兵、機関銃討手、攻撃砲隊長、戦車隊員となると日本的発想では追い付かない。日本で戦争は男性が行いは女性は銃後の支えが仕事である。ここでこの本のタイトルが重要性を帯びてくる。「戦争は女の顔をしていない」・・・・戦争文学で女性が主役になることはほとんどない。そういう意味で女性もマイノリティーに属する。マイノリティーであるウクライナ人が戦争文学ではマイノリティーである女性の性別を背負ってマイノリティーである女性兵士の事を書いているという構図になっている。そうすると戦争の違った側面があぶり出されるのである。延べ500人以上の女性の回答だけが墓地に並ぶ無数の墓名碑の様に佇んでいる。著者がどう質問したかは書かれていない。ここに掲載されている話に至るまでのイントロが有ったはずである。すべてカットされてテーマから入る。500ページのボリュームであるが一気に読む必要はない。一日2.3人の無名戦士の話を聴くだけで良い。戦争文学の傑作・・・例えば大岡昇平の「野火」等を読むと「もうわかりましたから、勘弁してください」という気持ちになることが有る。この本を読んでもそうゆう感情は湧いてこない。戦争期であっても日常や楽しいことだってあるという事実が散りばめられている。
平野啓一郎著「三島由紀夫論」
ブックレビューのコーナーなのに読んでもいないしまだ買ってもいない。月に二度とジュンク堂を舐めまわすように徘徊している。半日がかりである。勿論購入予定の本が何冊かは有るのであるが新しい本との出会いを求めて歩き回るのである。それは顔見せで客を牽く吉原の赤線地帯を歩くようなものだ。本が私を買って・・・と呟いているのが聞こえてくる時が有る。それが楽しみで本屋に出向くのだ。ネットで買って届けてもらうようなことはしない。その日は上記の「三島由紀夫論」他数冊購入するつもりであった。だが漬物石にもなろうかというそのボリュームに圧倒されてしまった。そして帯に書かれていたそして著者23年にもわたる渾身の力作・・・という推薦文に二の足を踏んでしまう事となる。もう一度三島の主要作品を読み直してから読もうと思った。平野啓一郎は三島の再来と呼ばれた作家である。処女作「日蝕」はこんな文章大学生が書けるの・・・と驚いた記憶が有る。三島の「金閣寺」は暗い吃音を持つ若い修行僧の生活を華麗な文体で表現している。その文体は遺作豊饒の海4部作まで引き継がれている。だが三島は純文学の読者以外の層を意識した中間小説的なものも多く書いている。70年代、10歳年下の大江健三郎が鬱屈した時代に性的なものでしか対抗できない若者の生態を書いて大学生に圧倒的な支持を受けた。その頃には押しも押されもしない文学会の重鎮になっていた三島が嫉妬していたと言う話を聞く。スランプ期にはテレビに出演し演劇や映画に手を染める一方ボディビルで体を鍛え薔薇族というゲイの雑誌の表紙を飾っていた。そして森田必勝という右翼青年と出合う事になる。1970年市ヶ谷自衛隊駐屯地でクーデターを呼びかけ三島と一緒に自決した人物である。この事件は三島事件と呼ばれ昭和の10大事件の一つに数えられている。だが思想的には森田事件と呼ばれるべき事件であった。三島が有名人であったからに過ぎない。「ライトハウスのリー・モーガン」というアルバムが実はベースのラリー・リドレーのリーダー作であったという事実に似ている。戦後三島は一貫して「自分はノンポリである」と言い続けていた。それが森田との出会いによって楯の会に繋がる政治活動として結実していく。森田は三島と初めて会った時「君は私の作品を読んだことが有るかね」と聞かれた。森田は「先生の作品は1冊も読んでおりません」と答えた。三島は下手にフアン的は人物が入会してくるようでは困ると言って森田を褒めたという。だが森田は全作品読破していたのである。1969年三島と東大全共闘の討論の事は以前映画のコーナーで述べたことが有る。その時森田も三島に何かあってはならないと会場に詰めていた。講演で学生に向かって天皇について述べてくれるなら行動を共にしても良いとまで発言している。天皇との近さにおいては三島はエリート意識が有る。何せ学習院を首席で卒業した際天皇から直々銀時計を賜わったことを誇りにしている。11月25日市ヶ谷駐屯地に向かう前「天人五衰」の最終原稿を編集者に渡している。そんな三島の人となりを含め全作品、そして三島の読んだ文献をも読み込み論を展開している。・・・・らしい。何せまだ読んでいない。だがとんでもない労作であることは分かる。平野啓一郎は信頼できる作家である。
話は少し飛ぶ。あるjazz研OBが高校の国語の授業の時村上春樹が三島由紀夫の影響を受けていると教わったと言った。村上春樹はSF.ジエラルド、Tカポーティ、Rチャンドラーの影響下にあり好きな作家はレイモンド・カーバやポール・オースターであることを知っている。僕は以上の事実をもって否定したが妙に引っかかる部分が有った。三島の影響かは分からなかったが日本的な香りがするところが有ったのだ。いつか三島を読み直さなくてはと思っていた。その後「村上春樹隣には三島由紀夫いつもいる」佐藤幹夫著を見つけた。2006年第一版である。その先生はこの本を読んでいたのだろうか。
付記
「みしま」と入力すると最初に「三嶋大輝」と出てきてしまう。それ程三島由紀夫とは遠ざかっていたと言う事である。
「セブンティーン」大江健三郎著
2023年3月3日大江健三郎が亡くなった。高校から大学にかけて僕は熱心な大江の読者であった。だがここ15年くらいは大江の本を開いていない。もう何年前になるだろう。大江の新刊が出た時、手には取ったが結局買わなかった。決別する時が来たように感じていたのだ。亡くなったと聞いた時代表作を一冊読んで追悼文書きたいと思っていたが中々手が伸びなかった。高校の時鮮烈な印象を持った作品を冒涜してしまいそうな思いに駆られるからだ。
まだ小学校に行く前の事である。親の言いつけを勘違いして自宅で一人かなり夜遅くまで留守番をしていたことが有る。電気くらい付けられたはずであったが何故か真っ暗闇の中で帰りを待っていた事を今でも覚えている。だんだん暗くなりこの世界に自分一人しかいなくなりその時間が無限とも思われるほど長かった。これが死の概念と繋がると知るのはだいぶ後の事となる。
次の文章は大江健三郎の「セブンティーン」の一節である。
「死ぬ瞬間の苦しみよりも、死を死に続ける時間の長さが途方もないことが恐ろしい、という感覚。
俺が怖い死はこの短い生の後、何億年も俺がずっと無意識でゼロで耐えなければならない・・・・」
この文章を読んだとき子供の時あの暗闇の中一人で膝を抱えて待っていた時の恐怖感の意味を分かったのだと思う。死と言う得体のしれないものを文章で示してもらった。少しだけ気が楽になった。だがそれを受け入れのにはその後半世紀掛かることになる。
そんなことを教えてもらった小説である。
合掌
戦争の作り方
この国が戦争に近づいているのではと危惧した有志によって製作された絵本である。
このブログを読んでいる方でお子様をお持ちの方は1100円の投資で次世代を救えるかもしれない。
クラウゼビッツは「戦争論」で戦争をできる3条件について述べている。
1. 政府の能力
2. 軍事力
3. 国民の理解と熱狂
この3要素が揃わなければ戦争は出来ないし、やっても必ず負ける。1は全くない。2は去年から慌てて準備している。3も主にテレビを通じて危機感を煽り植え付けようとしている。
戦争前夜の状況を次世代に引き継ぐことも必要かと思うのでおすすめ本とした。
コンプレックス文化論 武田砂鉄著
今日買ってきた本なので読み切ったわけではない。前書きを読んで目次を眺めていた。コンプレックからどのような文化が生まれてきたかを考察した本である。章別に色々なコンプレックスが列挙されている。天然パーマ、下戸、一重、親が金持ち、遅刻、背が低い、ハゲ等々。遅刻の章をぱらぱらめくってみた。ひよっとしたら日本jazz界の大御所Oさんの事が考察されているかと思ったが名前はなかった。この章は後でゆっくり読むとする。やはり気になるのはハゲの章である。僕はハゲに関しては新主流派jazzに関してくらいうるさい。僕の頭髪事情に関して説明しておく。20代の時から若白髪でアンドレ・プレビンのピアノくらい白かった。ぺいぺいの会社員だった頃上司と銀行周りをしていた時の事だ。融資課長が僕に向かって預貸の話をするのである。「あの、課長はこちらです」と言った時の融資課長の驚きの顔を今でも覚えている。会社の戻ってから上司に「お前髪染めてこい」と言われた。白髪は禿げないという言い伝えがある。ガセネタである。30代の半ばで円朝の怪談噺の様にバサバサ抜ける時期があった。いちおう会社員なので今の様にバリカンで五分刈にするわけにもいかず中途半端な髪型にしている時期があった。それでもハゲに悩んだことは全くない。僕みたい感覚を持っているのを「ポジティブハゲ」という事をこの本を読んで知った。こういう事を研究している人がいるのだ。「禿を生きる 外見の男らしさの社会学」須長史生著の中で「ポジティブハゲ」の問題点を3点指摘している。一点だけ紹介しておく。禿げた男性に特定のイメージが付着した男性像(明るい、精神的に強い、外見を気にしない)を要請しているとある。自分の事を言われていると思った。このような「ポジティブハゲ」によって救われるのはごく僅かであり有害ですらある。ええ・・・と思ったが思い当たる節がある。自分はある分野は気を使って話すがある分野は雑になる。相手の立場で考えることの大事さを思い出した。勉強になる。
禿げはありがたがられる抜け道がある。例えば「デブ」「ブス」と公式の場で発言したとしたら一発レッドカードである。ドリフターズのコントで加藤茶がハゲカツラを被って「あんたも好きね」と言ってもセーフなのである。それは坊さんの世界では毛が生えている人より剃髪している人の方が徳が高い気がするからである。この本でも述べている。瀬戸内寂聴が剃髪してるからこそありがたく話を聞くわけでサザエさんみたいにチリチリパーマだとしたらありがたくないでしょう。そうかもしれないと思う。
気持ち良く禿げているストーンズのキース・リチャーズがミック・ジャガーがナイトに叙勲された時のセリフがいかしている。知りたい方は本を読んでください。
付記
本の紹介と言うよりハゲ談義になったしまった。ついでなのでハゲネタを紹介しておく。今バンクーバーにいるマークが言っていた。カナダは髪の量で散髪代が違うらしい。
「俺ならいくら」
「マスターはほとんどタダだな」
臼庭と例によって駄洒落を言っている時の事だ。ミュージシャンにあだ名をつけていた。小樽の素晴らしいサックスプレーヤーOは時々フルートを吹く。「ハーゲーマン」でどうだというところで話は落ち着いた。回りまわって本人に伝わってしまいむっとしていたという話を聞いた。その時僕は「ポジティブハゲ」と言う用語は知らなかった。
点字からはじまるメッセージ 吉田重子著
著者の重子さんは月一回のlazyのセッションにはほとんど出席する。時々ライブにも来てくれる。ホストの本山にピアノを習っている方だ。著作のタイトルから推察できる通り視覚障碍者である。最初に来た日にはスティビー・ワンダーみたいな凄い人が来たらどうしようと思っていたが一緒に楽しんでくれるレベルで安心した。その事を重子さんに言うとちょっと悔しそうではあったが笑ってくれた。来ているお客さんはみな親切な方なので店内の誘導や、帰りも地下鉄駅まで送ってくれたりする。僕も時々迎えに行ったり送ったりする。すると今まであまり気にならなかった点字ブロックや地下鉄の転落防止柵の事が気になるのである。重子さんは僕のブログを読んでくれておりコメントをくれることもある。まずどうやって読んでどうやってコメントを書くのだろう。そして見送った後はどうやって帰宅するのだろう。食事は・・・買い物は・・・旅行は・・点字の楽譜はあるのだろうか・・・とかいろいろな疑問が湧いてくる。だがどこまで聞いていいのやら根掘り葉掘り聞くのも失礼かと思案していると良い本を紹介してくれた。それがこの本である。視覚障害に限らず一枚皮をめくると世の中色々な問題が山積している。勿論音楽界にもある。だがこの本では政治的側面にはふれていない。健常者の理屈で回っている現実を違った視点から見ることは非常に有意義である。そこには想像力が働く。想像力はどの分野にも役立つ。
重子さんは社会意識の高い方である。それはブログ「右往左往日記」を読むとわかる。一度覗いてみていただきたい。
最近は呆れる政治社会問題が多すぎる。重子さんと緩く話し合う場を持てないかと相談している。上記の本読みたい方はレンタルします。
付記
8月末からの一大イベントに暗雲が垂れ込めている。トピック欄をご覧の上ご支援を賜りたい
