
三嶋は昨年来ベース・ソロをやり始めている。彼が初登場してから7年くらい経つのだが、それ以降、上昇気流に乗って今日に至っていることは衆目の一致するところだろう。筆者はレイジーでのライブでしか三嶋を聴いていないが、この間の彼の足跡を見極めるにはこれで十分である。何故なら三嶋自身がレイジーでのライブ体験が、飛躍の引き金になっていると吐露しているのだ。
まぁ普通はベースのソロ・ライブとなれば、”So What?”という突き放した反応が予想できる。だが実際のところ、想定外の客入りとなっていたのである。三嶋を起用している貞夫さんを肌で知ることのない若者たちも来場していた。この事態は音楽的な才知以外にも三嶋に人を引き付ける何かがあるのだろう。しかしそれに増して気に止めておくべきは、普段のリズム・セクションの一員とは異なる重石を自らに課すSolo演奏という彼の選択である。ここには一定の到達点に届いた現状を、今一度振り出しに戻して新たに自己確認を試みようする熱意が窺える。そしてその気迫は演奏に連動していく。欠伸が出たら帰るとあらかじめ釘をさしておいたのだが、緊張感を孕んだ演奏は止むことがなく、筆者の予見を覆す嬉しい大誤算になってしまった。このSolo演奏に臨んだ彼の覚悟には濁り一つないと、感傷すら滲んできた。そして全曲に亘ってOne Bass Hitを放ち続けた様子は、今日の三嶋の全貌を捉え切っていたと言っていいだろう。滅多に聴く機会のないベース・ソロではあるが、今般それに接し大変恐れ入りました。演奏曲は「Goodby Pork Pie Hat」、「Hallucinations」、「For Heaven’s Sake」、「Violets For Your Furs」、 「Soon I Will Be Done With The Troubles Of The World」、「No More Blues」、「Luiza」、「Star Dust」、「陰のみぞ知る」、「Time After Time」、「Blues In The Closet」。
前段でも触れたが、三嶋にとってレイジーは単なる活動の場ではない。それは東京でも共演が叶わぬ先導者たちの胸を借りることを可能にする幸運と転機を呼び寄せる場だったのである。その縁は思わぬ広がりに繋がることもあった。2年余り前になろうか、東京のとあるライブ・ハウスにて三嶋率いるトリオと池田篤、松島啓之、鈴木央紹という夢の共演が実現していた。そのライブで、三嶋は「今日の素晴らしい機会が実現たのも、札幌のレイジー・バードという店にお世話になったのが切っ掛けになっているのです」と率直に語っていたらしいのである。今回のライブの帰りがけに「本当はSolo活動のスタートをレイジーからにしたかった」と胸の内を明かしてくれた。そういう純真さを備えた好漢が三嶋大輝なのである。
(M・Flanagan)
カテゴリー: ライブレポート
2025.3.1 松原慎之介Quartet

松原慎之介(as)布施音人(p)高橋 陸(b)中村海斗(ds)
この若者たちの発散するエネルギーに羨ましさを感じてしまう。ウズウズしながら出番を待っているような気合に満ちた雰囲気はそのまま演奏に直結していく。余計なサービスを排し、思いの丈やろうとする意志のみが一灯照らしているといった具合だ。その演奏は殆ど途切れることなく突き進む。このノンストップ・エキスプレスの乗り心地は中々のものだ。場内は発車してから乗客が増え、何時の間にか満席になっていた。さて、この4人を個別には聴いていたので力量は確認済みであった。これがひと纏まりになると、果たしてどんな景色を提供してくれるだろうか。言ってしまえば、相当に熱っぽい景色だ。筆者が注目していたのは、熱っぽさの質が各自異なっているところである。仮に炎が、白色から赤色の幅に納まるとするならば、布施はやや白寄りで松原と海斗は赤寄り、高橋は中間色付近で両脇に対応していると言った感じになる。こういう個々の陣取り位置が、彼らのサウンドを同質一辺倒になるのを食い止め、多彩な展開を可能にしているのだと思う。これがSS席から定点観測した印象である。演奏曲はオリジナルで占められている。彼らにとってオリジナルとは、新時代のジャズを希求しようとする突破口として想定されているのだろう。それらの曲を通じて、高速up downフレーズ然り徐行フレーズ然り、アイディアに溢れるものとなっていた。そこに危な気ないことに従う気配は全くない。これは今やれることを目いっぱいやり切るのみと主張しているに等しい。だがこの主張は波乱を敵に回すこともある。何でも彼らの前向きさは、勢い余って小突き合いの場外乱闘に発展することもあったと聞く。この頑なさ、濁っていないなぁ、ウン。演奏曲は「Black Dawn(海斗)」、「Autumnal Mood(布施)」、「Myo(布施)」、「Little Warm Winter」(海斗)、「Dr. Blythe(海斗)」、「Lapsed Away(布施)」、「Beyond Solstice(布施)」、「High Ace(慎之介)」、アンコールはエリントン「I Got It Bad And That Ain’t Good」。
自称ハンサム・ボーイ のリーダー慎之介は少年時代からレイジーと縁がある。LIVEを聴いて向上心を高めるために度々訪れていたのだ。その傍らシット・インを狙ってもいた。ここの鬼軍曹はそれを容易に受け入れることはなく、筆者もその様子を何度か目撃している。その少年が今や新世代の最前線に立っているのは感慨ひとしおである。今回その最前線を見せつけられ通して気分は上々となった。真剣に喰い入っていたのだろう、終演後は少々ヘトヘトだ。 気合を入れ直さねばいかん。
なお、メンバー各自、またレイジーで演りたがっているようである。ブッキング成立を期す。
(M.Flanagan)
2025.1.25 Classic Duo 按田佳央理(flu.)亀岡三典(g)
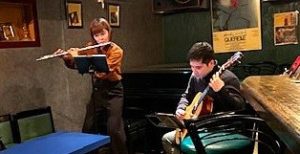
既にその才気実証済みの按田(通り名:あんちゃん)と、その名も演奏も初めての亀岡とのデュオ。クラッシック・ギターを生で聴くのは2度目である。一度目はキタラホールの後方席だったので、至近距離というのは心をくすぐる。至ってシンプルな動機で足を運んだ。
さてさて、レイジーは徹底して真摯にジャズ・ライブを発信するアジトだと思ってきた。従って、ここんところのクラッシック・プロジェクトは、幾ぶん気まぐれかなと勘ぐっていたのだ。ところが数度聴いた成り行きで、何やら本気度が見え隠れし始めたのである。想像でしかないが、ジャズに対する仮借のない視線が、この乱心の中心部にあると思うのだ。改めてジャズを考える切っ掛けとして仕組んでいるのではないかと言い換えてもよい。それはそうと個人的にクラッシックを全く聴かなかった訳ではないが、ひいき目に見てもそれは貧弱なものと認めておかねばならない。その程度の筆者ではあるが、クラシカル音楽のライブを目の当たりにすると、興味深いこともある。演奏家が曲の生まれた背景に注意を怠らない姿勢が明快に確かめられるのもその一つである。今回も二人のMCのやり取りからそれを窺うことができる。一概には言えないが、コード進行をもとに各自の調和意識任せ?のジャズ演奏は本質的に出たとこ勝負の性格があるので、いつも成功と失敗が枕を並べているように思う。両者の違いを優劣を超えた違いとして認めておけばよいのだと思う。クラッシックを聴いている時はそこに浸っているのだが、聴き終わるとジャズの浸り方との違いを 考えたりする。それでニンマリしているのが筆者の聴き方だ。これでは正統派のリスナー仲間には入れて貰えそうにないが、邪道 of my smileで支障なしだ。これ以上音楽の聴き方について四の五の言うことはよそう。
ライブの進行概要は、プッチーニの楽曲に始まり、「タイスの瞑想曲」、「ブラジル風バッハ」など本格もので聴く側をピン止めして序盤を制したあと、たちまち一路南米はブラジルに直行する。ボサノバやスイング感のあるショーロのビートが決め所を作っていく。やがてアルゼンチンのピアソラに移動してひと盛りあがり。何でもピアソラは、ダンスの伴奏サウンドだったタンゴを自立した音楽として確立しようとする野心を持っていたそだ。ふむ、勉強になるな。全編を通すと、純シリアスなものもあれば、少し娯楽性を混ぜ込んだものまで十分練って来たという感じだ。アンコールはベートベンの「悲愴」だ。これは二人のプライドなのかファン・サービスなのか判然としないが、演奏会の着地に相応しく一糸乱れぬ終了間際の追加点といったところだ。
その昔、ラジオの深夜放送で”カメ&アンコー”なる人気パーソナリティーDuoがいた。”亀&按”これは使えるなと思ったが、それでは演奏に向き合う真剣みが足りなく反省しきりだ。この日ライブに来る前のそわそわ時間に、クラッシック・ギターの物悲しい音色が聴きどころの映画ディア・ハンターに使われた「カヴァティーナ 」が演奏されるのを予感していた。だが見事に外れた。その代わりゴースト・ニューヨークの幻、「あんちゃんド・メロディー」をタップリ聴けたことで良しとしようかな。
(M・Flanagan)
2024 Live For 歳末 Sale

12.19 布施音人TRIO 布施音人(p)若井俊也(b)西村匠平(ds)
ここ10年くらい若手を聴くのは殆んどレイジーのライブを通じてのことになっている。おまけに彼らの作品セールスには殆ど貢献していない。せいぜい30年位までの作品群において区切りをつけているからだと思われる。従って新譜に気を引かれることは余りなくなっている。けれども生演奏は、事情が違っている。目の前で繰り広げられる直接性にアルバムとは異質ものがある。それを証明する唯一の場がライブだ。そのライブ空間において、特に初めて聴く若手に感じ入ってしまうことがが少くない。今回の布施も初めてだが、最初はやや内省的に聴こえていたが、あながちそうでもなくお馴染みのスタンダードをとって見ても、適度なエモーションと随所に耳にしたことのないような音使いがあり、曲に新たな一命を吹き込んでいる印象を受けた。こういう時の気分の飛距離は予想以上に伸びているのだろう。端的に言って布施は可能性の塊だ。何でも来年の3月に管を交えてやって来るとのことだ。極道の妻たちにフレーズを借りれば「あんたら覚悟しぃやぁ」といったところか。演奏曲は「Isorated*」、「Tow For The Road」、「Country」、「Sado*」、「I’m All Smiles」、「East Thirty-second」、「White Lycoris*」、「I Love You」、「Guess I’ll Hung My Tears Out To Dry」、「Ladies In Mercedes」、「Beyond The Solstice*」。*は布施のオリジナル。
12.20-21 池田篤Quartet 池田篤(as)布施音人(p)若井俊也(b)西村匠平(ds)

雪ある時の池田は危険だ。何度も転倒し怪我も負っている。最近は危機管理が徹底されていると見えて、事なきを得ているようだ。それはさて置き、最新作の「Taste Of Tears」はスタンダードのコード・チェンジに、別メロを乗っけるという構想で仕上げたという。これをコントラファクトというらしい。このライブでも数曲演奏されたが、同作のトリックに気を取られるとが散るので、ひたすら池田を聴くという態度に徹した。それは身を尽くすように疾走する池田の魅力に浸りたいためである。そして「やっぱり池田だよな」と相好を崩す。その魅力の一方で、ある時を境にしてバラードの池田を聴きたくなっている自分に気が付いていた。そんな折に心のリクエスト曲「Flame Of Peace」が演奏された。こういう時は軽い動揺を伴いながら、この演奏だけでも来た甲斐があったっと思わせる。少しづつ淀みを漂白していく演奏がそこにはあった。この1曲をして全体をまで拡張させしめることはできないが、そう思わせるものがあったとだけ言わせて頂く。なお、布施の父親は若き池田と知り合う親友だとのことで、これは人の縁に隠されたほのぼの話だ。あとの二人にも触れておく。レイジーと若井・西村の関係は、地銀と地元企業のようなもだ。今後とも双方の推進planが嚙み合い、円満に音富(コレ当て字)が達成されるよう願う。まぁ本節は”胸に飛び込む池の音 ”に尽きる。
演奏曲は「Green Dolphin Street」、「Typsy 」、「Nearness Of You」、「End Of Summer Is Just A Little Bit Sad」、「Roller Coaster」、「Flame Of Peace」、「Tangerin」、「Body&Soul」、「Take The Coltrane」、「All The Things You Are」、「On The Trail」、「Jitterbug Walz」、「Never Let Me Go」、「Star Eyes」,「Every time We Say Good by」、「Yes Or No」、「For A Little Peace」など。
今年の大詰めを、この2編成のプレイヤー達が至って締り良いものにして行った。通常のダブル・プレーとは2つのアウトを指すが、このLive For歳末Saleは、それが2つのセーフでもあり得ることを知らしめてくれた。ウソが下手と言われている筆者が言うのだから信じて欲しいな。
(M.Flanagan)
2024 Lazybird Watching

「今年もあっという間でしたね・・・」、かつて聞き流していた会社トークが、今頃になって身に染みる。レイジー・ライブで誰と誰の編成だったのかが明快に思い出せないことがよくある。しかも今年のことだったかどうかさえ怪しくなる始末だ。こういう時は、レイジーはマルチ実験の場だからシャーないと決め込むことで窮地を逃れている。そんな曖昧meではあるが、先を進めよう、まずは<上半期>から。年始のことはよく覚えている。タツル・里菜DUOで暖かみのあるスタートを切った。冬季は行動が鈍りがちになるが、2月に入ると田中菜緒子が若井俊也と柳沼を従えて一仕事をこなし、この流れで噂のギター平田晃一を聴くことができた。正統派の旗手だ。3月の記憶は田中朋子sextetで、朋子さんのallオリジナルにシミジミした。そして久し振りにフルート&ベースのDUO、アンタのバラードに好感。4月に突入、いよいよ粉骨砕身20周年の体当たり企画が実現した。一人づつならいざ知らず、このメンバーを札幌に集結させるだけで至難のことだったと思われる。そこから新たな物語が綴られていく。第1章は壺阪健登トリオ(楠井・珠也)、第2章はクライマックスとなる鈴木央紹参加のカルテットである。珠也は高を括ったように「ヤツとは、1,2回しか演ってなくてよォ」と反り返って言っていたのだが、演奏が始まるやいなや尋常ならざる異例のパフォーマンスとなってしまった。これは数あるレイジー・ライブのなかで最高峰に位置するものと確信する。珍しく央紹による調性にソッポを向いたような演奏が聴けたのは貴重。本人曰く「なんちゃってフリー」なのだそうである。壺阪のオリジナルが主体であったが、”Never Let Me Go”のようなスタンダードは全員の理解度の深さが結合されていて一言には置き換えられない。そして書かれざる終章は札幌から持ち去られた。珠也の男気によって東京で”レイジー・バード・リユニオン”なるユニットとなって20周年特別企画が継続されたのである。この突出した決断にはちょっと目頭が熱くなる。Jazz東京道五三次に新たな宿場ひと次が札幌レイジーから追加されたのだ。記憶に刻んでおこう。マズイ、これ以上この話を引っ張ると4月で今年が終わり兼ねない。暦をミシン目に沿って引き裂いて5月。前の月にエキサイトし過ぎてバッテリーが底をつき、暫く充電の日々が続いたようである。その傍ら、米木さん支援を呼びかけていたのは、説明不要の繋がり故であろう。中旬になると、.Pushトリオそして松島が一枚かむ。腕利きの中堅と大物の中で、若き富樫の才気溢れるプレイに頷かされた。毎年6月は件の米木さんと大石のDUOだが、今年は大石のSolo。学生客が多く予定曲を幾つか差し替えたり、緊急講座を開いたりの何時にない展開で賑わいをみせていたのだった。
時は<下半期>を告げる。7月になると入魂一徹のプログラムに出会う。まずは魚返明未と井上銘、ノンストップの40分に及ぶ一幕に「アンタらここまで演やるか」と唖然。この密度の濃いDUOに舌を巻き、飲み過ぎて舌がもつれた。一夜明けて竹村一哲グループ。このグループはレイジーに来演を重ねるとともに、最早、完熟期を迎えている。引き締まった出色のパフォーマンスが連続する。中でも一哲作の「トゥワイライト」は魚返が長めのイントロを引っ張り、そのあと銘がガツーンと入ってくる瞬間があり堪らない。アルバム「KAGEROU」でも採り上げられているが、インパクトの強さではこのライブに分がありそうだ。8月、央紹が来演できなくなり、本山トリオ(三嶋大輝、橋本現輝)となったが、本山のリーダー・シップの下、バックが文字通り”輝いて”いたな。9月は渡辺翔太のトリオ(俊也・海斗)から。ビッグな発展途上ドラマー海斗のプレイをしかと確認した。翔太はいつも素晴らしい、もち俊也も。次いでLUNA北海道ツアーの一環での一席、古舘・町田の2ギターによるトリオだ。どうやらツアーの中でも選曲その他、ここだけのSpecialメニューだったようである。月の〆は山田丈造4(武藤勇樹、古木佳祐、高橋直樹)、丈造を筆頭に皆んなレベル高いわ。残暑ともお別れの10月。例年は初夏のアルト・ヴォイス松原絵里がひょっこり秋口に現れ、どっしり風格を置いていった。少しズームを引かせて頂きたい。レイジーと縁の深いMarkがコロナ期のブランクを挟んで5年振りにカナダから来てくれた。たまたまライブだった鹿川3の北垣(b)や里菜4の菅原(tb)らと旧交を温め、彼も満足して帰国したに違いない。それから久し振りの按田・斎藤のクラジャ・ブレンド、ここには普段のライブと異質の緊張感がある。二人の演奏力だけでも楽しめると言っておこう。やれやれ霜月だ。この辺りになると昨日の熱気がすぐそこにある。加藤友彦トリオ(高橋陸・柳沼)がきっちりお膳立てをしてから、我らが松島の参入となった。最早その名聞いただけで音が聴こてくる。お題なしに”松島”と聞くだけでレイジーに座布団2枚。師走の「ライブ・ショーは歌謡」だ。古舘・夏美が昭和を誘い出して、まんまと別ものにリメイク。JAZZも決して油断してはならぬ。書き漏らしを悔いつつこうして振り返ると、おぼろな記憶を超えて忘れられぬLIVEが沢山あった2024だったと感ずるのである。あっちょっと待て、これからサンタ目掛けて池田篤ほかホット連がやって来る。Lazybird Watcherの皆さんに呼び掛けておきたい。締め括りのbirdsを数え落としては、今年は終わらないよ。何はともあれ二十歳になった今年のレイジーは青春してたな。
(M.Flanagan)
2024.11.後期 ライブ三様


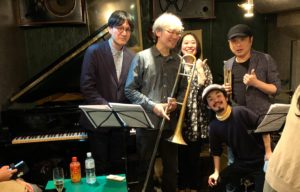
短期間で三つの放熱ライブ、冷めないうちに箸をつけておこう。
11.22 加藤友彦トリオ 加藤友彦(p)高橋陸(b)柳沼佑育(ds)
あれは3年前、喝采に至る経緯を思い出す。「トリオで思いつく最高のメンバーを連れてこい」、レイジーが三嶋(b)に出した宿題の答えが加藤と柳沼だったのである。一方、陸はおよそ10年振りだという。今や名の通った三人であるが、柳沼に至っては雨後のタケノコ状態で来演していて、支持率の勢い侮れないほどになっている。今回は現段階での彼らをファクト・チェックしようという態勢で聴いた。加藤には小気味のよいプレイをするという印象を持ってきた。ド派手なことに打って出ないが、それが趣味の良い演奏を可能にしているように思う。一聴マイペースに終始しているようで、進むにつれて如何に彼が多彩なスパイスの持ち主であるに気づかされる。珍しくエルモ・ホープの曲が採り上げられたので、家でホープのレコードを引っ張り出してみた。加藤は幾分か影響を受けているのかも。ベースの陸は多分初聴きになる(と思う)。従ってこのベースを最も注視した。彼はディテイルに拘泥されるようなタイプではなく、大きなノリに集中力を注ぎ込んでいるという見方を筆者はした。何でもヘイデンがお気に入りらしい。今日のところは深み追求の同盟員と判定しておこう。柳沼は相変わらずいいところで効果的なパンチを決め、トータルにしなやかだ。ツボを押さえるに長けたこのドラマーは、我らが近所のフィリー・ジョーなのである。なお、ファクト・チェックは道半ばにつき先延ばし。演奏曲は「Martha’s Prize」、「The Dolphin」、「雨上がり(陸オリジナル)」、「All Too Soon」、「In Walked Bud」、「Heren’s Song」、「Bellarosa」、「Black And Tan Fantasy」、「The Ballad Of The Sad Young Men」、「Cheek To Cheek」、「Too Late Now」。
11.24 松島啓之カルテット 松島啓之(tp)加藤友彦(p)高橋陸(b)柳沼佑育(ds)
毎年この時期の寒さを押し戻してくれるのが松島だ。彼が繰り出す躍動感がそうさせるのである。トランペットはジャズの歴史を彩どって来た花形楽器だが、この楽器はリズム隊のようなライブの常備薬と異なり、個人的には聴くことが意外に少ない。その意味からも松島には有難みを感じている。いつもの通りオープニングから突き刺し、そのまま急走していくところがたまらまい。かくしてジャズ・メッセンジャー松島に私たちは一息で「殺られる」のだ。アップテンポの曲には、ハード・バップの香り漂うが、ひたすら根性で押し切るようなものとは異なる良質な熱気がある。こうなると、浮かぬ気分のピープルをも上機嫌にさせてしまうに違いない。選曲の流れの中で飛び飛びに繰り入れられるバラードがはどうだろう。私たちにはラブ・ソングをモチーフとすることの多いバラードを深刻に聴かねばならないと思い込む一面がある。松島の懐深い心技は、そのそうした頑さを解きほぐす趣にこと欠かない。”さすがの松っちゃん”だ。演奏曲は「Just Because」、「Miles Ahead」、「Short Spring」、「Darn That Dream」、「Just At The Moment」、「East Thirty-second」、「Eluma(陸オリジナル)」、「Alone Together」、「Skylark」、「Chimes」、「All The Things You Are」。この日は日曜日、場内は”サンデイ・ナイト・フィーバー”に湧いたが、松島が帰京したいま、案の定寒気が強まってきた。
11.25里菜4±のクインテット
松島啓之(tp)菅原昇司(tb)本山禎朗(p)斎藤里菜(b)柳沼佑育(ds)
管のアンサンブルは実に気持ちがよい。ところ狭しとフロントの二人が牽引していくのだが、このスリルと寛ぎはこっちの気分を幅広にさせてくれる。上等な小部屋も良いが、こうした広間に通されるのも悪かろう筈がない。管の重奏はぶ厚く、ライブならではの直接体感が聴き手を揺すりつける。演奏全般を通じて感じていたことがある。札幌にいれば何時でも地元陣は聴けるなどと呑気な構えをしていてはいけない。とりわけこの日は、理想的なリアル本山を目撃した。ここら辺りを不用意に聴き逃すと”魅惑の松島day”に帰結してしまう。私見では本山の中で五指に入る出来栄えだ(あとの四本は伏せておく)。また、硬軟と緩急の覇者でならす菅原も、専ら熱さの側に身を寄せっ放なしだったのではないか。そして仕切りの大役を果たした斎藤は、集中と燃焼によって全身に湯煙が立ち込めていた。筆者の中では、彼女への淡い注目が手応えのある納得に切り替わったようだ。演奏曲は「Remember Rockefeller At Africa」、「My One &Only Love」、「Ease It」、「Ceora」、「I Got Rhythm」、「It Could Happen To You」ほか、名曲メイカーのH・シルバ、B・ストレイホン、B・ゴルソンの曲が並んだ。後日、眠りのうとうとの中に「2管’S Dream」が割り込んできた。真偽半々のハーフ・ドリカムってヤツだな。
標題はたまたま思い出した江戸期の学者「頼山陽」にこじつけた。
(M.Flanagan)
2024.10.23 「かおりな」へのECM

按田佳央理(fl) 斎藤里菜(b)
このDUOを何度か聴いているが、もっと知れ渡ってよいと思うので勝手ながら宣伝係の任を負うこととした。演奏の中にクラッシックの曲が幾つか盛り込まれているので、「クラッシックはどうもね」と訝る向きもあるだろうが、予断を持つ必要は全くない。クラシックをどうリフォームするかに注目するだけでよいと割り切っている。さて、斎藤のここ数年の傑出した活動は周知のことだが、ジャズ一本鎗のファンに按田は余り馴染みがないかも知れないので、僅かな回数ではあるが、ライブを通じた按田の印象を添えることにする。あらかじめ断わっておくが、彼女がその道でコンクール受賞歴が多数あることに惑わされることなく率直に語り始めようと思う。まずは鍛え抜かれた音色が出色であることは掛け替えのないことであり、最初に強調しておきたい。次に演奏全般の印象として、どうやら彼女は無理矢理ジャズに同化しようとはせず、クラシカルな素養をそのままジャズに対峙させようとしていることが窺われ、その受けに回らぬ積極性が通例のジャズDUOとは一線を画す局面を生み出していると感ずる。またジャズ側の曲においては、サックスのようなリード楽器とは異なる管の世界が存分に描かれ、こちらの興味を大いに引き出してくれているといってよい。斎藤の大きなノリに按田が自在に応じていく様子はコードレス編成に求められる強い緊張感に結びつき、終始そこが聴きどころの核を成していて、何ともカムフォータブルなのである。悪銭は身に付かないが、良演は身に沁みる。演奏曲を思い出す限り列記しておく。「マイ・リトル・スウェード・シューズ」、「ブルース・エット」、「ジプシー・ウイズアウト・ア・ソング」、「春の海」、「仮面舞踏会(ハチャトリアン)」のほかC・ヘイデン、BACHの楽曲など多種多用。なお、クラッシク曲はどっかで聴いたことあるよな、といった具合なので無駄な抵抗は不要だ。
冒頭に述べた宣伝強化に応えられたか一抹の不安は残るが、本文がいいコマーシャル(ECM)になったと思って頂けたら幸いである。標題の「かおりな」とは勿論二人の”乙女のいいノリ”に導かれて安直に名前を合体させたものだ。何れこのDUOの再演が計画されるだろうから、ホームページの見落としがないよう要チェックの喚起をお願いしておきたい。
(M・Flanagan)
2024.9.27 山田丈造Quartet

山田丈造(tp、fl)武藤勇樹(p)古木佳祐(b)高橋直樹(ds)
ここんとこ考えさせられるワードは”若手”だ。「生のいい」という言われ方もするし、LBのライブを通じて彼等らの熱気を存分に体感しても来た。ジャズ史に話を振ってみると、名演と評価されている作品の相当数が、”若手”時代のものであることが容易に窺える。”若手”とは人の生涯で言えば、序盤から中盤に届くかどうかを指すが、名盤はそこから生み出されている。するとライブで目の前にいるこの世代を呑気に眺めている訳にはいかんなという思いが迫ってくる。彼らが自らをどう考えているかは預かり知らぬが、筆者は彼らが第一次黄金期の状況下にいると見なしているのである。今年もそれに対応するライブに巡り遇っているが、この山田丈造Quartetを聴いていて、その思いが益々強まっている。何と言っても各自が持ち味を引き出し合いながら、全体をバランスさせていく様子には冷めている余地がない。そして抜いた感じのひと下りが絶妙にコントロールされていて成熟を感じさせる。どの世界でも声を大きくしたからといって必ずしも相手に伝わるものではないのだ。ふぅ~う、もはや”若手”以外の適切なワードを見つけなければならないな。Thanks丈造、Thanksメンバー!。演奏曲は、「I Concentrate On You」(C Porter),「Scissors」(Takezo)、「Upper Manhattan Medical Group」(B Strayhorn)、「Glad To Be Unhappy」(R rogers)、「Funky Boy」(Takezo)、「Night Mist Blues」(A Jamal)、「Sail Away」(T Harrell)、「Little Girl Blue」(R Rogers)、「 Wail」(B Powell)、「That Old Feeling」(S Fain)。今回は丈造を始め古木、直樹について触れることも考えたが、多言を排してじっくり噛みしめて置きたい心境にある。何故なら”若手”について「今夜は再考」の日にしておきたいからである。
このライブで初めて聴いたのはピアノの武藤 だった。 演奏中に彼のバック・グラウンドや影響を与えたミュージシャンを想像したが、そのオリジナリティーについては逃さず捉えさせて頂いた。東京のシーンでのピアノはニュージャージー州のような激戦区だと思うが、途切れることなく活躍することを願って止まない。
(M・Flanagan)
2024.9.20 LUNA&Twin Guitars

LUNA(Vo)古舘賢治(g)町田拓哉(g)
この編成はLB3度目になる。ギター陣はこれまで同様エレアコとエレガット。振り返って選曲を思い出すと所謂ジャズのナンバーを多少控えめにしていて、昭和枯れすすき世代にとっては心のどこかに眠る曲を掘り出して披露していた。今回も基本的にその路線を踏襲していたといってよい。本ライブは題して『エモ・キュン』、つまりエモーション&胸キュンなのだそうである。LUNAにとって’70年の前後10年くらいに流行った懐かしの名曲や埋もれた曲の発掘はお手の物になっている。それは彼女が日常的に遺跡発掘の現場に関与しているのことからも納得がいく(こじつけに過ぎluna)。まぁ細くはないその腕によりをかけた、ジャジーかつポップなお手並みを十分拝聴することができたといえば、この本格青春グラフィティーの趣向をひと括りで言い当てることになるだろう。演奏曲は、「All Or Nothing At All」(Standard),「First Song」(C・Haden)、「Tow For The Road」(H・Manchini)、「End Of The World」(Skeeter・Davis)、「Good By My Love」(アン・ルイス)、「朝日のあたる家」(T・Animals他)、「Almaz」(Randy・Crawford)、「 時よ」(吉田美奈子)、「Memories Of Tomorrow」(k・Jarrette)、[Everything Must Change」(名唱多数)、このほかジェイムス・テイラーやトム・ウェイツといった大物シンガー・ソングライターものや、初めて耳にする金延幸子さんという人の「青い魚」が沁みる。そしてダメ押しで行きついた先は「Hotel California」、この過剰サービスには例のイントロ段階で場内あちこちに小さい笑いが起こっていた。
この日は大衆食堂の献立表を眺めているような感じだ。人気のメニューが居並ぶ中、いま時は売れ筋とは無縁になっいても楽曲の味は何ら劣るものではないと主張しているような一夜だったのだ。
(M・Flanagan)
2024.9.6 渡辺翔太トリオ

渡辺翔太(p)若井俊也(b)中村海斗(ds)
レイジー3度目の来演となる渡辺翔太、前2回のライブを通じて実に個性的なプレイヤーだという印象を持っていた。”個性”とは個人が容易に集団化しない自立性ぐらいの意味合いだとして、渡辺の演奏はそこにピタッと嵌まるものがあった。謂わば「誰か的」な感じがしなかったのだ。加えて彼は作曲の才に秀でていて、本節もオリジナルたっぷりの選曲で固めてきた。とかくオリジナルだと余ほどのことが無い限り、その”旋律”よりも専ら”演奏”だけに気を取られてしまうが、彼の場合はその両者が絶妙にバランスしているので、初対面だがお馴染みさんといった中々有り得ぬ満足感を得ることができる。おこがましくも筆者の評定としては、局面々々の切れ味は言わずもがなとして、徐々に奥へ向かって畳みかけながら淀みなくクライマックスに持ち込んでいくところが最大の聴きどころといったところだ。その聴きどころをひっくり返してみると繊細なバラードプレイが待ち構えていて、両面からの聴きどころが相成り立っている。これを勝手に”翔太マジック”と名付けてているのだが、知らず知らず私たちは渡辺翔太が思い描いている世界に誘い出されてしまう。それを以てマジックの種明かしとしよう。オリジナル以外では唯一C・チャップリンの「Smile」が採り上げられた。この演奏は彼のアレンジによって私たちがよく知る”ほんのり・しみじみ”した曲想とは全く別ものに仕上がっている。彼の何枚目かのCDに収録されているので興味ある向きは聴いてみることをお薦めする。円熟期の翔太マジックにまんまと引っ掛かるのは気分爽快だ。加えて今回は中村海斗が同行してきたこともこのライブに魅かれる大きな要因であった。彼の叩き出す重量感もさることながら、血沸きあがるような奔放さが何とも頼もしい。それが初めて聴いてみての率直な印書だ。何か起こしそうな要注目のドラマーである。幾度も触れてきたことだが、レイジーでは若井俊也が推奨する「東京の生きのいい若手を聴く企画」が何年にも亘り継続されてきた。その初期のころに来た連中は今や分厚い中堅層をなして活躍している。海斗を聴いていて「生きのいい若手」が後を絶つことなく 排出されているのを実感したのは筆者だけではないはずだ。演奏曲は「マンチャー」「Day Dream」、「つれづれ」、「Our Lady」、「Pure Lucks Bears In The House」、「歩く」、「Smile」、「 要」、「Sad Times Before Peace」、[Lullaby」。
今までのところ渡辺翔太を生で聴く機会は多くはなかったが、彼の”個性と発展”から目を離さないようにしていたいものだ。
(M・Flanagan)
beautiful live 7/19,7/20

2024.7.19 魚返明未・井上銘DUO
言うまでもなく、この両者は翌日に控える竹村一哲グループのメンバーである。このグループの過去数度に亘るLBライブから受けたインパクトは、今日のジャズ最前線からの一突きといってよい。この日は何度も来演して多くのお得意様を抱えている魚返ともっと聴きたいランキングのトップを張る花形ギタリスト井上のDUOで、アルバムもリリースしているこの二人、そうそう生聴き出来そうにもないので真剣に聴き耳を立て続けた。曲は夫々のオリジナル(*魚返、**井上)で構成されており、曲順に沿いながら、虚実お構いなしに掻いつまんで振り返りたい。ある風景を映像として楽曲化した揺ら揺らする「*きこえない波」、井上による不動の名曲「**The Lost Queen」、几帳面に畳んでも取り出すといつも絡まってしまうイヤフォン・コードの不思議を捉えた「*Dancing Ear Bats」、視えない向こう側を美的にイメージする「**丘の彼方」、ほのぼのlikeな「**Slumber」、さすが魚返の曲と思わせる「*Herbie Westerman」、次の2曲は通しで40分に及ばんとする「*Cycling Road」~「*Embracable Ladder」、これは本日のハイ・ライトをなす壮大な熱演で見事だった。このほか魚返作のタイトル未定の2曲が披露された。アンコールは清新な曲想の”風の組曲”から「*Part1」。ここに鬼才同士の一騎打ちが終演した。DUOにしては少々異例の長時間にであったが、それは終始緩みのないものであった。ため息交じりにジャズ研のギター担当に一言感想を求めてみた。「こめかみに来ましたよ」、急所を一撃、いや二劇三撃されたのだろう。どっこい筆者も負けず劣らずDUOの丁々ハッシッシにオツムが揺れる幻覚症状に追い込まれてしまったのだった。
2024.7.20 竹村一哲Group

井上銘(g)魚返明未(p)三嶋大輝(b)竹村一哲(ds)
今回はGroupの第2作「KAGEROU」のリリースに伴う発売先行ライブとなっている。ここ4、5年内に一哲以外のメンバーもかなりの頻度で聴く機会に恵まれてきた。彼らの活躍ぶりは今や我が国のジャズ・シーンをあまねく牽引するに至っているという評価に行きつく。それと共にこのオール・主役Groupの纏まりも年々強固になっていて、息の合っていることが手に取るように分かる。脱線話になるが、とかく私たちは石鹸のアワ多ければ多いほど、より効き目が働いているだろうという先入観を持つものだ。しかし彼らが採り上げる多くのオリジナル曲は、その演奏力ゆえに余分なアワが払拭されており、オリジナル曲に対する妙な距離感を持つことなく聴き続けることができる。つまり冗長さのない実質のみの骨太さを感ずるのだ。このアルバムは全国に名高い芸森スタジオで録音となっており、それは本作にかける意気込みの強さの表れでもあるだろう。聴き比べると予想通り完成度のアルバムに対し拡張度のライブということになるが、どちらも充実感に溢れていることは共通している。プロだから当然とはいえ、このライブでは手抜かりのようなものが皆無と言ってよく、従って安心してスリリングな演奏の中に入り込めることができたのだ。Sold Outに納得する。
演奏曲は「MOZU」、アルバム・タイトルの「KAGEROU」、「陰のみぞ知る」、「Towilight」、「洞窟」、「The Memory of the Sepia」、「いきり」、「Snow Falls」、「Fall Of The Wall」、アンコールは、かつて一哲と共演を重ねた板谷大の「No」。
月並みだが、彼らの総合力の高さがストレートに伝わってきたというのが率直な感想だ。それはGroupを主導する一哲が、既に一ドラマーとしてのタレントを超え始めていることと深く関係しているのだろう。LBは日々多様な音楽を提供していて、夫々聴きどころに富んだものである。様々なフィールドを包摂しながらも、LBのポリシーとして中央付近に位置しているのは、紛れもなく今回のような王道を行く生演奏なのではではないか。両日ともスタンダード曲はなかったが、”Beautiful Live” それが筆者の目に映った店の景色 だ。
(M・Flanagan)
2024.6.28-29 大石 学 DUO & SOLO

ご承知の事情により6月の恒例企画は米木さん抜きに切り替えられ、大石・NAMIのDUOおよび大石のSOLOとなった。NAMIさんは何度か聴いているが、濃すぎず薄すすぎずの中間領域で活躍されているという印象をもっている。ライブで特段ヴォーカルを追い続けるような熱心さを持ち合わせては来なかったが、相手が大石となると別だ。大石はシンガーと自身を夫々自立させつつ、絶妙のコラボレーションを演出する。流麗に寄り添いながら、時折ドキッとするフレーズを注ぎ込む瞬間があり、それと同時にNAMIさんの表情から心が腕まくりし始めていることが見て取れた。こういう咄嗟の相互反応は我々をグイグイ引き付けていく。演奏は淀みなく進行するのだが、1ステ、2ステとも途中で大石のソロが各2曲挿入され、ライブ全体のメリハリに効果的な作用をしていたと思う。歌と歌バンに喝采だ。演奏曲は「Raindrops Keep Fallin’ On My Head」、「Under Paris Sky」、「Tow For The Road」、「生きていれば(solo)」、「安らかな志(solo)」、「One Note Samba」、「Corcovado」、「Devil May Care」、「My Favorite Things」、「So In Love」、「I Concentrate On You」、「Rainy Days And Mondays」、「上を向いて歩こう(solo)」、「ひまわり(solo)」、「I Let A Song Go Out Of My Heart」、「見上げてごらん夜の星を」、「New York State Of Mind」、「Caravan」。SOLOの日は前日の演奏曲から幾つかをピックアップしながら、「E More Me(≒いも美)」、「花曇りのち雨」、「I Fall In Love Too Easily」、「Alone Together」、「What A Wonderful World」などが選曲されていた。もっと聴きたかったが、それは来年の復活ライブを待つとしよう。
大石の2daysは会場を大いに湧かせて終了した。湧かせた理由は三つ考えられる。一つは何と言っても全くスキのない演奏によってである。二つは初日に二度不規則発言をしたことである。それは女性客が大半を占める中「今日は若い人がいらっしゃっていない…」(事実と推定されるが、会場大いにどよめく)、三つはNAMIさんが発した”かつて大石さんはよく正装で演奏していましたよね”とのコールに対し、Tシャツ大石のレスポンスは「ちゃんとした所ではちゃんとしたものを着る…」(LBとの長年の付き合いに照らし、会場大いにざわつく)。口を開く大石は、その社交辞令なき演奏と真逆なのである。なお、二日目はジャズ研メンバーになりたての学生さん達が多数詰めかけていて、終演後に大石による緊急講座が行われた。彼らは思わぬボーナス・トラックに等しく目を輝かせていたのだった。最後に米木さんのことに触れておきたい。年内はほぼ療養に専念と見込まれていたが、新着情報によると最寄りのライブ・ハウスでセッションに参加するまでに回復しているそうである。それを聞いて遠くから胸を撫で下ろしている。くれぐれも無理のない範囲で復帰の途を進まれんことを願うところである。
(M・Flanagan)
付記
この日の演奏を聴いていて二つの記憶が蘇ってきた。中本マリさんがlazyで「ひまわり」を歌ったときのことだ。臼庭潤もよくこの曲を演奏していた。この日マリさんはバックを務めていたセシル・モンローが亡くなったことを知らないでいた。臼庭がセシルとここで演奏した時20年ぶりと言っていた。思わず涙が込み上げてきた。「見上げてごらん夜の星を」は森山威夫バンドで井上俊彦が演奏している。1994年のアルバムである。このアルバムが発売されたときいつもクールに吹き切る井上に得も言われぬ暖かさを感じ思わず井上に感動したと電話した事を思い出した。二人とももうこの世にはいない。
2024.4.4 ~ 20周年記念LIVEの快楽演

Lazybird 20周年の記念を前に思いだしたことがあった。一つは名演の数々を差し置いて開業前の内装を拝見したときのことだった。その時点では前のテナントの名残があり、現在あるカウンターや椅子・テーブルは未だなく、壁が斜めになっている箇所(現在のドラム・セットのあたり)を見て、何がどう設置されるのだろうかと気を巡らせていたこと。二つ目は、晴れて工事が終了して暫くの後、同時営業していた隣接ビルのGROOVYを閉じてLAZY一本に統合するに際し、ボランティア数名で命のレコード・CDを一斉に移し替えすることになるのだが、作業段取のリハに真面目さを欠く人物がいて、本ちゃんで所定箇所に配置されず大顰蹙となる顛末があったことだ。1年を20回転させた歳月は、それを笑える想い出に変容させている。番外エピソードに時の流れを感じながら本論に入いろう。記念LIVEは初日から一人増え、二人増えと厚みを加えながら、来つつ去りつつの終盤は札幌の中核連合との手合わせとなっていった。これは1年のブッキングを短期間に凝縮したものと言えるものだ。因みに東京でも実現できない編成がLAZYで起こってしまうのだとミュージシャンが口を揃える。つまり今回も異例が規則になっていたのだった。
4.4 壺阪健登(p)楠井五月(b)本田珠也(ds)、4.5 プラス鈴木央紹
両日ともに壺阪仕切りだ。このメンバーの中だと彼は新世代に属する。普通の実社会なら若手に対し「お前にはまだ早い」的な空気が支配的であろうが、音楽では相互にインスパイアしていく度合いがその価値を決定づける。まずはキーマン壺阪がどう持って行くのか楽しみだ。予め選曲の構成をお知らせすると、壺阪のオリジナルとスタンダードなどが半々となっていた。オリジナル曲の核心は自作であるという事実よりも、独創性の「有無」によって真価が決定されるだろう。とすれば、壺阪の曲は「有」の側にあるだろう。それをプレイとどうリンクさせるのかが、普段にない編成での彼に課せられたミッションだ。筆者は壺阪が来た時はほぼ聴いてきた。その延長線上に今日もあるのだが、彼の躍動感が作りだす”うねり”に巻き込まれて、じっとしてはいられない状態を再体験できたことは報告しておきたい。他の人は壺阪をどう感じているのだろうか。奇しくも横に座っていた旦那さんが「初めて聴いたけど、藤井聡太のようだ」と語りかけてきた。超賛辞と受け止めるしかないだろう。演奏時間が押してしまうことは想定内だったが、”二十一世紀旗手”にバラードがもう一曲欲しかったと次回に向けておねだりしておく。他のメンバーについて触れておこう。楠井を初めて聴いたのは数年前にピアノとのDUOでやって来たときだった。その超絶技巧に細い目が丸くなった。だが超絶過ぎて、歌っている部分が上手く捉えられなかった思いがある。その後聴く機会を重ねにつれ見晴らしが良くなってきたのに気づく。それは単なる耳慣れによるものではないことを言っておきたい。今に始まったことではないが、アルコを入れるタイミングと音色にはハッとさせられたな。続いて本田珠也、先ごろホーム・ページに掲載された「わが青春の10枚」を読んでいると、彼が如何に多様な音楽に接し、課題に向き合ってきたのかが秘話を通じて伝わってきた。とかく気丈さ一点張りと思われがちな彼の演奏家像は、時として歩を休めながら随分思案してきたことが分かる。珠也が発する強さと繊細さはA面とB面の関係のように一つの作品になっているのだろう。彼の持論とする和ジャズの実現に立ち向かう姿は、目の前の感動劇そのものに映る。何故か分からないが「新しいことをやるには、習い覚えたことを忘れてしまうことだ」と含みのある発言をしていた洋輔さんを思い浮かべていた。いつもながら8系の音出しにブルっとした。彼は記念事業に欠かせない。珠也の来年今頃のスケジュール調整を急いで欲しいものだ。そして最後に駆けつけてきた鈴木央紹。意表を突かれたのは、これまで耳にしたことのないアブストラクトに爆走する演奏があった。本人は「なんちゃってフリー」と言っていたが、きっちりコントロールされていたのは流石だ。それはさておき、彼の演奏を聴きながら思っていることがある。彼の信条は曲を作った人に恥じない演奏を心がけるということだ。この自己約束こそ彼の演奏の深みと通底している。絶えずそれを実践し続けていることに真の実力というものを感じる。上っ面と無縁の地平は一体どこまで続くのだろう。気になって終演後、本人に確認したところ今年LAZYでのブッキングはないと言っていた。残念なことだ。では演奏曲をお知らせする。4/4「Stella By Star Light」、「Isolation」、「暮らすよろこび」、「Smoke Gets In Your Eyes」、「子どもの木」、「Quiet Moment」、「It’s Easy To Remember」、「Bye-Ya」、「Four In One」、「Little Girl Blue」など,4/5「Time After Time」、「Never Let Me Go」「酒とバラの日々」など。
神妙な面持ちで大区切りのライブを振り返ってきたが、ようやく頭がほぐれて来た。これだけのメンバーが結集するとレイジーの敷居が高くなる。実際の話、油断のあまり入り口で躓いてしまったが、幸いマスターよろしくケガなく良かったわい。それはさて置き、4/7の里奈3+珠也+鈴木と4/9の鹿川3+鈴木を聴いて筆者のお勤めは終了した。なお、重責を担った壺阪が7月末に小曽根真氏の企画によるピアノの競演が決定しているので(@キタラ大!ホール)、熱心なファンと中途半端に多忙な人は是非ともキタラで壺阪の雄姿を御覧あれ。もう一つ、数日前に鈴木は今年のブッキング未定と言っていたのだが、最終日に8月の再登場があることが判明した。こちらの方は多忙を極めていても、目標を外すことのないよう覚悟のほどを。LAZY20周年、誰しも同じだけ年齢が嵩むことになる。この度のような快楽演に巡り合うと、人生Warm馬齢を重ねていてもムダなことばかりではないと思うのだ。
(M・Flanagan)
2024.3.14 田中朋子Original Night

田中朋子(key)奥野義義(as、bs、fl)岡本広(g)斎藤里菜(b)竹村一哲(ds)
この夜は標題のとおり、田中朋子さんの作品集である。オリジナル作品のみの演奏と告げられて、我が意を得たりと思わせることは、そうそう多くはない。私たちはオリジナル作品について、熟す前の果物が出荷されているような印象を持つことがあることに薄々気づいているからだ。朋子さんの曲はその難を逃れていると常々感じており、筆者のみならずここに異論をはさむ余地はないと察する。ここ数年前から朋子さんは鍵盤ハーモニカを常備していて、アコースティックとは異なる味わいを付加している。曲にもよるが、フェリーニがいたら「私の映画に使わせて貰えないか」と申し入れがありそうな情緒豊かな音色が気を引く。毎度のことだが、朋子さんの演奏を聴いていると頭の中に過去の映像が映し出されてくる。ご本人の語りにもあったが、いくつかの曲において彼女がここレイジーで共演した今は亡き臼庭、津村、セシルの想い出深い演奏光景が滲み出てくる。その光景はかつては重々しいものであったが、今はスローに宙を横切るという風になっている。こういう思いの去来を通じて、田中朋子さんのプレイにはその演奏容量を超えた記憶が収められていると感じてしまう。喝采を送りつつ、柄にもなく感傷を隠すのに一苦労してしまった。この日はSextetというLB標準からするとやや大き目の編成で、時に華々しく賑わい、時に深いところに向かって偲び行く。何れも重厚な仕上がりと言えるものだ。この日は奥野の本邦LIVE初公開となった貴重なバリトン、時々アナーキーな岡本さんの歌いっぷり、菅原の抜いたフィーリング、一部高齢者の基礎票を着実に固めている里菜夫々の巧みさと調和がここにはあった。一人抜けている。「一哲、いい仕事してるよな」と掛けた帰り際の一声を以てレポートを納めよう。Original Nightの演奏曲は「Blues For Lazy Bird」、「Alkaid」、「Day Dream」、「母の絵」、「Hope」、「道くさ」、「Requiem」、「Life Long Friends」、「Vega」。
終わりに朋子さん今後についてお知らせしておきたい。今年はレコーディングを構想しているらしい。その頼もしき意欲には敬服する。なお、5月にはまたこの編成でLIVEが計画されているので、是非お運びのほどを。
(M・Flanagan)
Psnjab

2024.2.16 田中菜緒子TRIO feat.平田晃一
田中菜緒子(p)平田晃一(g)若井俊也(b)柳沼佑育(ds)
緊急告知があったとおり、曽我部泰樹(ts)が都合により不参加となったことに伴い、噂のギタリスト平田が代役を務めることになった。筆者はあいにく彼を存じ上げなかったが、LBのホーム・ページには「若手NO.1の」と記されていた。信ずるしかない。豪快な曽我部のブロウに諦めを付けたとき、このNO.1からの受けた第1報は洗練だ。まだ20才ちょい超えのこの演奏家から総じて研ぎ澄まされたものを印象付けられた。思うのだが、あっという間に過ぎ去る思春の期の意識は生煮えの熱意をあからさまにしたり、思いの丈を静かにに煮詰めていったり、その中間に身を置いたりタイプは様々だろう。平田は一見静か派にみえて、そこには熱い派を潜在させているようにも思える。こうした混み入った思いに至らせしめたのは、平田が大人然とした演奏をしていたからだ。伝え聴くところに依れば、彼はB・ケッセルほかジャズ・ギターのレジェンドのみならず、ジャンルを問わず幅広く音楽遺産を耳に蓄えてきたそうである。そのことを知り「成るほど」と思った。いま現在の彼が選択しているのは王道中の王道であるが、その彼はエモーションを露出し過ぎない処に立ち位置を定めているように思える。それが大人感の源泉となっているに違いない。今回は平田の持ち味をしっかと確認したが、今後どうなって行くかは興味津々ではある。おっと、筋立てを誤ってしまった。本ライブのリーダは田中菜緒子ではないか。彼女は毎年この時期に顔を出していて、今や馴染みの1人だ。前述のように平田に焦点を合わせててしまったため、入りの文脈が前のめりになったが、それもそのはず今回の彼女は平田を如何に引き立てるかに徹していたように思うのだ。因みにこの前々日にVocalのNAMIさんとの手合わせがあったが、後ろに回っていい仕事をすると感心させられたものだ。彼女の演奏は素人さんのようなMCと全く対照的な玄人さんそのものに他ならないと言い切ろう。演奏曲は概ね著名な曲とオリジナルとの半々の構成だ。「Punjab」、「Mine Mine」、「Monochrome」、「Willow Weep For Me」、「Costello」、「Nobody Else But Me」、「Estate」、「Monk’s Birthday」、「I Remember Smile Again」、「My Ideal」。他のメンバーについてちょこっと触れておく。柳沼は来るごとに番付を上げている。それが証拠に微塵も「俺が俺が」に流れずタイトなサポートを絶やすことがない。いま「渋いドラマーは?」と問われれば、「柳沼」と口を滑らせてしまい兼ねないな。そして心身ともに風格すら漂う若井俊也、彼はサウンドの整体師のような存在だ。如何なる状況にあっても体幹の歪みが見当たらない。こういう土台に乗っかていれば、住み心地が悪かろう筈がない。ついでながら「Costello」は珍しく若井のオリジナルで、そのタイトルは世話になった店の名前だという。早速「もっと世話になっている店があるだろう!」という不服申立ての声も聞かれた(笑)。いずれ何かいい土産を持ってくるものと期待しておこう。それはさておき、このライブをLB常連の魚返明未(p)が音楽担当を務めた映画になぞらえて言えば、田中菜緒子の『白鍵と黒鍵の間』に全員ピタリと嵌まっていた。この印象を田中のお国言葉にすると「気分が上がったばい」となるたいね。
(M・Flanagan)
2023 Lazybird ウォッチング

1年を振り返る時期になった。困ったことに、LIVEを基礎づけるその場の音とその場の光景が月日の経過でバラけてしまった。こういう時は、後退途上国の流行語を手懸かりに1年間を『しっかり精査し、適切に対応する』ことが宜しそうだ。ついてはこの路線で逃げ切りを図りたい。今年の突破じめはKANI-BANDだった。必ずしも聴く機会が多いとは言えないフルート(小島さん)が入ると、サウンドの暴れ度が変わることが分かり楽しませてもらった。曖昧な記憶をカットして勢い2月。渡辺翔太トリオ(b俊也、ds一哲)あたりからリスナー軌道に乗ってきたと思う。このピアニストへの注目度は高い。自分のものにしている閃きがある。中でも喜劇王の「Smile」にはこっちもニコッとさせられた。まだ年の序盤で戦局が定まらない中、早くも大手がかかった。翌日から脳の半分以上が音符で占めていると言われる鈴木央紹が参加し、名曲と名演の大つばぜり合いが展開された。またまた振るえが来てしまう(俗称フルエル・マータ症候群)のであった。3月もフロム東京組の豪華合わせ技で、田中菜緒子トリオ(b俊也、ds柳沼)に始まり、一夜を越すと松島啓之と池田篤が加わる展開だ。トリオの方は田中の個性的なオリジナル曲が中心、知らない曲もベースとドラムスのタイトなサポートによってピアノが小気味よくスイングする。菜緒子も固定席ゲットに意欲を見せているようだ。そして黄金のツー・トップ、夫々のソロをぐるりして解決へ向かう2管のアンサンブルはスリリル満点、何と気持ちの良いことか。4月に入ると敏腕プロモーターの底力の見せどころ、19周年企画だ。ハクエイ・キム、米木康志、本田珠也のトリオを皮切りに翌日から峰さんが参加してくる。久し振りにハクエイを聴きたいと思っていたので、余りにタイミングがよろしい。曲も演奏もオリジナリティーに富むのを再確認した。余談になるが、父親がハクエイの知り合いという道内在住の娘さんが聴きに来ていて、会話を弾まさせていたのは喜ばしいひと時だった。さて、詳細は省くがレジェンド峰さんの並外れたエナジーはMr.Monsterそのものだ。極め付けはジョン・ルイスの「ジャンゴ」だ。峰さんが幾重にも刻み続けてきた音の年輪に挟みつけられるようで、身動きを完全に封じられた。なお、これは珠也の選曲だったらしく、会心の一撃はプレイその他にとどまらない。時がどんどん刻まれ5月になる。この月はゴールデン・ウエークが絡むので、従来はひと山作られてきたが、コロナの制約フェーズ切り替えとなったためか、数年来にわたり全国的に中止・延期を余儀なくされていたLIVEが本格的に後追い調整され始めて来たのだと思われ、ブッキングに苦慮している様子が窺える。そうして半年を経過しようとする6月。この月の恒例となっているミュージシャンが登場してくる。まずは松原依里(Vo)を聴くことができた。最近はヴォーカルを聴き損ねていたので、この実力派の歌に触れHotさせられた。月の締めくくりは何と言っても大石・米木だ。ここんところ、このDUOでは米木がエレベに持ち替えている。個人的には、グルーブの異質性から、エレベとウッドは別楽器に思えていた。そしてこの日もそういう聴き方をしていた筈である。ところが、エンドを飾った大石の「ピース」を聴いていて、楽器がどうのこうのという思いは消えて飛んだ。説得力のある演奏ってこういうことなんだな。7月は「内地」からの攻め込みがなく、本山・Nate、昼下がりのクラシックなどを聴いた。8月は早々に竹村一哲バンド(g井上銘、p魚返、b三嶋)だ。道東を起点に幾つかの会場を回り、ツアー締めくくりのLIVEがここに実現した。各地で盛況を博したと聞く。彼らのサウンドは、ぶ厚さの中に華麗さが織混ぜられており、さすがの猛暑も逃げ場を失ったのではないか。とかく井上銘に脚光が浴びがちではあるが冷静になろう。彼以外は割と頻繁に聴ける機会がある。いま聴いておくおくべきだ。ここでちょっとブレイクさせて頂く。LBと縁の深い臼庭潤が他界してから19日で13年も経ってしまった。だが彼の演奏はいつも昨日のことだ。この日は彼が追及したJAZZ-ROOTSを偲ぶことにしている。まあ臼庭は湿っぽいのを嫌うから、長居せずに9月に行こう。鈴木央紹の”Stars”リリース記念LIVE(g荻原亮、b若井俊也)がやって来た。セールスに影響するので、余計なことは言わないことにする。このライブの完成度は本年屈指。購入して出来ればそれなりの音量で聴くことをお勧めする。月の半ばにはLUNAの「ジャズ」ライブ(gネイト、b柳)、「ペシャワール」などのオリジナルのほか「竹田の子守唄」など、歌いきっているのが記憶に残る。10月にはドット・プッシュのトリオ版(p魚返、b富樫、ds西村)と池田篤が加わるカルテット版。還暦に至るも意欲に衰えを見せない池田と若手・中堅の一歩も引かないせめぎ合いだ。オリジナルを基調とするプッシュの曲に堂々乗り込んでいく池田は実にカッコいい。月末に急遽決定したKurage-Mini-Band、頗るユニークな演奏で中島さち子にメンバー分を含め座布団3枚。いよいよ11月に突入。低空飛行を伴わないフライトはない筈なのだが、今のところlazybirdは上空高いところばかり翔んでいる。そして更に高度を上げようというのだ。世にいう令和の”大催し”だ。先陣を切ったのは松島のカルテット(p本山、b三嶋、ds一哲)だ。いつも松島のプレイにはワクワクさせてもらっている。周囲の人々も同じに違いない。聴いていると何だか自分にも運が回って来そうな気になる。改めて素晴らしいトランペッターに感服。そしていよいよ鈴木央紹参上。前記(9月)の”Stars”とのセット・アルバム”Songs”のリリースに歩調が合っている。彼については何度もレポートしているので、借りネタだけを垂れ流すつまらないジャズのような書きぶりになりはしないかと萎縮気味になる。そこで理屈っぽいことを排除することにした。筆者は鈴木をゲッツと同じレベルで聴いているのだ。この実感をもってまとめとする。そろそろ息が切れてきた。LIVEは宝クジではないから引けば当たる確率が高い。来年もこういう安心できる博打に賭けたいものだ。その意欲を途切らせないためにも、怠惰>成実の人生観に磨きを掛けて行くとしようか。今年の駄文をチラ読みされた各位にお礼を申し上げておきたい。最後に生演奏をレポートすることについて、右手を胸に充てて言い訳する。生聴記よ永遠なれ(笑sometimes泣)。
(M.Flanagan)
2023.10.31 Kurage Mini Band

中島さち子(p) チェ・ジェチョル(Changu) 小林武文(ds)
これはピアノと打楽器2つのレア編成である。レアと言えば”Changu”という楽器を初めて見た。これは韓国ではごく一般的らしく、我が国で言えば和太鼓に相当するのだろう。その形状は丸太りの砂時計風だ。折角なので当人に簡単な解説を求めたところ、3つの音程を基礎としながら上部と下部を繋ぐロープに結わい付けられた留め具をスライドさせて変化をつけるということであった。急遽決定したこのライブの狙い目は「ジャズと民族音楽の掛け合わせ」ということになっている。日頃からジャズをジャズとして意識しながら聴くこともないので、まして民族音楽について考えることは殆んどない。ただ耳に入ってくるリズムに「おやっ」と思うようなときに、それが民族音楽と称されるものであったりする。民族音楽というのは地域の土着性に根を持つ音楽であって、そもそも他の地域に広がることを求めない音楽だと思う。結果的に影響が広まることがあったとしてもである。この文脈の流れは何処から来たかというと、三人が先ごろエチオピアに行って音楽交流して来たという話があったことによるが、まぁ気合い入っているわ。粗い感想を述べさせて頂くと、中島がジャズ、チェ・ ジェチョルが民族音楽、小林が両者の橋渡しの役割を担っていて、トリオとして本日の主旨にアクセスしていたと思う。選曲は中島のオリジナルが大半を占めていたが、半ばで挿入されたチェによる韓国の”民族音楽”の独唱にはグサッときた。集落の祭事に欠かせぬ歌なのではないかと想像した。世に知られる「アリラン」や「イムジン河」とは異なる印象を受けたのだ。またラストで中島の代表曲「灼熱」を聴けたことも嬉しい。Kurageの由来は分からないが、世界の音楽をゆらゆら漂う意思表示ぐらいに受け止めておく。「ジャズ☓民族音楽」LIVEに型破りな感じはなく、寧ろ万国に連なろうというコンセプトから発案されたのだろうと思うに至った次第だ。
中島は5、6年前になるかと思うが米木康志、本田珠也とのトリオで演奏していた。この取り合わせが何所から来たのか不思議に思っていた。彼女がMCで本田竹広氏に師事していたことに触れ、疑問が氷解した。本田さんの曲を採り上げてもいた。何より演奏に本田因子が散りばめられていることが了解でき、繋がるべきものが一気に繋がったのだった。
(M・Flanagan)
2023.10.13~14 .Push Trio & 池田篤のTowDays ・Tow Ways

池田篤(as)魚返明未(P)富樫マコト(b)西村匠平(ds)
このTow Daysは初日がプシュの選曲、二日目は池田の選曲によるという意味でTow Waysだ。つまり私たちは、一枚の絵から二通りの鑑賞が可能となっている。これまでのプッシュのアルバムはオリジナル曲で固められており、ここでも概ねそこからピック・アップされている。池田の方はスタンダードとオリジナルが相まじえての選曲だ。初日の演奏曲を列挙しよう。「WANA BI」、「時しらず」、「Old Folks(これはスタンダード)」、「ORA 2」、「High Step Corner」、「Lonly Bridge」、「Tiny Stone」、「照らす」。よほど熱心なファンでなければ知らないだろう。しかしながらプッシュのオリジナルはシンプルで親しみやすい。数多くの曲を提供している西村も魚返もJazzのみならず昔のポップな曲を含め、幅広い分野の楽曲に精通していることがその一因としてあるのだろう。これが耳の琴線を心地よく弾くのだ。池田は(多分)初見になる彼らの曲を違和感なく受け入れていた。彼は小手先であしらう様なことをしないし、得意技で纏めるような方法に依拠することもない。そうしたプロとしての矜持が渾身のプレイを促すのだ。だからプッシュのどうにも止まらないエナジーに対し、存分にキャリアを重ねてきた池田は格上として受けて立つように振る舞うことをしない。だからこそ四者の音圧がひと塊のJazzとなって会場を埋めつくして行ったのだと思う。二日目の演奏曲は「On The Trail」、「Never Let Me Go」、「Subconsciouslee」、「For A Little Peace」、「Out Of Africa」、 「UGAN」、「Long Vib On The Blues」、「Every Time We Say Good By」、「Flame Of Peace」、途中、池田のノン・タイトル2曲が採り上げられていた。池田を長らく聴いてきたが、ここ10年ぐらいを切り取るとキレッキレの高速演奏もバラードも辛口ではあれウォームになっているというのが筆者の見立てである。そういう視点で池田の音色に舌鼓を打つことは筆者にとってこの上ない喜び事なのである。折角の機会なので、締めくくった後、粒ぞろいの演奏の中から「Every Time We Say~」にジーンと来たことを池田に伝えた。すると池田は「シンプルな曲って、普段から手入れしておかないと、扱えなくなるんですよね」と応じてきた。また噛みしめるものが増えてしまった。今回は前日(10/12)のプッシュ・トリオ(1年前はナーテー曽我部入りのカルテットで来演)の熱演に感服させられたことを付け加えておくが、それとともに思い浮かべていたのは、LBでの東京で活躍する生きのいい若手を聴くシリーズで期待値がハネ上がった連中は、今や日本のジャズ・シーンを担う段に来ているということだ。そんな時に彼らより手前の世代である富樫が現れてしまった。先輩格はウカウカしてられない。人生、逃げ足より追い足の方が速いから十分気を付けた方がよさそうだ。何はともあれ二日間のTow Ways「ごっつあん」でした。角界用語を使ったついでに付け足そう。ご存知だろうか外国籍で初めて関取になった高見山という力士を。この人はいつも自らの相撲信条を「押して押して押す」つまり「Push,Push&Push」と語っていた。奇策を排し「Push」を貫く取り口は彼をして多くのファンを獲得せしめたのである。このライブを聴いていると、時を隔てて古い記憶と繋がってしまった。謂わばドット・プッシュによる『”唸らせられたで東京』と言ったところだ。
すこし慎重に仕上げよう。「芸術とは真実を気づかせるための嘘である」と言ったのは、かのパブロ・ピカソである。今回のライブからはどうにも”嘘”が見つからない。例外のない名言はないということか。ここでもう一つ。筆者は”嘘”のない広告代理店を気取って、”真実”の宣伝を付け加えておきたい。最近「白鍵と黒鍵の間に」という映画が公開された。この音楽を担当しているのが魚返である。札幌でも上映されるであろうから、誘い合って魚返のニュー・シネマ・パラダイスを観に行こうではないか。
(M・Flanagan)
2023.9.14 LUNA の前転先祖返り
LUNA(Vo) Nate Renner(g) 柳 真也(b)
ここ数年、LUNAはバク転的活動に芸能人生を割いていたようだが、順序からいって人みな前転が基本であり優先される筈だ。そんな逆転現象のためか「Jazzやってるの、やってないの?」という疑念交じりの半苦情ーンズな問いを突きつけられていたらしく、後ろ髪を引かれる思いでこのほど意を決した”Jazz Tour In 北海道”なる看板を持ち込むに至ったそうである。かくして日々道内の犠牲心を厭わないメンバーとともに、各地を行脚した最後に LBにて千秋楽を迎えることになったのだった。大相撲でいえば千秋楽は15日目、このライブは9月の14日で千秋楽には届かない。2日分の頑張りを見せて貰おうじゃないの。この日数カウントの理屈はヘンテコだけど、それでイイのだ。さて、周知の通りベースの柳とLUNAは、古くから共演を重ねている仲だが、一方のNateとは初共演ということだ。この日は幾つか日本の曲が採り上げられており、Nateの日本力が本物であれば日本帰化の第一関門突破を認定するというウラの課題も入っていたようだ。私見では概ねNate色をキープしながら相応の出来栄えであったように思われた。話は変わるが、個人的に60を過ぎるころからVocalに接する機会がかなり増えたという実感がある。それは誰かが「60くらいになると、ルイ・アームストロングのように”What A Wonderful World”を歌うことに憧れる」と言っていた一文を目にした時期と対応している。そんなこんなで色々聴いていると、歌唱力やセンスを基準に気に入っただの入らないだのと断を下していたことに”ちょっと待て”を掛けることになっていった。それは”声の質“に重きを置いていなかったのではないかという自問である。インストものでは”この人にしてこの音色”という聴き方をして来たにも関わらず、Vocalには脇の甘さを露呈し続けていたのだ。以後、単にアクが強いとか美声であるとかを超えて”この人にしてこの歌声”というような歌い手と声との一致関係のことを気にするようになったと思う。それまで多くの人が当然視していたであろうことに、筆者は相当遅れを取っていたのである。本日のLUNAも聴くと直ぐに分かるシンガーだ。いま筆者は”声の質“は個性に欠かせぬ重大要素なのだという思いを強くしており、その軸をズラすことなく「Jazz Vocalist」LUNAの”声の質“に寄り添って聴こうとしていた。そして進み行く内に長年に渡り累積表現されたLUNAの”声の質“に更なる深みが加えられているように感じ取ることができたというのが結論らしきものである。そろそろJazzにされてしまった曲を紹介することにしよう。「Summertime」、「深淵」、「Summer Song」、「竹田の子守唄」、「Hand In Hand」、「A Case Of You」、「挽歌」、「Early Autumn」、「夕暮」、「Peshawar」、「Wind Of Fields」、「Blues In C」、「Tow For The Road」、「Destination Moon」、「Everything Must Change」。どうやら前転先祖返りは成功だったようである。
因みに「A Case Of You」はカナダの国宝ジョニ・ミッチェルの曲だ。勿論LUNAの選曲によるものだがNateは同郷の大ミュージシャンに対して余すことなく母国愛を込めた演奏をしていたように見える。そこから察するに、まだまだ帰化は難しいな。
(M・Flanagan)
2023.9.1-2 鈴木央紹 完璧トリオ
鈴木央紹(ts)荻原 亮(g)若井俊也(b)
ライブに行こうとする時に迷うことなく足が向く演奏家が少なからずいる。鈴木央紹は間違いなくその一人だ。こうした演奏家に巡り会えることを世間では「幸運」と言ってるらしい。その鈴木のニュー・アルバム「Stars&Smiles」がリリースされ、絶好のタイミングで今回のトリオ・ライブがブッキングされた。鈴木と若井は出演番付の上位者なのでお馴染みだが、荻原はおよそ5年振りのブランク永井だとなる。いずれ実力者なのだが、何と言ってもテナー、ギター、ベースという編成が魅力的だ。鈴木によればレコーディングに当たって、夫々がブースに入るのではなく、敢えてフロアに三者揃って演奏する方式を採ったということだ。つまりメンバー同士が息遣いをキャッチしたりアイ・コンタクトが十分可能となる条件設定だ。このシチュエーションは客を入れないライブに相当するので、演奏に仮想の臨場感を持ち込むことを狙いとしていたのだろう。その仮想を剝がしたのが、このLBライブということになる。何でもレコーディングに当たって、50曲をほぼワン・テイクで収録し、そのうち20曲をカット、30曲を厳選して2枚のCDにまとめたということだ。その第一弾がこの「Stars&Smiles」になっている。ライブでの選曲はそこに収められた曲を中心に進んで行く。その曲群を紹介する。「So Many Stars」「Milestones」「Wrap Your Troubles In Your Dream」「All My Tomorrows」「Groovin’ High」「Lucky Southern」「Little Willie Leaps」「Dreamsville」「You Say You Care」「Someday My Prince Will Come 」「Turn Out The Stars」「Hullcinations」「The Touch Of Your Lips」「Where Are You?」「Baubles,Bangles&Beads」「Get Out Of Town」「I’m Old Fashioned」「I Cover The Water Front」「Peri’s Scope」「Moon River」。筆者の狭い聴き歴で恐縮だが、ここにはよく聴く曲とそうでもない曲が混在している。途中で不思議に思ったことがある。それはどの曲も耳馴染みあるように感じられたことだ。答えは向こうからやって来た。鈴木のMCで「ハーモニーへの気遣い」についての語りがあった。我々の耳にすぅ~と入ってくるのは矢張りスーパー・ハーモナイズされた彼らの演奏によるものだと考えれば納得できる。バンマス仕切りのもとギターとベースは全曲について手を休めるひと時もないハード・ワークだ。鈴木スキ無し、荻原ミス無し、若井ムダ無し、我ら言うこと無し。言わば会場が調和していたのである。これは「完璧トリオ」によるパーフェクト・ゲームだ。終焉後、そこはかとなくドラムが入る時入らない時談義が聞こえてきた。どこかの空の下で「原たち日記」がアップさていたかも知れないな。なお、シリーズ第二弾は歌モノを揃えた「Songs」というタイトルで、近くリリースされることになっている。これに合わせて、11月に再び鈴木がやって来る。北区役所に転入届を出す勢いの長期企画であるらしい。皆さん「幸運」に巡り会うべく聴きに来てみなはれ。
(M・Flanagan)
2023.8.4-5 竹村一哲 BANDの”もはや彼らは”
井上 銘(g)魚返明未(p)三嶋大輝(b)竹村一哲(ds)
これは北海道ツアーの締め括りライブである。先行の道東2カ所(釧路、帯広)でも大盛況だったことを事前に聞いた。その勢いよろしくLB4度目の来演を迎えた。「いい演奏出来そうな店ですね」、初演のときの井上銘の一言を思い出す。以後、井上の予感が的中して今回に至っている。このバンド、芸能界的な次元では井上がセンターに君臨しているが、それは適切とは言えない。実体的には夫々が存在感を譲らない4人編成だからだ。魚返も三嶋も別建てでLBライブを重ねているので、その実力は実証済みだ。こう言ってしまうと、結論が見えてしまいそうだが、お墨付きも折り紙も付いている連中だから止むを得まい。では、完成状態で発展を止めないBANDを聴こう。まずは演奏曲を紹介する。「WE」、「The Lost Queen」、「Shinning Blue」、「Twilight」、「神のみぞ知る」、「Normal Temperature」、「妄想歩く」、「Chicken Rock」、「R M」、「悲しい青空」、「Spiral Dance」、「A」、「Mozu」、「No」、その他Non Title曲だった。大半が各自のオリジナルで占められている。最近は三嶋も曲作りに意欲をみせていて、今回も2曲提供している。失礼ながら彼は割とウラオモテのない一本気な人物だと思っていたのだが、曲想もタイトルも条理に収まらないものとなっており、ヒトの特性である矛盾を抱え込むことが垣間見ることがでる。知られざる三嶋の一面が妙に嬉しい。三嶋に寄り道してしまったので、ファンを代弁して他のメンバーにも触れておく必要があるだろう。井上は伝統を押さえた上でのスタイリシュなギター・ワークに抜群の冴えをみせ、何よりクライマックスに向かう演奏の創り方に圧倒される。魚返はリリカルな演奏に傑出する一方、何処まで行ってしまうか予測を超えた芸術的肉体労働のピアニストだ。そしてリーダーの一哲、例えば自曲の「Shinning Blue」での長尺ソロでは、打音の連鎖がいつしか物語の世界へと越境し、そのスティックによる筋書は我々の胸を打ずには置かない。改めて晴らしい。全てを聴き終えると、唐突に戦後10年余りの経済白書において我が国の再生宣言した「もはや戦後ではない」の一行を思い出していた。その誘因は少々安っぽいが「もはや彼らは若手ではない」と感じたことだ。一般論として若いというだけでそれに酔いしれてしまうことは、誰もが経験することだ。彼らは演奏家としてそれを完全に撃破して見せている。そう、”もはや彼らは”これからの我が国ジャズ・シーンを切り開く中核的な位置に足を踏み入れているのだ。こういうスリリングな局面に出会うと、私たちは一哲BANDの次回を楽しみにしたい気持ちが募る。ただ、今は過剰に美化することを控えよう。そうしなければ、次の楽しみを失いかねないからだ。
(M・Flanagan)
2023.6.25 「Under The Moon」リリース・ライブ
大石学(p) 米木康志(eb)
最新作を引っ提げた記念ライブである。これは大石によるアコピとエレベによるDUO企画だが、出自をオルガン弾きとする大石がこの楽器の低音部を見つめ直して、米木とのエレベによるコラボを持ち掛けたのが事の始まりだそうだ。実はこの青写真の現像作業は昨年からが開始されている。レイジーで恒例となっている6月のこのDUOもその意図をもとにしていた。それがこのコラボの第1回目のワクチン摂取となっていて、今回は前回の感染対策を程よく身に受け入れながら聴き進めることが出来た。「Under The Moon」とは録音した「月下草舎」というペンションの名に由来していると思われるが、それは大石の人脈由来の命名であり、そこに捧げたものと考えてよいたろう。というのも大石は演奏の場を提供する関係各位に自曲を以て一礼を表することを厭わないと伝え聞く。その律義さが勢い余って一か所3曲も提供していることがあるそうだ。何やら曲数争いが激化しそうな不穏な空気も漂うが、今回は満を持してレイジーの看板娘「いも美」をモチーフにした曲を店に劣らぬ品格を以て演奏した。筆者は現時点で「Under The Moon」を聴いていないのでアルバムに踏み込めないが、この曲が収録されていることだけはしっかり確認した。大石のMCからアルバム収録曲のほか、過去と近作を織り交ぜていたようである。ほぼ大石のオリジナルである。これまで大石の演奏を何度も聴いているが、彼は一貫して透明なものをもっと透明にしようとしているのではないかという印象を受ける。その姿は清々しいなどと云うよりも格闘に近い。それが筆者が思う大石ワールドだ。演奏曲の紹介に移ろう。過去に何度か共演した高野雅絵氏を鎮魂する「Melanchly」、お好みのスコッチ・ウイスキーに寄せた「Talisker」、前述した看板娘の「E More Me(いも美to Mr yoshida)」と二つの飲酒癖モノが続く。その酔い覚ましのような大石宅に咲く花「Color」、ブルース作品の多くない大石が名古屋の店に捧げた「Blues For Lamp」、倦怠感が燻る様子を綴ったような「花曇りのち雨」、米木のオリジナルでベース・ソロをフィーチャーしたシリアスな「Sirius」、闘病中のキースと先ごろ他界したゲイリーに捧げた「k・J&G・P」、鬱蒼とした時の流れを美的に構成した「Heavenly Blue」と「雨音」、かつてのアルバムからのタイトル曲「Nebula」。そして最後に待ち構えるのはあの曲、「Peace」だ。この曲を初めて聴いてから20年くらい経つ。幾度となく聴き、その都度感動を共にしてきた。かつて米木にこの曲をどういう思いで演奏しているのかを訊いたことがある。大石の演奏に込められた祈りを感じながら演っているよと言っていた。その一言を噛みしめている内に、悠久の名曲は渾身の演奏で締めくくられて行ったのだった。
(M・Flanagan)
2023.4.6-8 祝19周年記念LIVE
かねがねハクエイのLIVEを聴いてみたいと思っていたので、それが周年記念の大催しで実現したのは大いに喜ばしい。しかもトリオでの初日は米木、珠也との共演、翌二日間はそこにレジェンドの峰さんが加わるカルテットである。ハクエイと峰さんは両者とも多分4年ぶりくらいの来演と期間が空いたことも気分をプッシュしてくれた。話は変わるが、去年が17周年で今年が19周年になっている。18周年がないのだ。真相はよく分からないので、今回は2年分の気迫で臨んだということを正解としておこう。何よりこのキング達を結集ならしめたのがその気迫の現だ。つまり納得のキングをコールしたのだと一旦ショボく締めておく。
<4.6トリオ キム・ハクエイ(p)米木康志(b)本田珠也(ds)>
総じて短めのイントロからテーマに入るパターンにはなっていないので、何が始まっていくのだろうかと思わせる。眺望するとそんな感じで進行していった。オリジナル以外は、あらかじめ曲名が紹介されないので、聴いている途中で「あっ」ということになる。そこから圧巻のインタープレイに突入するのだが、このレベルになると握る我が手の汗も上質になった気にさせられる。またハクエイの曲はどうかというと、彼がイメージしているものとそれを旋律に落とすことにかけては、抜きん出たものを感じる。タイトルをつけてから、曲作りをしているのではないかと想像するが、どうだろうか。では簡単に演奏曲を紹介する。MCは僅かだったのが、それを手懸かりにそして後は当てずっぽうにしよう。まずは「Solar」、実はマイルス作ではないかも知れないとコメントされた深淵なる「Solar」、オリジナルで重厚感タップリの「Gardens By The Bay」、コルトレーンの「Some Other Blues」、身も心も分解させられる「Body&Soul」、既知の者が初対面であるかのようにフレッシュな「Have You Met Miss Jones」、オリジナルの「Fish Market」は小樽の三角市場のようなサカナ臭はなく、多分架空の何処かと思わせる。続く2曲もオリジナル、最初の「Sleep Walking」は夢から覚めぬまま彷徨い歩いてしまった実体験を曲にしたもので、その危うさを映し出していて怪しげだ。次の「Late Fall」における三者の熱量と所どころのエキゾチズムには少々陶然とさせられっちまった。ここで一段落といきたい「Old Folks」ではあったが、一息つけるものではなかったな。最後はショーターを偲ぶ「Foot Prints」。アンコールはオリジナル「Open The Green Door」、扉の向こうに何があるのか?珠也のドラムは「皆んな気をつけろよ」と警告しているようでもあった。全11曲、ピアノ・トリオとしては異例の長時間に及んだが、それは時計が言っているだけのことで、短くすら感じられたのだった。
<4.7-8カルテット 峰厚介(ts)キム・ハクエイ(p)米木康志(b)本田珠也(ds)>
そこにいるだけで存在感がある。峰さんのことだ。’70年代の峰さんのことを思い浮かべていた。既にその頃から50年を数える。尋常ならざる音楽精神のタフさが秘められているだろうことは創造に難くない。筆者のような一般人は体力と精神力の下降は相関してしまうばかりか、そもそもチューニングが狂いっぱなしの人生がチラついてしまう。よって、そこは見て見ぬふりをしなくてはいけない。それはさておき、実在する特別の巨人が凡人の目の前に座しておられることに集中しよう。カルテットでの二日間は、ほぼMCレスで余計なもの?は徹底して排除されていた。選曲はスタンダードとハクエイのオリジナルで占められていが、一部の重複曲も別演奏になっていて、JAZZのエッセンスが凝縮されたものになっていたと言える。敢えて触れておきたい。二日目の終盤に「Django」が演奏された。過去にプーさん(菊地雅章氏)と峰さんによるDUOの名演があり、即座にそれが頭をよぎってブルッときた。懐の深い音色に吸い込まれていったのだと思う。後で分かったことだが、この選曲は珠也の提案によるものだったらしい。曲によってハクエイが容赦なくアップテンポのカウントを出したりすることもあったが、峰さんは泰然自若、どの音域でも太く鋭くそしてノリの大きい歌心で例えようもなく素晴らしい演奏に仕上げていった。どうやも筆者は「このLIVEを聴きに来て本当によかった」ということを言いたいらしい。演奏曲は「Beatrice」、「I Want To Talk About You」、「Turn Arround」、「Sleep Walking」、「Body&Soul」、「In Your Own Sweet Way」、「Django」,「Offer Refused」、「Orgy」など。春の祭典は終了したが、LB史に残るLIVEが、また一つ加わった。
昨今では、何とかの”壁”という言葉が定着している。数年に亘って才気あふれる若手・中堅の演奏を大いに楽しませて貰っている。今回のLIVE3日間で巨人の壁があるかも知れないと感じた。さて、来年は何周年記念になるのだろうか?カウント蔑視はマズイよね。
(M・Flanagan)
2023.3.10-11 松島・池田Quintet 『夢で逢いましょう』
松島啓之(tp)池田篤(as)田中菜緒子(p)若井俊也(b)柳沼佑育(ds)
本文のイントロは私ごとから。このLIVEの数日前、夢に池田が出てきた。誰にも思い当たる節があるだろうが、夢という夢は何者かに追い詰められるような後味の良くないものが多く、それで目を覚ましたりするものだ。先日の夢では池田が古臭い大衆食堂のようなところにいて、確か彼に声かけしようとするあたりで終わったが、ニンマリできるものである。このあやふや短編動画は池田の預かり知らぬことではあるが、助走がついてしまったので、LIVEで最高の演奏をしてもらわねばならぬと思ったのだった。さて、ここからは現実に帰ろう。最近の池田の話によれば「今は若い頃のようには吹けないが、音楽は間違いなく向上していると感じている」という境地にあるそうだ。多くの池田ファンもそう感じているに違いなく、それは”吹けない”のではなく”老けない”のだと言葉を遊ばせたくなる。筆者としては、局所・難所を疾風のごとく駆け抜けてきた池田が終焉したとは思っておらず、それは”Warm”感が強まる境地に引き継がれているのだと思っている。ではこの日のLIVEではどうだったのか。まず鍵を握るのは松島だとしておこう。いつものことながら、初めて聴いたときの鮮烈な印象に呼び戻してくれる。つまり毎回新しいのだ。彼には「Treasure」というオリジナルがあるが、ぞれを地でいくように大判・小判ザックザクだ。松島の音には光源が仕込まれているようであり、更に突出したバランス感覚、ニュアンスの多彩さがその輝きに拍車をかけている。しかも呆れんばかりに無尽だ。その鍵を握る松島に対し、鍵を預けた池田はどんな図面を引いてくれるだろうか。もちろん池田は力ずくで扉をこじ開けるようなエラーを犯さないことは分かっている。二日間池田を聴いていて、体感的に固まってしまうことはなく、ずっと目尻が緩みを帯びていたような気がする。後でその理由を考えてみたが、踏み込み切れない。仕方ないので今現在の思いを残しておくことにする。それは池田がテンポの如何に関わらず、どの曲もラブ・ソングとして演奏していたのではないかということである。では何に対するラブ・ソングなのか?それは自身の音楽に対してであり、聴きに来る者たちに対してである。物語性に富んでいるとしても、ラブ・ソングを男女関係に限定するのは誤りだ。その関係は、一方の気遣いがいつの間にか過剰な干渉に転じ始め、両者の均衡は一気に失われて、典型的な結果に至ってしまう。音楽は均衡の不整を求めてはいない。筆者が池田式図面から探し当てたのは彼の隠された鍵としての”Warm”な音であり、それがラブ・ソングとして聴こえていたのだろう。ラブ・ソングとは攻め過ぎることなく、守り過ぎることのないところに見いだされる究極の調和なのだろうか。今回、ラブ・ソングという鍵ワードが頭から離れず、思わぬ方向に舵を切ってしまったが、LIVE終了後に松島と池田による出色の調和をそっくり家に持ち帰りたい気分になっていた。こういうことなら、次回もまずは「夢で逢いましょう」といきたいな。演奏曲は「Take Your Pick」、「Serenity」、「In A Sentimental Mood」、「Cup Bearers」、「Fee-Fi-Fo-Fun」、「Fly Little Bird Fly」、「Embraceable You」、「Crazeology」、「Fasta Mojo」、「My Heart Stood Still」、「You Don’t Know What Love Is」、「Eiderdown」、「On The Trail」,「It’s Easy To Remember」、「Be Bop」、「Ease It」。
なお、リズム・セクションを務めた3人は、この前日、田中菜緒子トリオとしてひと山作っていった。彼らはQuintetにおいても堅実かつ意欲的な演奏で見事に貢献した。この3人に対し近々やって来るドラマーのセリフを借りて一言付け加えておこう。「また来てやるからな」。
(M・Flanagan)
2023.2.17-18 鈴木央紹4&3 秘伝の『My Shining Hour』
鈴木央紹(ts)渡辺翔太(p)若井俊也(b)竹村一哲(ds) *二日目はドラム・レスのTrio
今回のLIVEについては結構前から知っていたので、待ちに待ったという胸中だ。当初の予定では二日間ともカルテットだったのだが、同行するはずの山田玲が都合により欠演となったため、代わりに竹村一哲が参加することになった。災い転じて福となったのである。それはさておき、鈴木のLIVEを振り返ってみると、スランダードや準スランダードがよく採り上げられている。このことは一面ファン・サービスでありながら、そこには明確に別の意味合いがあると考えてよいだろう。少しばかり余談から本筋に向かって行こうか。私たちにはお好みの曲というのがあって、色々な演奏家や編成で聴いて楽しんできたに違いない。個人的には例えば”Whisper Not” が収録されているレコードを見つけては、持ち帰って聴き比べていたことがある。そこには何度聴いても唸らされるものもあれば、年がら年中コロッケを食わされているような飽きのくるものもあった。同じ楽曲から感じられるこの差は一体何なんだろう。必然的に演奏とはそしてそこに生ずる差をどうう思うのかと襲いいかかってくる。原曲と演奏家の関係から何が視えるだろうか。一般に物事の辻褄に納得することを「理解」すると言うだろう。これと似て非なる「解釈」するという想像力に属する次元のことがある。ここでようやく鈴木についての手がかりまで辿どりついたかも知しれない。「理解」は横並びにつなぎ合わせても成立しそうだが、「解釈」は深化する方向に進路をとらざるを得ないように思う。彼は原曲に敬意を払うことを最も大切にしている。そこから繰り返し原曲の未来像を引き出そうとしているに違いないのだ。鈴木にとって「解釈」の徹底が演奏することであり、聴き手が同一曲に飽きがこない理由はそこにある。だから彼にとって”All The Things You Are”はいつも新曲なのだ。今回も能書き許さぬ演奏集となったのだが、それは鈴木の突出した「解釈」力にあると結論づけよう。やれやれ、いつも楽しみにしている彼のバラードの聴き応えは格別だったことを付け加えておきたい。では演奏曲を紹介する。まずカルテット。「I Love You」、イントロ早押しクイズなら”キラー・ジョー”と言ってしまいそうな「Along Came Betty」。照れくさいが20ほど若かったら惚れっぽい男を演じてみたくなるような「Be My Love」、モードでない方の「Milestones」、「Reflections」、「Like Someone In Love」。三曲続けて翔太作品「Color Of Numbers」「Pure Lucks In Bear’s House」「かなめ」、初見で譜面に噛り付いてしまったと鈴木は後で微笑んでいたが、実際これらは脅威のパフォーマンスといえるものだった。次はトリオ、「Long Ago&Far Away」、G・グライスの「Social Call」、「I Love You Porgy」、「Four」、「Sweet Lorraine」、「Autumn Leaves」、「It’s Easy To Remember」、「I Should Care」、「Bye Bye Blackbird」。古くも新しい名曲のフルコースだ。
よく江戸の時代からつぎ足し続けて200ウン十年、守り続けた秘伝のタレなどという老舗の看板セリフを見聞きする。筆者は鈴木のLIVEを聴いて僅か10年余りでしかないが、秘伝の生聴きが底をつかぬよう、毎年つぎ足しつぎ足し、いや紹たし紹たし聴き漏らさないよう心がけている。そしてこの二日間、秘伝のひと時にどっぷり浸かった。思わずタレのラベルをボレロから『My Shining Hour』に書きかえておいた。
なお、この前日となる2.16には渡辺翔太Trio(翔太、俊也、一哲)のLIVEがあり、聴く機会の少なかった翔太の演奏に三夜向き合えたのは収穫だ。彼の演奏個性が確かめられたのだ。曲目を添えておく。「歩く」「But Beautiful」「金曜の静寂」「かなめ」「We See」「Tones For Joan’s Bones」「Lullaby」「Equinox」「Body&Soul」「Smile」「Her Marmalade」。
(M・Flanagan)
2022年 レイジー・バード・ウォッチング
<前半戦>
今年の序盤は記録的大雪との戦に敗れ、腰が制御不能の危険な関係の状態になって、丸1カ月くらい聴き逃しのブランクを作ってしまった。確か年始は楠井のトリオで好スタート切ったかに思われたが、まさに腰砕けとなったのが悔やまれる。自分の実生活LIVEはほどほどにする。その後、2月の中頃から復調し、何とか松島のLIVE(ts岡、ds原が参加の5tet)に間に合ったので、この時のことはよく覚えている。松島の突き抜ける演奏は湿布よりマインドの復活に効き目があったと実感したものだ。引き続き原は残り古典派LaCordaと共演した際に、演奏の外でショパン(Chpin)をチョピン、バッハ(Bach)をバッチとくすぐっていたのが年末の現時点では懐かしい。原はプレイも喋りも痛快。次に地元札幌の青年?将校本山が奇しくも2.26にソロ・アルバム「As it is」のリリース記念LIVEを挙行、このアルバムをもとに入魂のSoloを聴かせてくれた。因みに本山は札幌ジャズ酒場放浪記なる配信活動を斎藤里奈とともに実行し、ライブ環境の側面支援に努めたことを付記しておく。3月にはLBの血行改善に欠くことのできぬ重要構成員の鈴木央紹が登場(ds西村)、例によって聴き流しを許さぬ重厚然とした演奏を残していった。一気に融雪が進む。そして4月には17周年記念。久し振りの本田珠也企画だ。ピアノはOwl-Wing-Record を主宰し、貴重な音楽記録を後世に残さんと精力を注ぐ荒武、ベースは巨匠米木によるトリオとtb後藤篤が加わったカルテットのセッティング。リーダーは荒武が務めたように思うが、これだけの個性が揃うとムダ口を叩いている場合ではないとういうLIVEの見本。5月は壺阪健人トリオ(b三嶋、ds西村)。外見的には壺阪と他の2人は家柄が違うなと口が滑りそうになるが、人は見た目で判断してはならないという普遍的な教えに立ち返らねばならない。演奏が始まると繊細かつ大胆に後ろと巻きつき合う壺阪をジックリ聴くことができた。年の折り返しとなる6月、この月恒例の大石なのだが、交通トラブルで1日のみとなった。共演者の米木はエレベで望んだのだが、ウッドでのDUOとは異なる空気間感を確認できた。(いずれCD録音するらしい)。蛇足だが、何やらこの頃から「コロナ禍の中、お越し頂きまして・・・」という型通りのMCがなくなっていったように思う。今のB・ディランなら「時代は変わる」ではなく「時代を変える」と言うかどうか。
<後半戦>
7月になると九州を拠点に活動するピアノの奥村和彦(b安藤昇、ds伊藤宏樹)がおよそ10年振りに来演、前回と同様に不動の力強さだった。なお、同行したVo.西田千穂は個性豊かな歌唱を披露した。カラだと思っていた財布に何枚か入っていた時のような思わぬ嬉しさ。国土の狭い日本の裾野の広さを感じたものである。この月の中頃に山田玲率いるKijime Collectiveに番が回ってきた。この連中の勢いは誰にも止められない。初聴きのtp広瀬、ts高橋の2管圧巻、充足感。帰り間際にCDとTシャツの押し売り被害に遇ってしまった。アキラは中々の商売人だ。数日後に鈴木央紹の長期戦、この日に合わせてワクチン摂取の日をズラして大正解だ。筆者が板前ならこんな切れ味の包丁を手放すまいよ。月末に本山と按田(fl)を聴いてみた。持ち替えではなくフルート1本ということに興味を持ったからなのだが、何やら心が清められた、知らんけど。8月は盆のド真ん中にカニBAND。予定の8人が一人増え二人増えそして11人。あまりの賑わいに地獄の釜の蓋がガタガタswingしてたな。加勢で参加し、カウンター内につけた丈造のソロは短かったが惚れ惚れさせるものがあった。月の終わりに加藤友彦トリオがやって来た。トリオの翌日から何と松島と鈴木が加わる。切り札二枚が投入されると盛り上がり系の演奏の熱気は破格レベルに達した。折角新調したLBクーラーが効いていなかったような気がした。それを気遣うかのような「Skylark」は心に沁みた。この両雄はダブル王手を掛けて譲らず、そのまま9月に突入して行ったのだった。そして時は10月、1年をマラソンに例えれば35キロを過ぎて一番キツイ頃合だ。吸水ポイントで真っ先に手を伸ばしたのが(Jazzの)LUNAだ。珍しくも今年はこれが初登場。2日間1曲も被らせずに全うし、女の意地が淀みなしに伝わって来た。これはb若井俊也とp田中奈緒子による初トリオで組まれたものだったが、若井は最早多言を要しないとして、特筆すべきは田中の歌バンの上手さだ。LUNAがいつかまたこのトリオで演りたいと漏らしたのも頷ける。いよいよ晩秋にはようやく池田篤に出番が回ってきた。この時は本山がリーダーとなってb楠井、ds原という垂涎の編成。出演回数では米木に二馬身ぐらい差を付けられているとは云え、池田は堂々の単独2位に付けている。近頃は振興勢力の追い上げがあるとはいえ。池田はLB年譜の要所を占めてきた誉高きプレイヤーであることに揺るぎはない。思い入れが先行してしまったが、一つだけ言うと本山の愛奏曲「Fingers In The Wind」の池田はこの曲に新たな命を吹き込んだといっていい。強く印象に残る。11月は珠也4daysと.Pushの駅伝形式で、タスキ渡しを魚返が担うという 豪華リレーとなった。魚返は間違いなく重要な位置にいる。そして最終12月。大口・米木DUO。ここに見えるのは築かれてきた壁の高さであり、怠りなく手入れされた庭園の佇まいだ。息つく間もなくLUNAの百変化ショー、特命任務を完遂するアビリティーに喝采するしかないな。締めくくりは郷土の至宝竹村一哲が率いるBAND(井上銘g、魚返明未p、三島大輝b)。都合3度目になるが、これを聴かずに年を越すことは出来ない。メンバー同士がその場で驚き合うような圧倒的パフォーマンスだ。同世代の密集した能力が創り出す絶大なる成果を観てしまった。このLIVEを聴いて日が浅いせいもあるが、一哲BANDを聴けただけでも2022年は良い年だったと思えるほどのインパクトだった。
ところで私たちは「何色が好きですか」とは言うけれど「色は好きですか」とは問わない。しかし、「どんな音楽が好きですか」も「音楽は好きですか」も成り立つように思う。筆者は「生演奏が好きです」とだけ言っておこうと思う。何はともあれ、今年も様々な編成のLIVEに恵まれ、語り継ぐべきLIVEにも出逢えた。2003年もまたそういう「生演奏」に巡り逢えることを願って止まない。
(M・Flanagan)
2022.12.15-16 LUNA のMagicai Mistely Tour
これは世界中の歌をさすらう異色の無国籍シンガーLUNAを追った2日間のドキュメントである。初日の1ステはブラジルもの、2ステは昭和歌謡という誰にも理解できないカップリング。2日目は大西洋を行ったり来たりの英米Unpluged Rock。いま私たちがいるのは、「サンパウロ郡北の酒場24番地第6区」という架空の地なのだ。
12.15 ブラジル&昭和歌謡 LUNA(Vo)古舘賢治(g、Vo)板橋夏美(tb)
外は寒いが中は温暖だ。ブラジルものは音をほのぼのと包む雰囲気という先入観が付き纏う。しかし、歌詞のあらましを聞くと男女の出会いとスレ違いをテーマとする内容が多いようだ。あの国から惚れっぽい情操を取っ払うと、文化が成り立たないのかも知れない。それはそうと、ポルトガル語は皆目分からないのだが、筆者はVocalを楽器として聴いているので気にしていない。かつて洋楽が勢いよく入って来た時代に歌詞は分からなくても、これいいなぁと思ったことが原点になっているのだと思う。意味の分からない異言語の歌を受け入れられるのは、音楽が超文化圏的に世界流通する希なる特殊性を内在させているとしか言いようがない。筆者の中ではインストもVocalも殆ど同じと言ってよく、ただ刺激のされ方が違うだけなのである。その違いの秘密は単純に肉声と特定できる。そして今回も楽器としてのVocalを大いに楽しませて頂いた。例えば、1曲目の「Cigarra」という曲で、ブラジルではセミが“シシシッシッシ・・・”という擬音になるそうだが、我が国では“ミィーン・ミィーン”である。この違いを一本道に繋いでいるのが楽器としてのVocalなのかも知れないと思うのだ。他の曲は「fotografia」「falando de amor」「bridges」「samurai」「ponta de areia」。そして2次会は北の24番地、昭和歌謡へと突入して行く。好いた惚れたのブラジルから恨みつらみを心情の核とする世界へ転換だ。多くの場合、この世界は情緒の汲み上げ手腕によって出来不出来が決定される。それもそうだが、定めある歌唱時間を重苦しさだけで埋め尽くしてはいけない。曲順的にjazzならバラードのタイミングに昭和歌謡では肩の凝らないものをハメ込む軽重相殺の工夫が必要とされる。北の酒場でもそれは実践された。では曲順。まず「天城越え」。普通、お通しは軽めの一品なのだが、これは背筋が凍る恐ろしいサービスだ。お口直しにポップな「ルビーの指輪」、北国もの2連発「雪国」「北酒場」。松田聖子の「瑠璃色の地球」(初めて聴きました)。M&Bの「ダンシング・オールナイト」、バイオリニストの高嶋ちさ子がこの曲を歌いすぎて喉をツブしたと言っていたので要注意だ。そして最後は隆盛を極めた北方漁業への郷愁「石狩挽歌」。あっという間の長旅だった。
12.16 Unpluged Rock
LUNA(vo)町田拓哉(g、Vo)古舘賢治(g、Vo)
会場は第6区に移った。このトリオ、3度目の取り合わせだから正直に言おう。完成度がますます高まっている。ギターの腕達者ぶりは周知のとおり出色なのだが、最大のセールス・ポイントはハモリ。いま述べた完成度ウップはこのハモリのことを言っている。3者の息が測ったように揃っていて耳が全く疲れないのだ。ところで、筆者がRockを聴いていたのは若い時なので、そのラインに乗ってないと聴く機会の無かった曲になる。Rockの場合、大半がオリジナルを演るので、バンドと曲は一体的なものだった。B・ディランが「枯葉」をカバーすようなことは後々の潮流だ。従って個人の記憶としてRockはバンドと曲がセットになっている。この3人Unplugedにバトンを渡したLoud Three&LUNAの演奏の時から、Rockの遺産を今日の現役プレイヤーが扱うとどうなるのだろうかという思いがあった。実際、聴いてみると面倒なことはなく、ストレートに懐かしさが蘇って来たのだった。これはクリームやツェッペリンがリアル・タイムだった者の宿命だ。この日のUnplugedは騒音防止条例に引っか掛かることのないアコースティックを基調としているが、前任バンドと受け止め方は何ら変わりない。そしてRockの名曲にはそのバンドが消滅しても生き残っていく生命力があると思わされるのである。過去のリアル・タイムの宿命であったものが、時を移した現在のリアル・タイムの特典に切り替わったのだと思う。多分、この3人は”懐かしさ頼みで聴いてもらっては困るよ”と言っているのだろう。そこまで言うのなら、次回は新たなハモリ曲を出して来る覚悟ができているのだろう。演奏曲は「Jumpin’ Jack Flash」「Sunshine Of Your Love」「Will You Still Love Me Tomorrow」「Angie」「Dust In The Window」「Down By The River」「Nowhere Man」「Who’s Loving You」「The Long &Winding Road」「Forever Young」「Honkey Tonk Woman」「Hotel California」「Blowin’ In The Wind」。
無事に世界のカム・トゥ・トラベルが終わった。盛りだくさんで決めの1行が浮かばない。遮二無二締めるとしよう。モンキーズの「恋の終列車(Last Train To ClarksVille)」を歌うカサンドラ・ウイルソンンには意表を突かれたが、LUNAはその上をいったかも。
(M.Flanagan)
2022.12.10 極上の男たちのDUO
大口純一郎(p)米木康志(b)
一般論として人は年を重ねるとともに話がクドくなる。寄る年波に従って謙虚に自分を過小評価すれば良いものを、それとは逆に虚勢を張るように作用する傾向が強まる。かく申し上げるのは、少しばかりクドい話をさせて頂くからだ。筆者が育った時代はパソコンやネットはおろか電卓すらなかった。そうした時代あるいはそれ以前に制作された音楽作品が不朽の名盤を輩出してきたのは何故なのか。現代の技術進歩と音楽的成果は無関係なのか。面倒話になってきたが、すぐ終わるのでご容赦を。前置きとして、技術は一方的に進歩し必ず便利になるが、人の精神はこのことと歩調を共にすることはないと言っておこう。最新の機器を使いこなしていても、泣き笑いその他の精神反応を起こしてしまう理由は太古から何ら変わっていない。すると人の精神営為には何が残されているのかという問題に行き着く。このことを今回のLIVEと関連付けてみると、人の精神営為に残されているのは、殆ど磨くとか掘り下げるということの他に余地がないのだと考えてよいかも知れないと思うのだ。私たちはよく「緩み無き演奏」という言い方を耳にするが、それは聴き流しを許さない演奏のことを言っている。このDUOの演奏に当てハメて言うと、安全装置を外して演奏に向き合っているから、聴き手はいつ何が起こるか分かりかねて、聴き流すことを許してくれはしない。それは修辞を凝らしながら本質論一本に打って出る冷静な論客の語り口のようでもある。ここにはムキ出しの過激さのようなものがないことによって、逆に荘厳さが引き出されているようにみえる。説得力のある演奏とはこういうことであると思わされるのだ。前述した磨くこと掘り下げることを両者と第4コーナーを併走する気分で代弁させていただく。こう言っているようだ。「目差すはゴールじゃなくて通過点だよ」、どうやら止まったままでいることがないらしいのだ。演奏曲は「Minor Choral」「(W・ショータの古い曲)」「Let’s Call This」「I Should Care」「Moments Notice」「Ugly Beauty」「Mr . Sims」「Sopa de Aio」「Don’t Explain」「Ode to J.S. Buch」「I Love You Porgy」。
このDUOは“極道の妻(おんな)たち”の岩下志麻的な任侠セリフの凄みとは趣を異にする。しかし、突きつけてくる隠れた切迫感の凄みは“極上の男たち”による至高の振る舞いであると確信する。このたび私どもにおいて、駄洒落精神は磨かれもせず掘り下げられもせず、財津一郎的に「悲し〜ぃ」。
(M.Flanagan)
2.22.11.25 .PUSH Quartet
曽我部泰紀(ts)魚返明未(p)富樫マコト(b)西村匠平(ds)
これはレギュラーバンドである。統率が取れていることと予定調和的であることは全く別のことである。私たちはLIVEにスタジオ盤からの逸脱を期待して止まない興味本位な聴衆といってよい。想定外は大歓迎なのである。リーダーの西村はそこを見逃していない。彼が叩き出す高揚感はその証明といえるだろう。LB初登場からそれは変わっていない。バンマスへの献辞はここまでとして、まずは地元出身で若干二十才の富樫が気になる。頷かされるのは指がよく動くというなことではなく、持っているGroove感だ。ここには何ものにも代え難いヤバさがあり、筆者を含めより多くの監視員をつけたい逸材だ。次は曽我部、.Pushのソツないイメージを覆すゴリゴリ感で押してくる。なんでもLB(つまり全国)の巨星S・央紹氏の後輩筋に当たるらしいが、同一楽器につき面識を持つ機会に恵まれていないそうだ。巨星が聴いたらどう思うか分からないが、肝の据わった頼もしさは確かなものだ。大阪の中の大阪たる河内出身の暴れっぷりを当面は今の延長で見て置きたいリード奏者である。そして前ノリした魚返は遠慮会釈を肯定的に振り払い、リリシズムとエクスプロージョンが全開だ。この若き上昇集団は聴いて兎に角気持ちがよい。こういう連中がいるから隠居はお預けにされっちまうのよ。演奏曲は「Catch&Release」「Vernal Days」「Body&Soul」「Hiball Party」「Wanna Be」「Darn That Dream」「Town Work」「朝焼け5時散歩」など。(「Hiball Party」の魚返、恐るべし)。
この週は大変結構なHard Daynightsでした。(M・.Flanagan
2022.11.22 魚返明未Qurtet
魚返明未(p)秋田祐二(b)本田珠也(ds) feat.林栄一(as)
魚返は翌日からの出演予定であったが、この日が最終日の珠也に呼びつけられて前ノリの格好になったということだ。珠也の気合のほどが窺われる。その気合にリーダー魚返がどう応ずるかが注目される。魚返には不思議な演奏家のイメージが付き纏っていて、どことなく異端を好んでいるようであるが、未だ解けていない謎が潜んでいるのを感じている。このメンバーだと優れた絵描き達の落書き合戦になる可能性が強い。そこで魚返は癖のある画商の目にとまるようなオリジナルを持ち込んでバンマス然とした対抗策を練ったのではないかと思う。秋田によると魚返の曲で多少の混乱もあったらしい。だが聴く側には全く分からない。なんだか誤解と理解の見境がつかなくなる。それもこれもJAZZなんだろう。小難しいことは差し控えるとして「今日は来て“本当に”良かった」ということは力を込めて伝えて置きたい。仕掛け人の珠也はやや荒っぽい喋りは別として、誰をも裏切ることのない誠意を注ぎ込んで我らを異空間にTripさせてくれたのだった。演奏曲は「Four In One」「Alcohol Jell(魚返)」「You Don’t Know What Love Is」「Bird&Dizz」「タイトル未定(魚返)」「Mary Hartman」「Tattatta」「I Mean You」。
2022.11.20 創作料理「カニタマ」
秋田祐二(b)本田珠也(ds)菅原昇司(tb)南山正樹(p)三浦広樹(g) feat.林栄一(as)
本田珠也は鈴木良雄さんのThe Blendのメンバーとして道東から札幌までのツアーを終え、本来ならそのまま帰京するはずのところ、もうひと暴れして行くという申し入れを受けて、このLIVEが成立したとのことである。事前の告知ではカニ・バンドwith本田珠也であったが、開演直前に急遽「カニタマBAND」とアナウンスされ、そこそこ「笑い」を取っていた。それはさて置き、これだけ名前が並ぶと誰に焦点を合わせるか人泣かせである。ひと「笑い」も取ったことだし、対極の必須科目である「泣き」について考えてみることとしよう。かつて美空ひばりは「悲しい酒」を歌っているときに止めどなく涙が滲んでくると言っていたが、彼女の歌唱力から納得させられたものだ。演歌でもRockでも「泣き」を売りにしていることが結構あり、謂わば「泣き」を商品化しているのだが、そうしたことと本物の「泣き」は容易には判別しにくい。けれどもそこには確実に違いがあると感ずる。例えば年がら年じゅう怒りまくっているようなミンガスを聴いていると、堪らなくなる瞬間に引きずり込まれたりする。こういう時は素直に「泣き」を受け入れていいのだと思う。そこでだ、今日のSpecial Guest林さんに同様の思いが重なってしまう。荒々しくも極めて鋭利なアイスピックのようで、林さんの音からは余計なものが紛れ込む余地のないPureさを感ずるのだ。Pureさの本質は透けて見えるところにはないので決して騙さてはいけない。何につけ流されやすい我々ごときであっても、気がつくと叫びを囁きとして聴いてしまっていることがあり、それを大切にしたいものだ。今日は林さんの日にしよう。涙腺が決壊する場を提供して頂いたのだから。おっとっと、「カニタマ」の味つけについて言いそびれるところだった。リピーターは語る。相変わらず「濃い目だな」。演奏曲は「Monkey Business」「Lonely Woman」「皇帝」「Penny Saved」「Ladie’s Blues」「North East」「回想」「Mary Hartman」など。
2022.10.21-22 本山禎朗4「溢れ出そうな涙」
池田篤(as()本山禎朗(P)楠井五月(b)原大力(ds)
この度の初日は某役所がらみの興行ということで、飲み物の提供なしという異例の反社会的仕様のLiveなのであった。筆者にとってLiveとアルコールは、伝票と証憑のような出納原則的な一致の関係にあるので、それを反故にされるとロリンズ抜きのサキソフォン・コロッサスを聴いているような感じなのである。しかしここは大人として如何なる環境変化にも順応しよう。今回は本山仕切りのWith江戸の剣豪という身震いを誘う編成である。周知のように本山は安定的にクオリティーの高い作品を発表しており、押しも押されもせぬ札幌拠点の中核ミュージシャンとなっている。この世の中では若い時に方便として、周囲から期待のホープと言われ続け、そしてそのまま終っていく者がいるのは珍しいことではない。これにはかく言う筆者も心を乱してしまうが、こうしたホープ症の域内に本山の姿は何処を探しても見当たらない。そんな彼に転がり込んだのが今回のセットである。選曲は本山の愛奏曲が中心を占めるが、レジェンド級の池田と原に鬼才楠井が絡む包囲網によって、それらの曲がどう捌かれていくのか興味津々である。人は物思いに耽けながら全力疾走することはできない。本山!無心で疾走してくれと呟いていた。では、本山はどんな曲を厳選したのか。「Witch Craft」「We See」「Butch&Butch」「Pensativa」、「Blessing」「Fingers In The Wind」「Brilliant Darkness」「Misty」「Amsterdam After Dark」「Who Cares」「Just Enough」「Serenity」「Out Of Nowher」「Midnight Mood」「In A Sentimental Mood」などである。その中で印象深かった演奏曲の一つとして「Fingers In The Wind」を取り出してみよう。池田が静かにゝゝに本曲の輪郭を提示しながら、少しづつ内からこみ上げる情念を積み重ねていくのである。この曲はバラードなのだが、その枠組みを超えて解体と構築をシンクロさせていく圧倒的な創造性がここにあり、聴く者の心を打たずにはおかない。この曲の作者R・カークのアルバムを借りて言うならば「溢れ出る涙」を堪えなければならなかった。一つの物語が優れた脚本家の手にかかると物語の作者を追い越してしまうのだと思うのである。たまたま筆者の座っている位置からはカウンター・テーブルの隅に並ぶ池田の意欲作「Free Bird」が視覚に入っていた。鳥が自在に中空に飛び立つということは重力に対抗する力を有していることと言えるのだが、池田も同様に気迫を宙に舞わせているのを感じた。そのことに気づくためには、原と楠井そして本山のサポートという条件を必要としたのだと思う。
最近、「聞く力」を「馬耳東風」の意に書き換えてしまった政治家さんもおられるようだが、こういう粒揃いのLive演奏に浸っていると、つくづく『聴く力』が養われるのだと感じ入った次第である。
(M・Flanagan)
2022.10.6-7 LUNAの回帰現象
LUNA(Vo) 若井俊也(b) 田中菜緒子(p)
「芸のためなら女房も捨てる~」という演歌の一節がある。これに倣うと「Liveのためならジャンルも捨てる~」というのが、LUNAによる局地的な戦略である。このまま行くとシルク・ハットから鳩を出すくらいのことをやってしまうのではないかと恐れている。今のところどれを採っても本流と支流の区別がつかない一級河川の景観を呈していて、興覚めを寄せ付けない。今回は、一念発起、JAZZに徹するというのだ。しかも、二日間、一曲も被ることなくやり抜くと豪語する意気込みようだ。そっちもそうなら、こっちもこう。「一丁聴いてやろうじゃないか!」。演目は後で並べるが、よく知られた曲にオリジナルを交えるという構成だ。標題の”回帰”というのはJAZZ一本でいくという以上の含みを持っている。「失ったものを数えるな、残ったものを数えよ」と謎の名言を発したのは、かのB・グッドマンだが、今回のLiveでLUNAが言うには、古の自分が歌っていたド・スタンダードを現在の思いをこめて数曲取り上げたということだった。それが彼女の中で「残ったもの」なのだろう。このことが”回帰”の本当の意味合いである。成るほど、聴いているとエモーショナルに歌い上げながらも、月日の故に度が過ぎぬよう抑制されている。ここはLUNAボーカルの大きな聴きどころになっていたと言っていい。唐突だが、たまたま最近、中島みゆきの”糸”という曲を聴いたので、それになぞらえて言うと、”糸”と言えば仕上がりは別としてタテとヨコの関係から編まれるものを想起しがちであるし、非を唱えようとは思わない。ただ一方で、人は”糸”を使えば必ずついて回る”糸くず”と無縁に生を営んでいる訳ではない。このLiveを聴いていて、その”糸くず”をLUNAはどのように胸中に納めているのだろうか、そんな余計な思いに駆られてしまった。少々湿りがちになったところで、演奏曲をズラッと並べる。初日は「Body& Soul」、「I didn’t Know What Time It Was」、「My One &Only Love」、「Save Your Love For Me」、「 My Foolish Heart 」、「All The things You Are」、「残滓」、「Porgy&Bess」、「愛の語らい(Speaking Of Love)」、「Ellen David」、「Good By」、「Chega de Saudade」、「Here’s To Life」、「Autumn Leives」。そして翌日は「The Man I Love」、「It’s Only A Paper Moon」、「Nearness Of You」、「Tow For The Road」、「Lush Life」、「Loads Of Lovely Love」、「Peshawar」、「Se Todos Fosse Iguais A Vose」、「Re: Requiem」、「We Will Meet Again」、「Who Can I Turn To」、「Lawns」、「Fly Me To The Moon」、「Everything Must Change」。歌いも歌ったり、聴くも聴いたりの二夜に渡る「回帰現象」であった。次回登場は師走、ウルトラ・ウーマン吠える、シワッス!
なお、リズム・セクションを務めた若井の厚みと田中の清新なバッキングにより、スキを見つけようにも見つけられないLiveとなったことを報告しておかなければならない。次の日にこの両者によるDUOがあり、PM2:00スタートで白昼・白眉の演奏となっていたことを付け加えておきたい。
(M・Flanagan)
jazz研定期戦
jazz研定期戦
先週の土日北大と小樽商大のjazz研一年生の定期戦を開催した。コロナ禍で3年ぶりの開催になる。10年くらい前からの行事になる。当時の北大の部長と話していた時の事だ。6月の学祭が終わると新入部員が大量に辞めると聞いた。一部の部員は学祭でやりきった感を持ち、一部の部員は次の目標がないので続かないと聞いた。次の行事は12月の定期演奏会で半年先になる。夏の合宿が終わる9月終わりに一年生だけの発表会をやったらと提案してみた。それが何とか継続している形だ。今回の出場バンドは5バンド。商大は一年生部員1名の為2年生がバックアップする方法で1バンドだけだったが先輩の温かいまなざしが感じられた。学祭はお祭りである。ライブハウスで演奏するのとは空気感が違う。一年生は緊張しているのが手に取るようにわかった。演奏中は先輩たちと気難しそうなjazz barの親父が腕組して聴いているのである。心中お察し申し上げます・・・と言ってあげたい。こういう時、僕はノーコメントにしている。まず演奏することを楽しんでほしい。そしてまたライブがやりたくなったら戻ってきてほしいと思っている。願わくば良いリスナーに育ってほしいというのが最終目標だ。昼のライブの為打ち上げはないが店の前で先輩たちから色々なアドバイスを受けているようであった。何曲かはハリケーンに襲われた木造住宅の様に崩壊しかかっていたが生き別れにならない様手をつなぎ合って持ちこたえていたのが微笑ましかった。演奏が終わると犯人探しが始まった。反省はしなければならないが粛清は辞めたほうが良い。この2日間僕は感謝されまくった。「こういう貴重な機会を頂きありがとうございます」とバンドが変わるたびに言われるのである。誰か先輩の入知恵であろうが何度も続くと居心地が悪い。MCは緊張するのであらかじめ考えているようであるが官僚が書いた作文を読み上げる大臣の国会答弁の様にはならなかったので良かったと思っている。学生たちからエネルギーを貰った2日間であった。
2022.9.2 無条件の降伏と幸福
松島啓之(tp)鈴木央紹(ts)加藤友彦(p)三嶋大輝(b)柳沼祐育(ds)
4番バッターの次が4番なのは明らかにルール違反である。ところがLIVEというのは演奏家によるその時限りの営為なので、ルールはメンバーの掌中にある。従って、彼らが一般的社会規範の干渉を受けることはない。そこに率先して巻き込まれれば、私たちも普段の縛りを忘れてステージを見つめることができる。しかも4番以外もソロありバッキングありの機会均等で嘘がない。何とも羨ましいことだ。今回のような若手と経験を積んだ演奏家の組み合わせはごく普通のことであるが、このメンバーなら私たちをどう説き伏せてくれるのだろうかという思いが胸中を往来する。若手陣の聴きどころは枠をハミ出さんばかりに前に向かって突き進む俗受け関係なしの清々しさにあるし、一方の熟練者は若手であった時を水に流すことなく今日に反映させ、過去と現在を同一過程のものとして自身を研磨している。そうした違いが原動力となってバンド総体としてどのように調和するのかに興味が湧くのである。いま目の前で何が起ころうとしているのか。予想に違わぬことと予想をこえることの両方を期待しているのだ。先発する松島の躍動感は身震いさせるに十分であることは予想どおりであったが、この音色には良心が宿っているのではないかと感じたことは予想外であった。盟友の鈴木については、最早どう綴ってよいか分からないので、イメージを掻き立てたままに言うと、例えば、Mt.富士を描けと云われれば、多くの者がほぼ左右対称の典型的アレを描くのだが、彼は上空から俯瞰して如何ようにも描くのである。既定の視点にない処から放たれる演奏に終わりのない物語を感ずる。少し力を抜いて若手について触れよう。今どきの用語を使えば、彼らは一様に「持続可能な発展目標」を地で行っている。3人揃っているのを聴くのは確か3度目になるが、回を追うごとに進化している。出荷されない規格外の野菜には思いがけない味わいがあるのだ。そうでなければ選定厳しいLBの座敷に上げてもらえない筈だ。筆者はブッキングに関与する権利はないが、「また来るよ」と語りかける権利はある。彼らの日々の研鑽と奮闘とが音に滲んでいるのが伝わってくるのである。終演直後にヘトヘトになっていた加藤がふとフロントに向けてこぼした賛辞を以て結びとしたい。「あの人たちバケモノだ」。演奏曲は「Ugetsu」,「Serenity」,「Skylark」,「Craziology」,「Panjab」,「Ceora」,「La Mesha」、「Fun」,「All The Things You Are」。この日の興奮をCD-Rでお届けできるようなので、迷いなくLAZYBIRDのブログでご確認されたい。
先月の8月15日は、「終戦記念日」になっている。ところが世界標準では正式に調印行為のあった9月2日が戦争終結の日とされている。日本国は「無条件降伏の日」を意図的に不採用にしたと思われる。LIVEにはそのようなスリ替えはない。重苦しいことを持ち出してしまったが、このLIVEのあった9月2日を「無条件幸福の日」として調印しておきたい。昨今賑やかな事件簿を引いて今年は最後となる2管に申し上げる。「LIVEには行くが、松島の印鑑と鈴木の壺を買うつもりはないよ。」
なお、前日9月1日はリズム・セクションを務めた加藤友彦トリオのLIVEがあった。バンマスの加藤はリハした曲をやらなかったらしく、三嶋はこのルール違反に苦笑していたが柳沼のアグレッシブなドラミングもあってスリリングな出来栄えになっていた。彼らの白熱ライブもCD-Rの提供があるようなので、演奏曲を紹介しておく。「Simply Bop」,「Boplicity」,「Bolivia」,「This Autumn」,「Alone Together」,「Dolphin」,「Time After Time」,「Just Friends」,「Fogtown Blues 」。
(M・Flanagan)
2022.7.15 鈴木央紹Meets The Rhythm Section
ここのところ生きのいい若手と支配人クラスの演奏家をジグザグに味わっている。そうしたことを抵抗なく受け入れており、パソコン使った上書きのように前の記録を消失させてしまうようなことはない。誰しもそうであると思うが、所持しているレコード・CDの類で、アレを聴いてみようかと思うものと余り気が進まないものとがある。勿論、これは一個人に付き纏うカタヨリなので、そうではないという人が否定される謂れはない。筆者は凡庸にこれは聴き逃せないなと思う一群の演奏家を中心に繰り返し聴きして来ているにすぎない。それがライブに対する自然体での測量感覚だ。もう薄々答えを言っているようなものだ。鈴木央紹はスルーできない演奏家なのである。縦横、奥行、深さ、重量感、つまり音の容積のようなものを一発で体感できるのだ。ハズれのないクジはクジとは言わないかもしれないが、これまでハズレたことはない。今回は札幌のシーンを背負っている本山のトリオに参加しているのだが、例えば演奏曲の中にO・ネルソンの「Butch&Butch」という曲があった。後に鈴木に初演かどうかを尋ねてみると、初演だと言った。曲読みの深さとそれが平然と音として化けて出る様は普通でなさすぎる。バド・パウエルの作品を借りて言うならば、アメイジングでありジャイアントである。あっという間に時が過ぎてしまのも仕方がない。唐突にあることを思い出した。吉田茂が占領軍たるGHQとの協議中に、連中の頭文字をなぞってGo Home Quiclyと脳裏で呟いたらしい。論理の場に感性が割って入って両義成立している様子が窺われる。鈴木によれば演奏中途切れることなく原曲の旋律が流れているという。表の一枚が実は二重構造になっていることの実例として吉田を思い出だしたのかもしれない。ここまで来ると気分は頂上付近だ。余計なことを言って滑落せぬよう、肝心のリズム・セクションについて語ることは容赦願いたい。演奏曲は「Embraceable You」、「Pensativa」、「Guess I’ll Hung My Tears Out To Dry」、「Butch&Butch」、「Midnight Mood」、「Blessing」、「Worm Valley」、「I Remember April」、「In Love In Vain」。
ところで、私立ちは“本日限り”“残りわずか”“というチラシが踊ると黙っていられない主婦心理が働く。鈴木央紹、その名を見ると、吾輩は主婦であるになるのである。厄介なことに9月早々鈴木がまたまた来演するとのことだ。立派な主婦としてちょっといい前掛け締めて行かねばならないな。
(M・Flanagan)
2022.7.15 Kejime Collective
広瀬未来(tp)高橋知道(ts)渡辺彰汰(p)古木佳祐(b)山田 玲(ds)
過去にも記述したが、6、7年くらい前から東京で芽吹く若手ミュージシャンのライブが継続的に企画されて来た。若井(b)という慧眼の持主をエージェントとして多数のまだ見ぬ若手が送り込まれて来たのである。今回のバンド・リーダー山田玲(以下「アキラ」という)もその内の一人だ。それまでは名のある演奏家を聴きに来るという手堅い基準に寄り掛かりがちであったが、その頃から寸尺掴めぬ危うくも新鮮な環境に触れることが出来るようになった。LBでは東京でも実現されていない組み合わせはよくあることだが、今回はレギュラー・バンドである。レギュラー・バンドには、是非は別として割と台本どおり纏めてしまう場合と意図を共有する者同士が自由度を高めながら纏まっていく場合いがあるように思う。さて、このバンド(Kejime Collective)の針はどちらに振れるだろうか。今回のライブは彼らの新作『Counter Attack』のリリース記念を兼ねているということで、選曲はオリジナルで占められるそのアルバムからのものである。実はこれまでアキラ以外のメンバーを聴いたことがない。なので何度も目を開閉し、観察したり聴き入ったりを繰り返した。夫々について感想を並べてみよう。冒頭から唸らされたのはtp広瀬である。抜群の切れ味・フラつきのなさは、気分を引っ張ってくれるのに十分と言ったところだ。Ts高橋は黒光りする艶やかなトーンからアイディアに満ちた展開力が聴きどころ。しかも玉切れしないのは見事である。P渡辺はスキを見せないフロント2管に対し、強く割って入るようなことはなく、あえて隠し味を添えることでバンドを引き立てることに徹していたように思う。だがソロを執った時の腕前は並ではない。B古木はウッドとエレベを使い分けでいたが、古きをたずね・・・などと言っている場合ではない、生粋のグルーブ野郎であることが分かった。個人評からバンド評にいこう。まずそこにレギュラー・バンドならではの総合力があるのを感じた。互いの持っているものを最大限に引き出し合おうとする信念のようなものが、会場を席巻していたと思えてならない。時に、笑いを誘う器用なひと幕もあったが、取り組みが大真面目なので、単なる余興とは明らかに一線を画するものだったと言えよう。総じて何か新しいものへの追求心のようなものが、台本にない熱いステージ・ワークへと導いて行ったに違いない。その熱気を冷まして締めくくろう、私たちはドラマーそしてバンド・リーダーとしてのアキラの底力を見せつけられたのである。演奏曲は「African Skies」、「It’s A Hustle」、「Mr. K」、「Counter Attack」、「Kejime Island」、「A I」、「Mouth Drum Battle」など。
その昔、学研のグリップ・アタックという参考書があった。後日、アルバム『Counter Attack』を聴いてみた。今のいま、表紙に“kejime Collective”と題された会心の参考書を手にすることが出来たわい。
(M・Flanagan)
2022.7.9 奥村和彦tio +1+α
奥村和彦(p)安藤 昇(b)伊藤宏樹(ds) 西田千穂(vo)
奥村の来演は相当久し振りのことになるが、ドラムスの伊藤が九州で共演を重ねているので、時折話題になる。思い起こせば、奥村には豪腕系のピアノだというのが初聴きの印象としてある。私たちは演奏家に対するイメージを何となく定着させてしまうのが普通にあるが、耳というのは規律正しくあろうとしない面があって厄介だ。熱演に喝采することもあれば少しやり過ぎと訝ることもあるし、圧倒的な技量に持っていかれることもあれば卓越の度が過ぎて心に響かないと感ずることもある。こうした我儘な感覚を整理するのは鬱陶しいので、演奏家のオリジナリティーに拠りどころを見出すのである。「ああ、あの人の音だ」いうように。奥村の音は以前聴いた印象の延長上にあり、一言では難しいが逞しさを基調にしているように思う。今回の構成は、前・後半ともトリオで2曲のあとにヴォーカルが入るというものである。そのトリオを聴いていると、ヴォーカルが押し込まれてしまうのでは、と思ったりもしていた。ところが西田(鹿児島出身で九州を舞台に活躍の場にしている)の堂々たる歌唱は、何ら後ろに引けを取らない堂々たるものであった。そして少しハスキーな声質は、Trio+1に+αの役割を提供していたように思う。演奏曲はTrioがオリジナル3曲に「「There will never be another you」、歌が入って「Lousiana Sunday Afternoon」、「For All I Know」、「Gee Baby,Ain’t I Good To You」、「That’s Life」、「Here’s To Life」、「My Favorite Things」、「What A Wonderful World」。
失礼ながら、予想外の素晴らしさに「帰れ、帰れ!」のシュプレヒコールが沸き起こり、薩摩の芋味はレイジーのいも美を凌ぐほどであったことを付け加えて置かなければなりもはん。
(M・Flanagan)
2020.6.25 新生DUOの生電ネットワーク紀行
大石学(p)米木康志(eb)
本年上半期を締めくくる米木週間で聴いた三夜の中からDUOの日に焦点を当てたい。実はこの前日(6/24)にセットされていたのは大石と“そして神戸”の実力派松原絵里(vo)とのデュオであったが、折からの暴風雨により鉄路北上中の大石が函館で足止めを食らうことになってしまったのだ。運良くこの日オフの米木と実力・ユーティリティー兼備の本山によりボーカル・トリオのライブとなった次第である。詳細は割愛させていただくが、ジャズ・ボーカルの王道を行く松原に緊急リリーフ陣が抜群のサポートを見せ、トラトラの奇襲は惚れ惚れするものになったことを伝えておく。さて、本編の主題である大石・米木のDUOについて語って行こう。特筆すべきは米木がエレベで臨んだことである。エレベにはウッドと違った粘着性や浮遊感があり、そこから発出されるグルーヴはこの楽器独自のものである。そうは言っても、アコースティック・ピアノとの組み合わせはどうなんだろうかと訝る思いも無いわけではなかった。なのでかつてのネイティヴ・サンやZEKでしか米木のエレベを聴いたことがない筆者のなかでは期待と躊躇が交錯していたのだった。ところが聴き進むにつれ、エレベは奇を衒ったものではなく、新たな試みとして大石の音楽的意図を拡張したものだという思いが強まっていく。そのことはベースがふんだんにメロディー・ラインを執る構成に見て取ることができる。なんかハマっちゃったなと思った時には、既にこの“生電ネットワーク”紀行は終盤を迎えていた。その終盤を飾ったのが、何度も聴いてきた大石の名曲「peace」だ。この曲に新たな表情を吹き込んだこの新生DUOの象徴をなす演奏だ。私たちは書き損じたときに、紙をクシャっと丸める経験をしている。だが一回二回几帳面に角を合わせて折り畳んでから丸める、そんな大石の人物像が頭をかすめた。彼はひと手間かけることを厭わない演奏家なのだと思うのである。演奏曲はオリジナルで占められていた。何が言いたいのかを問われれば、ピアノは持ち運びの効かないゆえ、マイ楽器による演奏家とは異なる立場を強いられる。従って1台のピアノを巡って演者の個性が露わになってしまうのだ。僅か数音で誰の音か分かることもあれば、そうでない場合もある。大石は分かる側の筆頭株だと思う。ピアノから何か一言もらいたい気分にもなるというものだ。文脈が雑多になってしまったが、かねがね一度負け惜しみを言っておきたいと思っていた。因みに筆者は演奏曲を音楽理論的に解説したりすることはないし、そうする能力もない。それは専門家の役割である。旨い小料理を伝えるのに、高名な産地を並べても旨さを伝えることができないと思っているので安心している。大切なのは舌包鼓の感触を伝えられれば良いと思うのである。ライブとは音の振動をそのように味わうことなのである。軌道をもとに戻してかなり不確かだが演奏曲を紹介する。「今できること」「ロンサム」「カラー」「シリウス」「アンダー・ザ・ムーン」「キリッグ」「7777酔いマン」「ニュー・ライフ」「花曇りのち雨」「目覚め」「ルック・アップ・ワーズ」そしてトドメの「ピース」。
このライブを以て今年もはや半分経過する。ミュージカルの聖地ブロード・ウェイの関係者によれば、上演の75%は失敗に終わるとのことである。上半期の24ナロウ・ウェイはそれに該当していないな。この分だと7月以降も視界良好に違いない。
(M・Flanagan)
2022.5.20 オール目玉、3人Side Up
壺阪健登(p)三嶋大輝(b)西村匠平(ds)
西村8Days、連勝街道を行けば、中日で勝ち越しである。そうなれば良いが、これは先ごろ開校した「レイジー生き残り塾」の第一弾だという噂を耳にする。聞くところによると、及第点は落第という抜き差しならぬ基準があるそうだ。親しき仲の礼儀なにするものぞということか。つかみはこのくらいにして進めよう。最近、今回のメンバーのような演奏を聴いていると、つくづく思わされることがある。気鋭の若手登場!という触れ込みに釣られて初聴きしてから僅か数年しか数えていないにも拘らず「前とちがうな」と印象づけられるのだ。ここで個人的かつショボイでストンプな話をさせていただきたい。サラリーマン稼業を卒業すると、長年つづけてきた仕事って一体何だったんだという問いかけに襲われ、立ちつくしてしまったことがあった。結局、仕事という仕事は「対処力」を養い続けることに過ぎなかったのではないかと思わされる。これは誰しも共通していることなのであろうが、しかし、音楽を含む文化活動を生業にしている人々はそれだけでは済まされないと感ずる。それは突出して固有性が突きつけられるということだ。気の進まない言い方だが。会社人が会社の法規に従い続けるのに対し、文化の人々は独自の文法を作らねばならない宿命にある。筆者にも青春というひと時があって、今時の人には馴染みがないと思うが小田実という作家(活動家)がいて、彼の講演会を聞いたことがある。彼の思想を必ずしも受け入れようとは思わないが、一つ印象深いことがあった。それは彼が聖書を大阪弁に翻訳して、それを読み込んでやろうと大真面目に言っていたことだ。滑稽な話にも思えるが、一笑に付すことが出来ない含みがあるかも知れないと振り返って思う。ここには人がどう思おうと自分的なる展開に持ち込もうとする意思が見て取れる。このトリオのメンバー個々にも小田とは別の仕様で為そうとする意思があると思わざるを得ない。であれば、演奏から受け取る高揚の一方で、彼らののっぴきならない深層に付き合わされていることになる。聴いている私たちは「感ずる」だけで良いが、彼らは絶えず「感じ直す」という次元で勝負しているに違いないというのがこのライブの感想だ。本文に目を通した各位にはカビ臭い話に許しを請うが、ライブの寸評として、壺阪が従前以上に弾き切っていたこと、サウナ汗に匹敵する三嶋の完全燃焼、西村のと切れることのない繊細かつ逞しいプレイ、そこにはこの日の目玉の3人とも「対処力」たる守りの白身に依存しない自立する黄身を輝かせていたと言っておこう。我が家にはライブの余韻割というカクテルがある。小林幸子ではないが帰宅後、無理して飲んでしまった。演奏曲は「The Days Of Wine & Roses」、「Little Girl Blue」、「SubconsciousLee」、「Turn Out The Stars」、「Bye-Ya」、「Isolation」(壺阪)、「暮らす歓び」(壺阪)、「All The Things You Are」、「It’s Easy To Remember」、「Moments Notice」、「I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free」。
なお、壺阪のオリジナルは、大変“お世話になっている”レイジーに捧げるとのことであった。売れっ子にスキは見当たらない。
(M・Flanagan)
2022 17周年のApril in バリバリ
これはLB17周年記念として企画された規格外の本田珠也6日連続ライブである。今回はそのうち編成メンバーの異なる4日ほど足を運んだ。久しぶりに頭の中はてんこ盛り状態になっている。これ全部を捌くのは至難と思い、東京ミュージシャンが結集した二日分に限定するのが賢明と判断した。この組み合わせは率直にファースト・ラスト的な感じがする。予感的中ならば、後から振り返ったとき私たちは大変貴重な場に居合わせたことになる。未来はどのような悪戯を選択するかは分からないが、今これを聴き逃すことにならないという焦りが襲いかかるというものだ。当然ながら、主賓の本田珠也についてレポートしなくてはならないのだが気が重い。その理由は彼についての月並みな賛辞は許されないということではなく、祖父や父親の楽曲を演奏するというということ自体が稀有なことであるうえ、それを突き詰めていくと、子は親を選べないという人の鉄則に反し、彼に限って子が親を選んでしまったのではないかと思わせるような幾分怖い特異性に行き着いてしまので、それに太刀打ちできそうにないからだ。幸い演奏中はそういうことを考えずに済んでいるが、書いている今はライブ中ではないので揺ら揺らしている。なので卑怯にもリスク・マネジメントとして、モザイク効果を期して少々脇道に逃げることにする。40数年前になろうか、B・エヴァンス・トリオを聴いた時に、ドラムのP・モチアンがうるさくて取り返しのつかないことをしているように思えていた。それから何千もの昼と夜が費やされていくにつれ、モチアンがいなければワン・ランク下の名盤に留まっていたかも知れないと思い始めだしたのである。こうした思いの核心は共感を得られるかどうかではなく、時と個人の感覚の関係として見た場合に、感覚は定点に留まることなく結構うろうろ歩き回っていることが確かめられることにある。時つまり歳を重ねるとはそのようなことだという極く平凡な結論に至るだけのことに過ぎないかも知れないのだが。すると珠也を初めて聴いた時と今とでは感じ方がどこか違っていると感じても不思議なことではない。それは彼の側ではなくこちら側の問題なのだから。誰もが認めるようにあの伝説的“蹴り”同様に破壊力のある豪快なドラミングが珠也の最大の聴きどころであることを受け入れた上で、今回耳を凝らしながら強烈に思いを強めたのは、珠也が驚異的に歌い続けていることであった。ここには表層の興奮を通り越した世界がある。アンタ今ごろ気付いたの?と言われてしまうと身を隠したくなるが、ここのところを正直に告白しておかなければ、彼が標榜するDown To Earthや“和ジャズ”の達成に近づける気がしないのである。ここらでモザイクを解除し二日間のライブ話に持ちこんで行こう。なお、今回の珠也Weekで彼はバンマスを務めておらず、ピアニストがその役割を担っていたので、予め申し添えておく。
2022.4.7 荒武雄一朗(p)米木康志(b)本田珠也(ds)
荒武は三年ぶりくらいの登場になろう。その間、彼は自ら立ち上げたレーベルOwl-Wing-Recordにおいて精力的に制作活動を行っていたらしい。蓋を開けてみると制作活動が演奏行為の妨げになるどころか矛盾することなく連結していたように思う。そこにはピアニストの枠を越えた音楽者としての荒武の素晴らしい演奏があった。それを周囲の様子からお伝えしよう。筆者から少し離れたところにある女性の背中があった。肩を震わせていた。後で聞くと、荒武のプレイに号泣、珠也の打撃に嗚咽、米木さんによって辛うじて我に返えらせて貰ったということである。筆者も終演後の余韻に縛られ、しばらくは人と話をする気になれなかったのだった。荒武のレーベル名になぞらえると、三者All・WINと言ったところだ。演奏曲は「Golden Earirngs」、「I Should Care」、「Water Under The Bridge」、「Influencia De Jazz」、「Dialogue In A Day Of Spring」、「Beautiful Love」、「閉伊川」、「Sea Road」、「Dear Friends」。
2022.4.8 荒武雄一朗(p)後藤篤(tb)米木康志(b)本田珠也(ds)
昨日のトリオに後藤が参加したカルテットである。後藤は2度目の来演だ。何と言っても彼はこころ温まるトロンボーンの一般イメージとは違う位置にいる。音がデカい。従って我々は救急車が来たときの一般車のように一旦道路脇に寄せなければならない感じになる。ではあるが、だんだん救急車に引っ張られて行くハメになっていく。そんなプレーヤーが後藤である。荒武、後藤、珠也そして米木さん、それぞれ固有の黄金比をもっているミュージシャン同士の融合は聴き応え十分であり、それ以上付け足すことはない。演奏曲は「That Old Feeling」、「All Blues」、「Be My Love」、「No More Blues」、「I Should Care」、「Riplling」、「Little Abi」、「夕やけ」、「Isn’t She Lovely」。Here’s To This Quartet。
レイジーバードのApril、17周年記念ライブは、うっとりするようなパリではなくバリバリだった。嗚呼“Live is over”とオーヤン・フィフィーなら言うだろう。ひと言付け加えさせて頂く。「米木さん、今回も心に沁みました」。
(M・Flanagan)
2022.3.15 鈴木・西村の週間春分砲
鈴木央紹(ts)本山禎朗(p)柳 真也(b)西村匠平(ds)
弥生三月の第2週は鈴木央紹、西村匠平週間だ。多様な取り合わせが組まれていので、迷いつつこのカルテットに出向くことにした。鈴木については、何度も聴き何度もレポートして来たのでおおよそ書き尽くした。このことは聴き尽くしたこととは全く違う。次も聴きたいという動機が働いてしまうのがその理由である。ファン心理とはそんなものだ。高速でねじ伏せ、低速で息をのませる、しかも大人の粋さがある。私たちが目撃しているのは、どんな風向きも自分の味方につけてしまうような並外れたクリエイターである。おっと、またダラダラ書きしそうなので、ページをめくることにしよう。西村は昨秋久しぶりに顔を出したが、それから程なくの登場でペースが上がってきたようだ。前回と今回から思うのは、初めて聴いた多分5年くらい前との微妙な違いである。かつて、勢いあるプレイと繊細なプレイが区分されていたように思えていた(それはそれで非難されるべきではない)が、今はその区分が簡単に見分けられない。繊細さが繊細に聴こえているうちは未だ本当の繊細さに至っていない、彼の数年間はそういう歩みと共にあったのではないか、そのように想像してみた。鈴木も西村も年内にまた聴けそうなので楽しみだ。ライブは既に始まっているのである。この日は聴こうと思えば何時でも聴ける堅実なプレイで定評のある柳と秀逸な作品を連発している本山が申し分のないサポートをしていていたことを付け加えておく。演奏曲は「Airegin」、「Introspection」、「Little Girl Blue」、「Long Ago & Far Away」、「Vely Early」、「317East32」、「Worm Valley〜Little Willy Leaves」そして「I’ll Be Seeing You」。
この冬の札幌には散々苦しめられた。最近は少しずつ日が長くなってきてコルトレーンの“Equinox”(昼夜平分点)を思い出しながらレポートしている。週刊文春のようにスクープはないが、このライブは、正に昼夜平分点を目掛けた充実の“春分砲”となっていたのだった。
(M・Flanagan)
2022.2.26 本山禎朗 の「As it is」
この日のライブは、本山の最新アルバム「As it is」リリース記念の第一弾として組まれたものである。発売レーベルは、ここLazybirdで何度か演奏歴のあるピアニスト荒武裕一郎氏が主宰するOWL-WINNG-RECORDだ。音楽文化の保存や発展と真摯に向き合うこの主宰者から声がかかること自体、本山の力量を物語るものであり、その意味で今回のことは降って湧いた特ダネでも何でもないと言えよう。私たちがこの新作に期待を膨らませるこのライブは2月26日に行われた。226である。一石を投じられているかも知れない。それはさておき、ライブは当然ながらアルバム収録曲が中心であり、まずはそれを紹介をする。「It Could Happen To You」、「Witch Craft」、「Misty」、「Butch & Butch」、「Come Together」、「Moon Walz」、「Little Wing」、「Fingers In The Wind」である。これらの曲は本山が演奏し慣れた曲というよりは、特別な思い入れがある曲である。普段はあまり読まないライナー・ノートに目を通して、これらの曲は本山が演奏することへの志を後押しする契機へと導いた楽曲集なのである。そう思っているとタイトル「As it is」の意味合いが少しずつ近づいてきた。多くの人と同じように、筆者にとっても音楽とは、音を媒介にした生命の表現行為と思っている。個々のアルバムやライブを即時的に楽しむことを大前提としつつ、そこに至るまでに演奏家がくぐり抜けてきたプロセスを想像することは陰の楽しみである。生命が必ずしも一定でないように、音楽表現も“時の階段”を踏み上がることで一定であろうとはしない。このことは過去の否定とは異なっていて、時を経た現在から過去に向かって返信してやろうとする思いに駆られるのは正統なことである。すると本山がこのアルバムで描こうとしたことが見えてくる。「As it is(ありのまま)」とは、過去の「As it is」群を現在時点での「As it is」に集約してみせることだったのではないのかということだ。先に述べた“時の階段”とはそういう意味を含ませて使ってみた。最後に、このアルバムについて体感的に述べておく。筆者はレコード、CDをジャズ喫茶のように聴くので、同じアルバムを立て続けに繰り返す習慣はない。しかし、今回は朝、昼、晩そして深夜と何度となく聴いた。むしろ何度も聴くことができたと言ったほうが正確である。「Misty」ほか素晴らしい演奏が納められている。本山の最良の姿を捉えた素晴らしい作品だと言い切っておく。
(M・Flanagan)
付記
アルバム購入方法についてはトピック欄をご覧ください
2022.2.18 「バップ、いいスね」
松島啓之(tp)岡 淳(ts)本山禎朗(p)柳 真也(b)原 大力(ds)
松島と岡そして原は、若き修行時代のバークリーで被っていて、帰国後はよく顔合わせをしていたとのことである。その頃から時を経てこの3人が顔を揃えるのは随分久しいとのことらしい。因みに東京から来るミュージシャンの話によると、ホームでの共演機会がなくても、ここLBで再会を果たすことがままあるらしい。言わばレア盤のようなライブを私たちは目の前にする機会を得ているということができる。今回もそのケースと言ってよく、LBライブ史上、Saxではまだ見ぬ最後の大者の一人というべき岡の参加という貴重な編成となっている。終演時点から物申すのも妙ではあるが、たまたま横にいた柳が「バップ、いっスね」とはしゃぎ加減の笑みをもって一言発した。彼が初めて演奏したというモブレーの「Rall Call」のことを言っているのだろう。筆者もライブでこの曲を初めて聴いた。突き抜けていく松島と悠然とウォームな岡のブレンドは、「バップ、いっスね」で勝負ありだ。20世紀半ばの黄金期に敬意を払うかの熱演である。開演に時に巻き戻そう。オープニングは「You Are My Everything」、多分松島の選曲だろう。トランペットが輝きに輝く。2曲目は岡のペンなる「Only One」、岡によれば“My One&Only Love”のチェンジを拝借しつつ原曲の“Only”と“One”を抜き出してタイトルにしたそうである。後で原が「リハ演らんかったらヤバかった」というナーバスな曲である。バラード指定席の3曲目は「Darn That Dream」、何故か最近この曲を最近よく耳にする。そして4曲目は先の「Rall Call」だ。2回目は如何にもハンコックらしい曲想の「Driftin’」で開始。続いて松島の「Treasure」、何度か聴いて耳に焼きついてしまった。3曲目は「If You Could See Me Now」、どういう訳かこの曲を聴くとH・メリルの歌唱を思い出してしまう。最後はK・ドーハムの名作「Lotus Blossom」に汗が飛んだ。喝采に乗ってアンコールは「I’ve Never Been In Love Before」。岡の参加は効き目十分のGroovin’ High!。
後日、札幌は記録的大雪となったので、その前にこのライブを聴けたのは実に幸運であった。一方、ドラムを務めた原にとって後に控えた3Daysが直撃されたのは不運としか言いようがない。歩道も閉ざされる中、意を決して中日のLa Coda with原を覗いてみた。原曰くバッチ(Bach)やチョピン(Chopin)など普段は演らない楽曲においても、原ワールドは至って揺るぎない。さすがの原師匠である。なお、本文に一度も触れていない本山については、別の機会に譲ることにしたい。
(M・Flanagan)
2021 レイジーバード ウォッチング
『Jazz is』。これは批評家ナット・ヘントフ氏の著作のタイトルである。「is」のあとに来るのは個々人のJazzに対する思いであり、特定の解はない。だからヨソからの縛りを喰らうことなく聴いていられる。これは結構大切なことのように思う。今年もソロから複数人の編成まで様々なタイプの演奏に接したが、それは偏に楽しみの幅の広がりとして受け入ればよいのだと思うが、どうだろうか?。さて、今年はどんなだっただろうと考えてみると、気分のうえで上半期はモヤモヤ、下半期は割り切りといった感じだ。思いつくまま振り返ると、6月までは常連の鈴木央紹、若井俊也、Unpluged Rockなどが記憶に残る。それと若井のライブに客演した村田千紘の「Blue In Green」が個人的には印象深い。7月以降になると時間制限と酒類禁止の中、皆さんがチビチビとウーロン・トゥギャザーしていた時の光景を思い出す。それはさておき、ライブの話に戻ろう。まずは三嶋のトリオだろう。毎度の手土産“東京バナナ”の皮1枚で滑らずにいた三嶋が満を持して連れてきたメンバー(加藤友彦(p)と柳沼祐育(ds))とのセットだ。このトリオは彼の自信を裏付ける出来栄えだった。連れてきた二人とも初聴きだったが、溌剌として引き締まったプレイは上々のものである。特に若き加藤の今後には大いなる期待を持った。そしてこのトリオは12月にも声がかかることになったのである。三嶋は辛口で知られるLB・AWARDにおいて堂々最優秀賞の栄誉に輝いたと聞く。そこで三嶋について一筆付け加えておく。彼は回を重ねるごとに充実した演奏を披露しているように感じている。思うに、三嶋にとってライブは課題発見と克服の結合になっている。人は本当のことに気がつくと嘘をつきたくなるものだが、実直な三嶋はそこに陥らず課題を正面から受け入れているように見える。演奏を聴けば、それが分かるのだ。ただし、それが受賞理由の一つになっているかどうかは知る由もない。8月にはLBの一帯一路戦略を牽引してきた米木さんのお出ましとなった。聞くところによると東京ミュージシャンはギグの中止・順延を後追いで穴埋めしていようで、ブッキングが思うに任せない事情下にあるようなのだ。そんなこんなで、今年は観測史上初めての1回出演になったのだ。演奏は山田丈造を招いてスタンダード中心に進められた。8時終了というのは残酷に思えた。お盆明けには松島・山ジョーの双頭ライブがあった。松島は演奏もさることながら、人柄だけでメシを食っていけそうな模範人だ。9月はLUNAの北海道ツアーの本体が中止になったが、ツアーの付録編は無事挙行された。ジャンルのルツボのような構成は特許もの。この路線は定着しつつあるようだ。月の終わりには原大力Week、オルガン入りトリオ(原、鈴木、宮川)のグルーブは益々磨きがかかっている。宮川が「上達すると演奏がつまらなくなる」と自身に警鐘を鳴らしていた。プロの世界は厳しい。10月に入っても時間制限は解除されていない。カニBAND北海道ツアーのオフに唯一設定された大口・林Quartet。林さんのドエラい音に会場が膨張した。11月にようやく制限解除となった。先鞭を切ったのが若井・壺阪・西村のライブだ。いいタイミングでいい連中が登場した。彼らにとっても客にとっても開放感が充満していた。これが本来のライブではないか。以後、怒涛の展開となって行く。昨年我々を驚かせた竹村一哲グループ(竹村、井上、三嶋、魚返)による『村雨』ライブだ。4つの個性の激突はスリル満点、一哲は改めて札幌の誇りであると確信した。こうなると気を緩められない流れにハマってしまわざるを得ない。小松・楠井・本山のトリオ。聴きどころ満載である。リーダーは本山、昔流の言い方を借りれば「どこに嫁に出しても恥ずかしくない自慢の娘」的な本山が余すとこなくこん日の力量を見せつけていた。いよいよ本年の最終月。待遇改善がかなった三嶋トリオの再演。「アップ・テンポの演奏で喜んでもらうだけが能じゃない」と切り出して“テネシー・ワルツ”なんぞを披露した。三嶋は演奏家としていいテンポを刻んでいるわい。そしてこのトリオをバックに待ちに待った池田篤。いつも池田には感動の予感が働く。蓋を開けてその通りになる。大熱演の締めくくりにどこまでも穏やかな「フォーカスセカス」には麻酔にかけられたような抵抗不要の気分になったのだった。今年の締めくくりはLUNA4DAYS。全部聴いたわけではないが、あぶない路線に円熟味が加わり、黄金期の浅草六区でも面食らいそうなSun Shine Of Your Liveでフィニッシュした。
今年も残り僅か、毎年、除夜の鐘の刻に何かを聴くことを習慣にしている。今年は何にしようか考えているが、LIVEものにしようと思っている。JazzおよびBeyond Jazzファンの皆さんよいお年を、そして2022もLIVEを楽しみましょう。
(M・Flanagan)
2021.12.9-10 Free Bird At Lazybird
池田篤(as)加藤友彦(p)三嶋大輝(b)柳沼祐育(ds)
「Free Bird」とは池田の直近アルバム名である。Bird、パーカーの演奏は機械的すぎるというような理由で好まない者が結構いるような気がする。しかし、彼の天才を否定する者は余りいないだろうし、その後に及ぼし続けた影響を否定する者はいない筈だ。「Free Bird」というタイトルはパーカー的なるものの最終確認の意味合いが含まれていると思う。“帰巣”とそこからのより自由な“旋回”と受け止めても良いかもしれない。詮索は程々にして、ライナー・ノートの最後の一行が池田の音楽家意識を平明に表しているので転載しておく。『さあ大変なことになった!次回はこれを超えるアルバムを作らなくてはならないからです』。池田の凄みは徹底したやり残しの拒否である。残渣を受け入れないのだ。聴いていて、池田はどこまで行ってしまうのだろうかと感ずる聴き手は少なくない筈だ。それは今日ここで人生最高の演奏をする、いつもその思いが池田にはあり、必ず彼はそういう演奏をするのだ。ひょっとすると若い時の方がスキル的に上回っていたかもしれないし、若い時にしか成し得ない音があることも事実に違いない。しかし池田はいつも往時を背負った今日を発信し続ける。池田の演奏に胸打たれるのは、それが生で伝わって来るからだ。このリアルな体感は消そうとして消せるものではないとつくづく思うのである。演奏曲は近作で曲名の紹介がなかったブルーズやバラード数曲のほか「Miles Ahead」、「You’re A Believer Of A Dream」、「Enter The Space」、「Is It Me?」、「Ceora」、「Infant Eyes」、「Rhythm-A-Ning」、「Star Eyes」、「ThisIDig Of You」、「When Sunny Gets Blue」、「Newspaper Man」、「Folhassacas」などである。
標題は“Free”と“Lazy”とのBird的な相性を問うてみることに端を発しているが“自由”と“怠惰”は馬が合うとの噂が広まっているらしく安心した。
PS.池田の前の日、リズムセクション三嶋大輝トリオの7月に続くLive Againがあった。これまでのところ、三嶋は勝負球を連投するタイプと思っていたが、ライブでよくあるモンクでつなぐような選択を避け、「テネシー・ワルツ」、「ビギン・ザ・ビギーン」といった楽曲を持ち出して来た。何んだか三嶋が半歩ほど近くなった。演奏曲は「Time After Time」、「North Of The Border」(B・ケッセル)、「Training」(M・ペトルチアーニ)、「Tow Bass Hit」(J・ルイス)、「Hindshight」(C・ウォルトン)、「Old folks」、「Fly Me To The Moon」など。ドラムとピアノは初聴きの人が多くとに思うが、柳沼のタイトさ、加藤のフレクシブルさに目を見張ったに違いない。これは、あるソフトリーな脅しに対して三嶋が命を張ったトリオである。
(M・Flanagan)
2021.11.17-18 本山禎朗 2021 ジス・オータムのカルテット&トリオ
11/17 鈴木央紹(ts)本山禎朗(p)楠井五月(b)小松伸之(ds)
11/18 山禎朗(p)楠井五月(b)小松伸之(ds)
この二日間は小松伸之週間の大詰めに位置している。筆者は小松の隠れファンなのだが、この両日に絞らせて頂いた。この二日間の選択は、荒くれ少年の告白に意中の少女が返す定番のセリフ「私にも選ぶ権利があるわよ」というのとは違う。過去に同じメンバー編成のライブがあり、その延長線上に眺められる本山の姿を確認しようという動機が働いているからである。昨今の本山から充実感が伝わって来ると思うリスナーは少なくないだろう。場数と研鑽によって彼は自らが意図する音楽表現を今では手に取るように出し切れているように見えるのだ。東京から来るミュージシャンとの共演は、過去において遠慮や自重が見え隠れしていたこともあったが、今それはない。今日に至る変遷と今日の演奏とがオーバーラップすると、音が音以上の装いを伴ってやってくる。今日は本山の音を聴き逃さないようにしようと、東京連に向きがちなこれまでの聴き位置から一旦座り直すことにしたことに誤りはないように思う。1日目はあの鈴木央紹入のカルテット、2日目はトリオという編成で、その違いも上々の組合せとなっている。カルテットの日は、予想通り我が国ジャズシーンの中央にいる鈴木がやはり圧巻の演奏を披露したことだけは言っておかねばならない。演奏曲は後にするが、とりわけ「Misty」における本山の演奏は、血がかよっているなぁと思いながら聴いていた。「本山これだよ」と呟いていたかもしれない。皆んなが盛り上がるアップ・テンポの曲も本山はフレームの強さを感じさせる隙のない演奏を繰り広げていた。トリオの日は当然ながらリード奏者がいない分、自由度が高められねばならない。そもそもピアノ・トリオはp・b・dsによる典型的な編成がなければピアノは随分困ったことになった筈だが、そうではなかったために激戦区になっている。多くの名演が残され、それとともにピアノ・トリオファンも大勢いいるだろうから、演っている側にしてみれば実は相当な重圧を感じているに違いないのだ。そこを攻略するには脇を固める連中のオリジナリティーが欠かせない。その意味で楠井と小松との取り合わせは申し分ない。両者とも辛島サウンド体験者なので緩むはずがないのだ。個人的にはもっとバラードを、と思っていたが良しとしよう。どの演奏にも温度・彩度・強度がバランスしていた。これ以上は脚色が過ぎてしまいそうなので、先を急ぐが、本山はソロ、フリーなどを含め多岐にわたる取り組みを行っている。それらが積分されて新たなる本山の立体世界が出現することを期待している。カルテットでの演奏曲は「Witch Craft」、「We See」、「Misty」、「Hey It’s Me Talking To」、「Laura」「Serenity」、「Long Ago&Far Away」、「Woodin’ You」、「I’ve Never Been In Love Before」、トリオは「Embraceable You」、「Boplicity」、「Pensativa」、「Worm Valley」、「Butch&Butch」、「Midnight Mood」、「All The Things You Are」、「Fingers In The Wind」、「The Song Is You」、「It Could Happen To You」。
最近は来札する東京ミュージシャンのライブに限定した聴き方になっている。それは理由あってのことだが、2021の秋は地元の本山に拘ってみて、色々考えることができた。いつも冷静を味方につけていた印象のある本山だったが、この二日間で思ったことは、本山のネライは冷静からの脱却にあるのではなく、冷静自体を燃焼させることなのではないかということだった。去りつつあるジス・オータムのメッセンジャーから一言あるそうだ。MVP(Motoyama・Valuable・Pianist)。通過点として聞き留めてくれよな。
(M・Flanagan)
2021.11.6 竹村一哲G LIVE!『村雨』
井上銘(g)魚返明未(p)三嶋大輝(b)竹村一哲(ds)
昨年春のこのグループによるLIVEはセンセーショナルなものだった。その時が初登場の井上銘に注目していたが、バンドとしての傑出したトータリティーに驚かされたものだ。その後、レコーディング計画が持ち上がっていることを耳にしていたが、程なくこの『村雨』がリーリースされたのである。一連の流れから待ちに待ったタイミングでこの日を迎えたと言っていい。午後8時、会場はいつの間にか人で溢れ、それはこの1年半余りにひと区切りをつけ、ようやく時計が動き出したかのようであった。竹村は決め事を極力排除することで、演奏するとは何かという追求心をグリップして離さないドラマーだ。彼を十代のころから聴いているが、懐かしさに微笑んでいる場合ではない。このグループは現時点における彼の集大成、つまり、実録竹村一哲ここに至る意味しており、彼の第一回記念碑なのだ。こっちも力が入るが、気分を鎮めて早々に演奏曲を紹介しよう。「MOZU」、「RN」、「悲しい青空」、「Spiral Dance」、「Normal Temperature」、「Vera Cruz」、「ノウ(板谷)」、「村雨」、「Lost Visions」。オリジナル曲が中心に構成されているが、思いもよらぬ「Vera Cruz」のイントロを聴いて、たちまち数々の名演を残して去っっていった津村和彦の顔が脳裏に襲いかかってきた。それに続きリスペクトと追悼の意を込めて板谷大の曲を演じたときは、その曲調が大らかな分だけ目尻の調整が効かなくなってしまった。感傷を取り除いて進めよう。既に述べたように竹村の目論見はメンバーの自由度を極力高めることにあるので、同一曲はいつも新曲に聞こえる。どのミュージシャンもそれを目指しているに違いないが、しかし、それを如実に体感できることはそう多いことではない。少しくらい遊んだらと思はないではないが、どこをどう切り取っても一貫して緩みがない。私たちはこの快感にヘトヘトになることを受け入れざるを得なくなったのだった。それでは、メンバーの様子を少しばかり振り返りたい。井上はジャンル横断歴なプレイヤーなので、普段は眠っている神経が覚醒させられる。敬愛するP・マルティーノ風フレーズを忍び込ませていたのもゴキゲンの上積みだ。兎に角、井上の演奏には努力では身につけられない資質の恵による華があるのだ。魚返の演奏は結構聴いているが、この日の止めるに止められないエモーションの噴出には、腰を抜かした。これは特筆しておくべきことに違いなく、これまでの見積もりの甘さを反省する。三嶋はいつも演奏が嬉しくて堪らないのだ。メンバーから新しいアイディアが提供されると必ずニンマリしている。LBのベース指定3席の一角を奪取するのはハードルが高いが、それ近づいているかもしれない奮闘ぶりだった。そして竹村一哲。全ての曲において後ろからの支配権を全開で行使していたように思う。細かいことは抜きにして、その途切れを知らない集中力に並々ならない意気込みが伝わって来る。堅実なサポートなどと言って済ます訳にはいかないのだ。纏めがたきを纏め上げた竹村に心からの賛辞を贈りたい。
余談になるが、入口の“本日のライブ”に、竹村一哲G・・・井上銘g・・・となっていた。Gはグループのことだが、開演前、彼らは談笑していた。“今日は大っきいのと普通のとツイン・ギターなんだ”。演奏中にそんな和んだ雰囲気は何処をどう探しても見当たらない。ライブから数日経た今も、LIVE!『村雨』が頭の中で鳴り続いている。
(M・Flanagan)
2021.10.29-30 壺阪健登3 スリリング・イズ・ヒア
壺阪健登(p)若井俊也(b)西村匠平(ds)
壺阪も毎年の顔になってきた。ブッキング基準については知らないが、少なくとも聴く気をそそることが真ん中あたりに位置しているだろうことは容易に想像がつく。では聴く気をそそるとはどういうことだろう。私たちには、日頃の煩わしい用向きから離れたいときに、気分を鎮めたり発散させようとしたりといった心理が働く。そこに音楽が待ち構えていることもあるだろう。けれども人がどのようなシチュエーションにいても、音楽はそれとは独自して成立している。そうとは言え、個々人のシチュエーションが音楽に潤いを期待するのは勝手な話だとしても、それを許容できることは音楽自体が決して敗北しない理由の一つであろう。どしてこんな問答を持ち出したのかと言えば、多くの音楽家が“何故音楽を演るのか”という問いに“音楽が好きだから”という平凡な答え以外は案外何も見いだせていないらしいことによる。“それが好きだから”という答えは平凡だが、音楽家もリスナーもそれを肯定的に受け入れているようにみえるのは、どう振り回しても否定しようがないからとしか言い様がない。平凡こそ長持ちの秘訣なのだろう。前置きが長くなってしまった。それでは本編へ。今日のメンバーはブッキングに相応しい聴く気をそそる連中といっていい。彼らは定期的に演奏してはいないが、夫々の個性についてはこれまでのLBライブで確認済みだ。壺阪についてはK・ジャレットを連想するとの声が聞かれる。筆者もその一人であるが、とりわけ長めのエンディングに向かってグルーブを引き出す構成力において、実際に教えを請うたような感じすらする。そこに壺阪がいまやっておきたいことがあり、その意思は十分伝わって来るのである。ドラムスの西村はやや間隔をおいての出番となったが、久しぶりの彼は、持ち前の男盛りの勢いを堅持しながら、繊細さが一回り磨かれていたように思う。時の鼓動が彼をして着実に前進せしめているのだろう。そして若井俊也だ。初めて聴いた時に感じた可能性から時を経たいま、このベーシストの手腕は計り知れない域に達している。ドライバーを何本持っているか知らないが、甘いネジの絞めどころが見つからない。このトリオの要たる若井はもはや予測より遥かに早く王道を歩んでいる。ここで迷いながら架空の話をするが、ライブ教習所のテキストには冒頭こう書かれている。安全運転は最大の法規違反である、と。先に平凡は長持ちの秘訣と言ったが、一発勝負のライブ演奏にそれは当てはまらない。彼らの生演はそれを証明しつつ走り過ぎて行った。演奏曲は「Tones For Joan’s Bones」、「Good Morning Heartacke」、「Mirror,Mirror」、「Little Girl Blue」、「Up On Cripple Creak」、「Come Rain Or Come Shine」、「Morning Morgan Town」「Delaunay’s Dilemma」、「Smoke Get’s In Your Eyes」、「Bye Ya」、「East Of The Sun」、「Boplicity」、「I Could Write A Book」、「It’s Easy To Remember」、「U.M.M.A」、「Of Course,Of Course」、「For Heaven’s Sake」、「Four in one」、「Shainy Stockings」。スタンダードからR・ロバートソン、J・ミッチェルまで壺阪の選曲マジックがこのライブに一層花を添えた。JAZZ無党派層の筆者はウグイス嬢になり代って連呼しよう、「壺阪、壺阪健登をお願いします」。
寒さ深まる当節はスプリングにあらずだ。標題は彼らの白熱パフォーマンスを讚え“スリリング・イズ・ヒア”とした。
(M・Flanagan)
2021.10.13 大口・林4 Jazz Advancing
大口純一郎(p)林 栄一(as)秋田祐二(b)伊藤宏樹(ds)
いきない脱線しよう。先ごろ亡くなったR・ストーンズのチャーリー・ワッツは自称“ジャズをこよなく愛するロックドラマー”だ。彼は少年時代にジャズに魅せられたものの、家にドラムを買える余裕がなく、そこで彼はバンジョーを改造してスネア代わりに練習を積んだという逸話がある。そういう出自をことさら美化するつもりはないが、後に名声を博するか否かに拘らず、おそらく50年のキャリアを重ねる演奏家の中にはそれに類する体験者がいると思われる。飽くまで想像でしかないが、演奏を聴いていていると林さんにもそういうことがあったのではないかという気になる。林さんのライブに接した機会は決して多くはないのだが、林さんに付き纏うイメージは長らく変わっていない。それは一貫してアンダーグラウンド感が漂っているような印象である。いわば公のルールでは裁くことの出来ない天賦の資質と言ってもいい。この日も演奏から演奏外の何か得体の知れないものを感じていた。筆者にとってそれが林さんなのである。一方の大口さんにもそれを感ずるのだが、溢れだす閃きは両者に共通していてもその質感には差異があり、それを直に味わうことはライブの重要な面白みである。それにしてもこの方たちのエネルギーはどこから湧き出してくるのか。数多くの音楽データが蓄積されているお二人の筈だが、おそらく“今日はこれまで以上にベストな演奏をする”、そういう演奏覚悟のようなものがエネルギーの出どころではないかと思えるのだが、どうだろうか。まぁ巨匠評は二の足を踏むもので、本文は欠員レポーターのトラとしてチャーリー・ワッツに援護して貰った次第である。演奏曲は「Goodbye pork pie hat」、「Four in one」、「You don’t know what love is」、「回想(林)」、「Better get hit in your soul」、「New moon(大口)」、「What is this thing called love」、「ノー・シーズ(林)」そしてアンコールはブラジルもの。上昇しながら構築する曲も、横へ横へと流れていく曲も独自性に溢れていたと思うのであるが、おしなべてタフな演奏の連続だった。従って、ベースもドラムスも心身ともに運動性量が限界に達していたのではないかと思われる。上手いこと言えないが、おどろおどろしさに咲くファンタジーがこのライブだ。
実はこのライブ、カニBAND北海道ツアーの谷間に嵌め込まれた唯一のカルテット企画である。そこに惹かれて来られた人もいたようであるが、分かるような気がする。
ところで「Jazz Advancing」とはいまなお前進して止まない御大に捧げた標題である。その出典はセシル・テイラーの「Jazz Advance」だ。芸術家の家計簿は知名度ほどにはアドヴァンスしていないんだろうな(泣)。
(M・Flanagan)
