
これは筆者がJazzを聴き始めた’70年代中期にリリースされ、わりかし話題となっていたと記憶している。さて、’70年代の空気は’60年代の余熱を引きずっていて、所謂モダン・ジャズや更に硬派なものが好まれる空気が充満していた。「会話厳禁」などと張り紙されているジャズ喫茶も散見された。巷には主張をばらまく語り手もいて、未熟者には口を挟む余地はなかったが、密かに参考にさせて貰っていた。他方この時期はフュージョンの勃興とも重なり、アコースティックとエレクトリックが交差するカオス繚乱の時代となっていた。今回の選定盤はCTIというレーベルのもので、当時このレーベルはややフュージョン寄りの企画ものを矢継ぎ早に発表していた。誤認を恐れずに言えば、腕達者なミュージシャンを組み合わせて、ひと儲けをネラっているような作品が多く、いま一つ腰の入った感じがしない印象があった。「アランフェス」という有名楽曲を持ち込んだ本作もその路線に沿ったものだったのかも知れない。しかし内容は充実していて、頻繁に聴いていた。加えて運よく来日したJ・ホール・トリオをナマ聴きできたことと、その時に本盤のタイトル曲が演奏されたことは想い出を色濃いものとした。こうした経過の助けもあってホールの作品を長年に亘り聴き続けることになっていったのである。本作にはC・ベイカー(tp)とホールとは非常に相性の良いP・デスモンド(as)が参加していて、さり気ないが実に効果的に絡み合っており聴きどころを演出している。それとは別に、とりわけ筆者はローランド・ハナ(p)の演奏に魅かれてしまい、その後、ハナのライブ(ジョルジュ・ムラーツ(b)とのデュオ)に足を運んだりするほどになっていった。物語は簡単には終わらない。そのおよそ10年後(’87年)くらいにLBマスターが関与したスーパー・ジャズ・トリオの一員としてハナが参加したコンサート(@道新会館)に行くことへと繋がったのである。放っておけばバラバラに終わりかねないPieceが思い掛けず新たなカタチを組み立ててくれた。それは偶然の成行きによるものであったかも知れないが、半分は恣意的に選択した必然のような気もする。本論に戻すが、この選定盤でのホールはどうだろう。いま聴き直してみて”まろやかな音色の達人”と片付けてしまうには余りに奥が深い。このギタリストはソロもバッキングも絶妙なほど無駄がないが、若い時はそれを読み切れていなかったように思う。バツの悪い話だが、街角の論客に惑わされたり聴き込み不足もあったろうが、今はそれら余分な荷物を下して本アルバムに向かうことができるようになってきたかなと感じている。彼の演奏は概して大げさではないが、そのフレーズは磨き抜かれていて、とりわけ心を動かされるのは彼の感受性と音が濃密に対応していることを思い知らされる瞬間だ。聴き手にとってはホールの技巧を一旦忘れて、その表現力を感じとることが遥かに重要だと思う。因みにここにはホール夫人が提供した趣味のいい曲(Answer Is Yes)が収録されており、筆者の”お気に入りに”格納してある。今回この名匠が残した数ある名盤の中から本盤選定の決め手となったのは何か。最近当ホーム・ページで拝見する”若き日の音楽広場”流に言わせて頂けば、これは我が青春の1枚であることに他ならないからである。
(JAZZ放談員)
master’s comment notice
このアルバムを選ぶことになった前振りを牛さんが書いてくれている。先日長沼タツルと斎藤里菜のduoがあった。アンコールでalone togetherを演奏したのだがタツルがJ・ホールとR・カーターのアルバムのことをしゃべった。それが牛さんの記憶のアーカイブに火をつけたようだ。牛さんはその昔学園祭にJ・ホールトリオを呼んだ経験がある。勿論本物である。
カテゴリー: ディスクレビュー by牛さん
名盤・迷盤・想い出盤 Oscar Peterson Trio『シェークスピア・フェスティヴァル』

想像するに、ピーターソンを楽しめるようになるまで、かなりの年月を要したというジャズ・ファンは結構いるのではないか。筆者もその一人であることを認める。非の打ち処ろのないこのピアニストに戸惑う理由は夫々あるのだろうが、多くはこの人の完全無欠なことにその一因があるように思う。特に若いころは、ジャズの不健全さや混沌とした処に鼻を利かせたいと思うようなこともあり、それが見当たらないとなると、自然と離ればなれになるのかも知れない。とは言え、人は伊達に齢をとることばかりではない。かつては音数の多さで腹いっぱいと感じていたことも、今は聴きどころと捉えられるし、一方で彼は上質のバラードを数多く残している。ピーターソンは夥しい数の音源を残している。筆者はそれほど多くを所持しておらず、しかも1970年代以降のpablo盤は殆んど聴いていない。そういう貧弱な事情にあるとは言え、この1枚となると悩んでしまった。ここは戦うライブ・バーLBに敬意を表し、ライブ盤にすることを決め込んだ次第である。本作はベースR・ブラウン・ギターH・エリスのトリオであるが、三者とも全開で猛烈なスインガーぶりを発揮しており、豪快にドライブするものから寛いだものまでバランスがよく、飽きてるヒマがないというのが率直な感想だ。聴き進むほどにボリュームをがっつり上げてしまった。ピータソンもブラウンも文句なしだが、エリスの貢献を称えなくてはいけないだろう。この人はリーダー作において出来不出来のムラがあると感ずるが、ここでは彼の実力が余すことなく収められている。このアルバムが傑出したものになっているのは、エリスの寄与が奏功して白熱のインタープレイが描き出されているからではないか思うのである。本盤シメの最終曲「52番街のテーマ」を聴いていると、まぁよく3人とも指がもつれることなく、こんな統制乱れぬ高速コラボ出来ますねぇと言いたくなる。一度は聴いて頂きたいと思うが、何せこの名盤コーナーは書き手の自伝めいた推薦盤の意味合いが強く、客観性は甚だ怪しい。本格的な批評を知りたければ、豊富なデータと知見に基づく専門家の記述を当るのも良いかも知れないが、でもやっぱり聴いみることに真実を見つけようではないか。なおpablo盤は良識ある皆さんにお任せする。
最後に手前みそだが、蘇ってしまった蛇足で締めよう。多分20年くらい前のことだ。それはLazyの前身Groovyで12月にお客さん選抜の忘年会があった時のこと。そこには個々人のセンスらしきを確かめるクイズの時間が用意されてたのだ。その中に参集者からの2人対決という設定があり、設問は「何々と言えば誰?」というものだった。その時、筆者は「渋いドラマーと言えば誰?」という崖に立たされたのだ。即刻カウントが入り、間髪入れず2人一斉に答えねばならない。咄嗟に「エド・シグペン」と言ってしまった。場はキョトンとした。このシグペンさん、エリスの後任になった人である。何故シグペンさんと言ってしまったかと云えば、出かける前にピーターソン・トリオを聴いていたからだ。今般各種ピーターソンを聴き続けていて、あの時の光景が息を吹き返してきた。それに併せてシグペンさんと纏めて再開を果たすことが出来た。懐かしくも照れくさい話であるが、人間万事こんなもんだな。
(JAZZ放談員)
Master’s comment notice
ピータソンはNHKの音楽番組によく出ていたので小さいころから名前は知っていた。だがジャズのめり込むようになってもピータソンは後回しになっていた。牛さんも罹患していたピータソン症候群という心の病である。テクニックもある、歌心もある、強力にスイングする、どこが悪いのか・・・と詰め寄られてももじもじしてしまうのである。ところがある年になると普通に楽しめるようになる。分野は違うが大人になり切れない症状にピータパン症候群という病名がもある。
付記
牛さん20年前の忘年会の問題よく覚えていましたね。ここでは「渋いドラマー」の渋いが味噌である。問題が「ドラマーといえば」だとすると答えはエルビンとかマックス・ローチとかと答える回答者が多いが「渋い」をつけると回答者は迷うのである。牛さんはそこに引っかかったようである。相手は確かS原だった様な気がする。
名盤・迷盤・想い出盤 Eric Dolphy『At The Five Spot Vol.&2』
名盤・迷盤・想い出盤 Eric Dolphy『At The Five Spot Vol.&2』
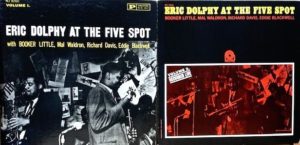
本盤は初めてのドルフィー体験だった。JAZZとの付き合いは日が浅い時のことだ。ドルフィーの音色に戸惑いながらも、このライブ・レコードが発散する熱気は忘れられない。よくあることだが聴いていれば慣れてくるものだ。この慣れは先入観が醸成されるという厄介な面もあり、用心しなければならない。さてドルフィーのリーダー作は、押しなべて評価が高いが、ドルフィーと言えば、真っ先にこの作品を思い浮かべる。しかもこの「Five Spot」はドルフィーの最上位に属すると言われ、特に、Vol.1が一般的に高評価を得ている。ただこのLIVE演奏の全貌を掴むためにも、Vol.2(「Aggression」と「Like Someone In Love」)まで一気に聴いてみることをお薦めしたい。5人の独立した個性が交錯するこのアルバムは、スピーカー越しに、目の前で演奏しているかのような錯覚に浸ることを可能にしている。会場にはさほど大勢が詰めかけたとは思えないが、これはレコーデイングされたことによって歴史的な共有財産となり、その残高は増加こそすれ減少することはないだろう。かくして本稿は無難なエンディングに向かう。だが、ここからがいけない。折角のドルフィーという余勢に押されて、他のアルバムを聴いてみようという誘惑に駆られ、日頃の単発聴きをうっちゃって、立て続けに彼の作品を聴いてみることにした。すると、かつて彼から受けた異質の重力空間に引き込まれるような軽い船酔い感覚が、今は薄れてしまっていることに気が付いた。ドルフィーに限らず、これは必ずしも好ましい兆候ではない。何故なら、新たな発見の芽を摘んでしまい兼ねないからだ。一概には言えないが、多くのアルバムにおいてよくよく聴いていれば新たな発見が間々あるのだ。それはともあれ事態が悪化したのは固め聴きしている内に、エリック・ドルフィーとは何者なのかと思い始めたあたりからだ。というのは、彼に多大な影響を与えたとされるパーカーやオーネットのことが気になり始めたのだ。この流れは幾度となく嵌まった「思うツボ」というヤツだ。この歴史的2人を今々考えて置かなくてはならないのは気が重い。私事でで申し訳ないが、ここんところ関節がガタ来るというリアリズムの下にあって苦慮している。情けない思いの延長で、こんな風なところに行きついた。仮に演奏に人の動作を司どる関節があるとしたらどうなるのか。パーカーは誰も踏み込まなかった次元で関節のフル活用を試み、オーネットは自在に関節を外し・戻ししたら何が生まれて来るかを問うていたのだろうぐらいのことだ。これは何度も堂々巡りしてきた凡庸な帰結ではある。では2人の巨人の影響下でドルフィーは何を発していこうとしたのか。誰しもが思うように、前世代の演奏を未来化することである。革新を試みる演奏家はこのパターンから逃れられない。ドルフィーの突出した成功は、前世代つまり集積された伝統への敬意を、演奏アイディアの核心に据えて手放さなかったことにあると思われる。彼の演奏には斬新さの中に何処となくトラディショナルな音楽への懐かしさがあるように感ずる。これは素人の感想であるが納得している。長々と眠たい話をしてしまったが、目をこすって付け加えておきたい。筆者はドルフィーの岩盤支持層に属してはいないので何でもかんでも礼賛してはいないが、この選定盤「 Five Spot」には短命にして世を去ったtpブッカー・リトルが参加していて、彼の最良の演奏が捉えられている。かつてF・トリュフォー監督は若きジェームス・ディーンの死に寄せて「彼は撮影が終わる前に楽屋を出て行ってしまった」というような一言を添えていたが、リトルに重なる。本盤は名盤であるとともに貴重盤としての価値も備わっている。
(JAZZ放談員)
master’s comment notice
思い出話を2題。このアルバムでベースを弾いているR・ディビスのコンサートを主催したことがある。この日のことを是非聴きたいと思っていた。「それより、今日のライブはどうだった」と窘められてしまった。その日のライブはローランド・ハナ、フレディ・ウエイツのトリオだった。松風紘一さんにドルフィーの音使いに特化したクリニックをやってもらったことがある。突飛な音使いはなくて跳躍させるとドルフィーの音使いのようになると実際吹いて見せてくれた。二人とも昨年亡くなった。
新譜紹介 松本治feat.大野えり『Duke On The Winds』
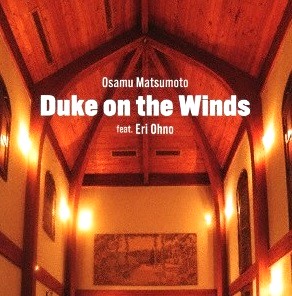
まず告白しておく。エリントンの楽曲を収めた作品は数多くあるが、ここに紹介するアルバムのような演奏集は身に覚え、いや耳に覚えがない。しかし絶え間なくエリントン感に溢れたものとなっているので、個人的な聴き歴に照らし、これまでにないアプローチが意図されたと推察しなくてはいけない。編成は管楽器(Wind)6名とVocal(大野えり)&Bass(米木康志)で、それを指揮しているのが松本治氏だ。ご存知のとおり大野えりは、その歌唱表現力において群を抜いたシンガーである。だが、その事を軸にしてこのアルバムを聴くと、聴き誤るように思う。ここにはVocalを如何に際立たせるかとういう既定の方法論が持ち込まれていないため、この6管はVocalを盛り立てることを目的としたアンサンブルに終始することにはなっていない。それどころか、6管の調和の中で夫々の管奏者が真摯に挑発していくバリエーションが凄まじく、それだけでも聴き応え十分だ。そこに参入する 大野えりは、自己主張を抑制し、管セクションとの融合を徹底的に追求している。そのことが逆に彼女の存在感を高めているという理解も成り立つだろう。このアルバムを数度聴き終えて、少し呆気にとられてしまっているのを感じたので、ためらうことなく1930年代のエリントンを聴き直してみることにした。古きエリントンの神のみえざる手は2000年代の今日にあっても、音楽の可能性に対する影響力を行使し続けているという感慨が湧いて来た。この作品『Duke On The Winds』は高度に設計されていると同時に斬新さが満載されており、エリントン音楽から引き出された今日的到達点を端的に示すものであるということを結論としよう。驚きの本歌取りアルバムが誕生したものだ。
(JAZZ放談員)
master’s comment notice
盟友米木から送られてきたアルバムである。松本のアレンジが素晴らしいと米木には伝えた。エリントンの音楽が初期のもであっても印象派の響きまで内包する音楽であったと再認識させられるつくりになっている。牛さんの評論がアルバムくらい素晴らしい。
2023.11.16~ 初冬の大催しat 常設会場

11.16松島4 11.17松島・鈴木5 11.19本山Special5
松島啓之(tp)鈴木央紹(ts)本山禎朗(p)三嶋大輝(b)竹村一哲(ds)
「LIVEどうだった?」に対し「聴けば分かる」という受け答えは横着だが、「何食べたい?」「任せるわ」というのとは違っている。前者がその模様を言葉対置出来ずに口惜しさを滲ませているのに対し、後者は相手任せの受け流しだからだ。実のところ、この大催しから「聴けば分かる」と言ってしまいたい心境にある。まだその場にいる気分から抜け出せていないのだ。数日経ているのに客観視できずに苦慮している。いかんいかん、熱いうちに何か言っておくことは、冷める前に食うのと同じように基本的な向き合い方だ。苦肉の策を考えねばならない。そこで本節はLIVEに足を運んだという「事実」が、聴くにつれ音の「真実」に近づいているかも知れないという感触を手懸かりにしよう。この大催しは入魂の長丁場企画だったが、残念ながら初日のワン・ホーンカルテットの一日とそれに続くリーダー交代の2管クインテットの二日間に限ったものになった。プラス1本予定していたが、天気予報が的中して口惜しくも「地上の愛」に見放され、身動きが取れなくなってしまった。余談はさて置き、筆者はいま初日の松島4の1曲目にいる気分だが、松島は1発で仕留めにかかってきた。何ともこのブリリアントさは彼の独占市場である。ハード・バップを消化した演奏家にしか表現出来ない迸る熱気がそこにある。それは突き刺さってくるというより、この身を包んでくれると言ったほうが相応しい。清濁が相半ばする日常が一気に吹っ飛んでしまうな。最後の最後まで「聴けば分かる」としか言いようがない。息つく間もなく筆者はいまクインテットの二日間を目の前にしている。黄金のフロント2管だ。ここでは鈴木に焦点を合わせてみよう。今年は3度目になるが、長らく解けずいたものを感じていた。それは専らこちら側の問題である。彼から伝わって来る胸打つものの正体をあと一歩見つけられずにいたのだ。そのことを説明するために、短かく余計なひと回りをすることをお許し願いたい。私たちは縦書き・横書き問わず殆んど抵抗なしに読み書きする特異な言語文化圏に属している。このことに関連するのだが、音楽は左から右へと譜面に沿って流れつつ、数オクターブ内をあちこち行き来するが基本的には横の流れだと考えている。これは演奏についても同様と思ってきた。前回(9月)に鈴木の演奏を聴いていて、彼は処どころ縦書きのフレーズを持ち込んでいるのではないかという思いが募り始めてきた。これは日本語文化圏から特異的に獲得された鈴木の資質によるものとの思いに辿り着き、今回もその思いに傾いた。筆者は一人よがり気味ではあるが、飽くまで個人的な視点での了解事項になっている。これを再確認する意味でも初冬の大催しは筆者の大催しでもあった。鈴木はLIVEリスナーの重要な含み資産と思っている。その恩恵はこれからも公平に分配されるに違いない。リズム・セクションの3人については割愛するが、勢い「聴けば分かる」の一言にまとめさせて頂こう。演奏曲は、初日「Bop Dream」、「Miles Ahead」,「Festa Mojo」、「Skylark」、「Just Because」、「Dewey‘s Square],「In your Own Sweet Wav」、「Here That Rainy Day」、「In A Sentimental Mood」、「Chaims」、「Stera By Starlight」。二日目「No Room Square」、「Silver’s Serenade」、「Farm Rose」、「Moon Train」、「Lady Luck」、「In A Sentimental Mood」、「Woodin’ You」,「Here That Rainy Day」、「In A Sentimental Mood」、「Chimes」、「Stera By Starlight」,「You Are My Delight」。そして三日目「Amsterdam After Dark」、「On A Clear Day」,「Just Enough」、「Inception」,「Mushroom Boy 」、「Dedicate To O」,「It Could Happen To You」。知る曲知らぬ曲、いっぱい聴かせて頂いた。今の気分は常設会場と同様、ギッシギシのsoldーoutだ。
(M・Flanagan)
Carla Bley 『Live!』
名盤・迷盤・想い出盤 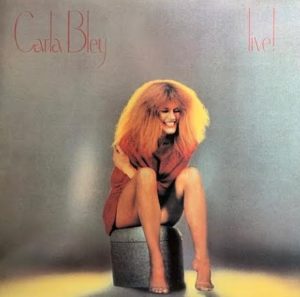
異能の音楽家カーラ・ブレイが他界した。彼女の名を知ったのは50年余り前になる。その頃はROCKのクリームをよく聴いていたので、グループ解散後もメンバーの動向を適度に追っていた。たまたまベースのジャック・ブルースが入っているオムニバスのレコードを見つけ、そのノートを見ていると、キーボードにカーラがクレジットされていた。謂わばROCKの列にヨコ入りしたら彼女の名を見つけてしまったのである。その後、JAZZ聴きに転じて行くことになるのだが、再びカーラ名を目にしたのは「Liberation-Music-Orchestra」だったように記憶している。このバンドを率いているのはチャーリー・ヘイデンだが統制しているのはカーラだ。その後、同バンドは何作かアルバム・リリースしているが、何れもカーラ色に彩られている。この他にも彼女は多様な編成で音源を残しているが、比較的規模の大きい編成のものに魅力を感ずる。そこにはジャズ、ロック、フュージョン、民族音楽など種々の要素を共存させながら、強靭さと緻密さを織り込みつつ、彼女にしかない音楽観を作品に投影させているように見える。カーラの作品は実験的なものも多いが、それは意欲の純粋な表れであって、聴き手が着いて行かなくなるような実験主義を退けている。カーラが手がけるサウンドから管の歌わせ方に絶妙さを感じるのだが、同時にそれは後ろの引き出し方の上手さに釣り合っているのだろう。荒々しさもあれば大らかさもある。時にその幻想性に吞み込まれ、また時には寂寥感に泣かされる。とにかく多彩なのだ。彼女の「ローンズ」や「アイダ・ルピノ」といったEvergreenな楽曲 はこれからも愛聴・愛演されていくだろう。それらの作品が偶然出来たとは思えない。音楽家カーラ・ブレイとは本人自身をアレンジの対象とし続けた生涯を歩んだのではないかという想定が間違いでないとすれば、それらの名曲が生まれたことは、時代ごとに自身と向き合った必然的な成果ではないのか。そう踏めば僅かながら彼女の人物像の一端に触れられた気がしてくる。今回は稀有きわまりない才能がこの世を去りてなお生き続けることを祈り、アレンジ人生中期の傑作『Live!』に行きついてしまった(合掌)。
(ジャズ放談員)
master’s comment notice
田中朋子がレコーディングする際カラー・ブレイの曲をやりたいと言うことで全アルバムを貸したことがある。アルバには入らなかったが札幌でローンズがスタンダードになっている遠因がここにある。
40年以上前になるがカーラ・ブレイオーケストラを一度だけ聞いたことがある。ステーブ・スワロウ、マイクマントラーを擁していた。色彩感あふれるサウンドを今でも覚えている。蛇足であるが僕が主催していたジヤズ幼稚園のオープニングテーマがアイダルピノであった。力量不足でフランス現代音楽のようなハーモニーになっていた。
『Hampton Hawes Trio』
 名盤・迷盤・想い出盤
名盤・迷盤・想い出盤
これはホーズの代表作と言われている。これを初めて聴いた時、普及品のスピーカーにも拘わらず出てくる音がクリアーだと感じたのを覚えている。ホーズの演奏を格別なものに引き立てるといっていい。”compemporary”というレーベルの音質にはその思いが付きまとう。よく知られているようにホーズは軍人として1950年代の前半に数年我が国に駐留し、いくつかの演奏活動を通じて日本のミュージシャン引いてはジャズ・シーンに多大な影響を与えたとされている。このアルバムは帰米後の1955年に録音されたものだが、これを聴けばその影響力の核心に触れることができる。そのスピーディーなスウィング感は抜群の切れ味であり、また「Hanp’s Blues」にみられるブルース・センスは彼独自のものであり、他の曲を含め、何度聴いても飽きがこない。また、ポツンと一軒家のように選曲されている短めのバラード「So in love」はこの若き演奏家の懐の深さを示すものであり、一聴弾き流しているよでありながら、とても片手間で聴くような不埒を許さない。今回、本盤を選定するに当たって立て続けに5,6回聴き続けてみたが、自信をもって推薦したい。ハード・バップ期のホーズの演奏はどれも秀逸であるが、60年以降は輝きを失ってしまったように思う。唯一救われたのは、70年代半ばに制作されたC・ヘイデンとのデュオ・アルバム「As Long As There’s Music」であり、晩年のホーズがやり残したことをこの1枚に凝縮させたのだと思われる。両方とも聴いてみて頂きたい。
ホーズのことを気に留めると、かつて清水くるみさんがLBで演奏したとき、彼女のジャズ研時代に「半分布団干~す」という駄洒落が考案されたとの話を披露していたのを思い出す。他愛のないことを付け加えるが、筆者は今回の選定盤『Hampton Hawes Trio』については時折取り出しては聴いているのだが、長らくスマホのロック画面をこのアルバム・ジャケットにしているので、こちらは日々対面している。
(JAZZ放談員)
Wayne Shorter『Super Nova』
名盤・迷盤・想い出盤
このアルバムを聴くのは久し振りぶりだった。年を取ると5年や6年は”久し振り”とは言わない。二桁に突入してしまうのだ。気が付くと疎遠気味になっていたこのアルバムを何故取り出して来たかというと、古い話になるが、ジャズに熱心でなかったある人物がこの『Super Nova』を凄いと言って、夢中になって聴いていたのを思い出したことによる。これは殆んど怪奇なことなので覚えている。この企画に乗っかったお蔭で、ジャケットの引っ張り引っ込めの動作が以前より増えた。すると内容とは直接関係のない「あの日あの時」的な事柄どもがちゃっかり息を吹き返すことがある。”ある人物”の件もそれに該当する。それはともあれ、今このアルバムについて何か申し上げねばならず、早速苦境に追い込まれている。ショーターについては、60年代のマイルス・クインテットやそれと並行してリリースしていたリーダー盤を聴く機会は結構あり、またライブでもこの人の名曲が演奏されことが少なくないので、その意味で”久し振り”さは全くない。では苦境に追い込まれるのは何故なのか。よく彼は「黒魔術的」と評されるが、筆者は「黒魔術」なるものを知らないし、ショーターの神秘性を高めるための修飾ぐらいにしか思っていない。敢えて言えば、他の誰も持ち合わせていない作風を生み出す主(ぬし)らしいことは間違いないという感じだ。”他の誰も持ち合わせていない”とは独創的ということだが、筆者はその独創性の出どころに恣意的に思い巡らそうとしている。この『Super Nova』が録音されたのは1969年である。世界中で既成の価値観を問い直すムーブメントが起こる混沌とした時代と言われている。その混沌とした時代の共通語として例えば”ラジカル”という言葉があったように思うが、それの象徴的一語もやがて流行語化の道を辿ると、その生命力が失われてしまう以外に行先はなくなってしまうように思う。いまその混沌の時代とショーターの関係に遮二無二焦点を合わせようとしているのだが、その時代はショーターが影響されたとされるコルトレーンの没後2年ぐらいのことである。漠たる思いだが、彼はコルトレーン的なるものを更に先鋭化しようとは思わなかったに違いないのだが、このことはコルトレーンに見切りをつけたということを意味するものではない。様々なジャズに接していると、自身の表現力に磨きをかけ続け、そして人々に感動を送り続ける才人に出会うことができる。その中には時代を動かすことのできる能力を併せ持った才人がいる。ショーターはその一人であろう。彼の感性は古着(伝統)を着こなしながら、同時にそれをニュー・モード(変革)に連結させる離れ業をやってのけている。どうやら筆者が言いたいのは、普通であれば人が時代に多くを制約されてしまうところ、ショーターの場合は彼自身の手によって時代を補正したのではないかということらしい。いま普段使わない脳を煽ったせいで、我がアダムス・アップル周辺がカラカラに乾いてきた。これ以上なす術がないので、『Super Nova』について何んか言っておこう。この作品はブラジル色が立ち込めているが、1曲目の標題曲はショーターの激情的演奏に加え、ドラムスとギターが緊急事態の発生を告知するようで、聴く者を一種の焦りに包み込む演奏となっている。『Super Nova』にハマル者はこの曲で必殺状態にされるのだと思う。また、3曲目にジョビンの名曲「DINDI」が配されているが、歌のMaria Bookerが最後には泣き出してしまう異様な瞬間がある。後にショーターとこの人は結ばれるという話だ。これは公然と泣き落としに成功したハチの一刺しと言うべき名演中の迷演である。今回ショーターのことを考えていて筆者の盤面がスリ減ってきそうになっている。暫くはショーターからスーパー野放しになっていたいものだ。
(JAZZ放談員)
Master’s comment notice
このアルバムは聴く人の感性を試す。1曲めのショーターのたたみかけるようなソプラノと奔放なバックの動きをこの人たち何してるのだろうと指をくわえて聴いていた。新しい・・・でもそれを的確に言い当てる事が出来ない知的脆弱さを感じていた。だがここに出てくる”ある人物”の様にすんなり受け付けられる人もいる。聴く側にある種の分断を産むアルバムである。
『The New Miles Davis Quintet』
名盤・迷盤・想い出盤
このアルバム『The New Miles Davis Quintet』と聞いてすぐにピンと来ないかも知れない。通称「小川のマイルス」と言われているようだ。近づいてみると、ジャケットは全面ブルー(グリーンもある)を基調に木々と鬱蒼とした茂みに挟まれて静かに川が流れていて、中央に白ヌキで大きくMILESと描かれているシンプルなものだ。ああ、あれか”ということになっただろうか。名盤を冠するなら、他にいいのが有るだろうという声が聞こえてくる。だが、「カインド・オブ・ブルー」のような隙の見当たらない金字塔は語り尽くされている。従って、迂闊なことを言おうものなら、突っ込まれる。それが理由で避けた訳ではない。このアルバムが世間的にどのような評価となっているか分からないが、1955年録音のこの作品は、何かの始まりを予感させる雰囲気が漂っていて、興味深さでは上位に来て然るべきという思いがある。これは、マラソン・セッションにとして実を結ぶことになるQuintetの記念すべき第一作であり、後の成果に結実する原型がここにある。因みにメンバーにはコルトレーンが参加していて注目されるが、何やらマイルス邸に居候させてもらっている身のようで、遠慮したのか特に際立つものはないように思う。この段階では後に自己を確立し、行くところまで行ってしまう彼を覗い知ることは出来ない。ところでいつ頃からマイルスが「帝王」と言われるようになったか知らないが、このアルバムを聴いていると、「帝王」とまで言わなくとも自身の演るべきことの狙いは明確になっていて、ハード・バップ期の熱弁を振るうような賑わいに満ちたサウンドとは明らかに一線を画している。彼は掘り下げるという行為に労を割くことは、音楽家の基礎的ミッションと生涯考えていたに違いないのだが、その野心的な気性とは対照的に練り込まれた品格溢れる作品を積み重ねていく。このアルバムはマイルスが50年代の自画像に確信をもって絵筆を入れようとする記念碑的な一作といえるだろう。どれも粒揃いの演奏が繰り広げられているが、中でも「There Is No Greater Love」はマイルスならではの稀有な解釈と言える。謙虚な気持ちで向き合える味わい深いアルバムとして選定させていただいた。
(JAZZ放談員)
Master’s comment notice
この時期のマイルスは徹頭徹尾「歌」に拘っている。どう頑張ってもガレスピーの技術に追い付かなかったマイルスが技術と生産力の均衡点を見つけた時期でもある。マラソンセッションはどのアルバムも素晴らしいがこのアルバムを持ってくるあたり牛さんの包丁さばきの見せどころである。旬であれば秋刀魚でもマグロと同等の旨さを引き出すようにさばいて見せましょう・・・と言う事である
Art Blakey & J・M『Saint Germain』
名盤・迷盤・想い出盤
この『Saint Germain』は、ジャズ・メッセンジャーズの中でで初めて入手したと記憶している。周知のとおりこのコンボはメンバーの変遷を繰り返しながら息の長い活動を継続し、多くの名作を残している。アート・ブレイキーはドラマーとしての名声ばかりではなく、新たな才能の発掘によって演奏鮮度を堅持しながら時代を乗り越えてきたと腰の据わった大物だ。とりわけ1950年代の中後期は白熱そのものである。よく言われるように、ブレイキーはメンバーを纏める面でのリーダーとして存在し、音楽コンセプトは他のメンバーに託している。本作ではその役割をベニー・ゴルソンに充てている。このコンボの前にはホレス・シルバーが、後にはウエイン・ショーターがそれを担っていたのだが、明らかに白熱の質が異なっているのが分かる。それぞれの代ごとに引きも切らぬ名演が残されているにも関わらず、何故このアルバムを選定したのか。その理由は「モーニン」が入っていだけでこのアルバムを手に入れ、何度も聴いた過去の思い出にせかされたからだ。恥ずかしいことに、その時点では「モーニン」を朝の「モーニング」のことだと思っていた。娘ならぬ”モーニング息子”だったのである。それはさて置き、このアルバムには100発100中の勢いで飛躍を遂げているリー・モーガンが入っている。彼はブレイキー親分の煽りに一歩も引かず渡り合っていて、その天才ぶりを如何なく発揮している。ここで彼に焦点を合わせると長話になりそうだ。いずれモーガンのアルバムを採り上げることもありそうなので、今回は彼について控えることにする。実は筆者がこのアルバムの最大の聴きどころにしていたのがピアノのボビー・ティモンズである。この人の醸し出すファンキーなノリは呆れんばかりだ。唯でさえ熱いこのコンボが、ティモンズによって更にそのメーターを上げているのだ。筆者はこのアルバムを回すと、早くティモンズのソロが来てほしいという気分になる。こういう聴き方は変則的に思われるかも知れないが、私たちは聴きどころを探しながら聴くという欲求から離れることは出来ない。。ボビー・ティモンズというピアニストは、革新的な功績を残すようなことはなかったにせよ、自分を出し切るということにおいて、賞賛されるべき演奏家だと思う。数ある「モーニン」の中でこのアルバムのパフォーマンスがベストだ思う。また、収録されている他の曲も引けを取らない出来栄えである。加えてバッチリ捉えられている会場の雰囲気も申し分なく、ライブ盤としての値打ちも大ホールものに競り負けない一級品である。ブレイキー御大にあまり触れずじまいになってしまったので、その代わり数年前の話しにズーム・インしてみよう。LBライブに訪れていた原大力に、ドラム上達志願者が「どんなトレーニングをしたら良いでしょうか?」、原曰く「アート・ブレイキーを聴き込めよ」。原はジャズのそしてジャズ・ドラムのエッセンスについて、自身の体験をもとに一言添えたのだろう。
(JAZZ放談員)
Master’s comment notice
僕はA.ブレイキーのライブを聴いたのは一度だけであるがブレイキーがいなかったら日本でこんなにjazzが隆盛することは無かったのではと思っている。このアルバムの時代は「蕎麦屋の出前も口ずさむモーニン」というキャッチコピーをよく聞いた。ブレイキーのバンドは若手の登竜門でもありいつの時代も溌溂としているがこの時期は黄金期である。パリで受けに受けているのが伝わってくる。ティモンズが素晴らしくて失神者が出たというエピソードを聴いたことが有る。groovyを引き継ぎ「モーニン」のリクエストを受けた時初めてもっていないことに気が付いた。レコード店に買いに行った時店長から「盤痛めたのですか・・・」と聞かれ「すり減ったので2枚目・・・」とか言ってカッコつけたことを思い出す。
